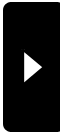『週明け月曜日の夜から火曜日にかけて警報級の降雪の可能性有り』とは天気予報では言っていたものの、『火曜日の朝は起きたら真っ白なんじゃろか?』と覚悟していたが、そんな事は無く風は強いものの雪は積もる事は無くしかも朝から気温が高いため直ぐ雨になってしまった。
市街地は雪にならなくても自分は良いが、スキー場には降ってくれ…
------------------
さて、さて、さて、例年なら自転車(ロード)は春まで冬眠、ってとこだけど、今年は雪も降らず気温も高めってことで組み立てたディスクロード車の試走をすることに。

時系列的には書いてるのが前後しちゃうけど、試走した後にバーテープを巻いて重量を計ったが、実質的に走行できる完成車状態での重量は8.53㎏。
ボトルケージ2個、ペダル、サイコン、サイコンマウント、ベル、後リフレクター有りでの重量。
------------------
走ったのは先週で、バーテープを巻く前のポジション確認ってことで走った。
走ったコースは篠ノ井橋→千曲川CR→斉の森交差点から姨捨駅へ上り→千曲川展望台まで。
千曲川展望台まで上って帰り道は403号を下ろうと思ったが、上ってる最中の日陰部分の路面が湿っていた為、日陰部分が多い403号だと霜や塩カルが撒かれてる可能性が高いので日当たりの良い来た道を戻る。で
------------------
とりあえず千曲川CRを南下。風はほぼ無し。30㎞/h目安で走行。車重自体が重いってのも有るが、組んだばかりでグリスがなじんでいないので、ハブ、クランクの回りが重い…
※1/13のシクロクロスレース以後、全く自転車に乗ってない+防寒装備で動きづらく、重いってのもあります。
グリスなじませる方向で回す感じで、ガチャガチャシフトも動かし、ブレーキも掛けたり放したりの慣らしをやってきながら姨捨方向へ。
まずヒルクライム用の車体より絶対的に重量があるってのが最大のマイナスポイントだけれども、反面グレードの低いフレーム(フレームの詳細はまたで)って事もあって?柔らかいからか、乗り心地は良い。サイクリングロードの舗装の繋ぎ目等を通過してもアルミフレームの『コン、コン』ともヒルクライム用のカーボンの『コッ、コッ』とも違う『モッ、モッ』って訳の分からん擬音での表現だけれどもフレームとハンドルで振動を吸収?分散?してるので自分の体にはあまり振動が来ない。
ヒルクライム用の車体のハンドルバーはアルミだが、今回使ったカーボンハンドルはポジションも合うのでヒルクライム用のもコレに換える予定。腕を乗せるハンドル上部もやはりフラットになっていると腕とバーが点接触じゃなく面接触となり、滑らないのでやっぱ楽。
------------------
斉の森交差点から上り開始。距離2.4㎞、平均勾配7.5%。
心拍数が170~と上がって真面目に上るけど、やっぱ重い。。。
ヒルクライムシーズンでの練習走行ならココはチェーンリングアウターで上ってるが、今日は早々にインナーへ落っことし…あ、この車体にはパワーメーターは付いてません
------------------
最初の坂区間を上って姨捨駅前の平坦部で脚を休ませ展望台までの上り 距離0.9㎞ 8~17%の勾配 平均勾配11%の区間へ。
ここは普段ならフロントチェーンリングアウターで上り始め、半分くらいまで行ったらインナーに落とす。だけど、今日は最初っからインナーで上り始め。
『えっほ、えっほ』踏んでも普段よりどうにも遅いが、それでも踏めば進んでる。(空回ってる感、力が下方向に吸われてる感は無く、前に進んでる)
フロントはインナーに落としてはいるけど、スプロケの方は重いギヤにしていつものようにダンシングで行ってみる。自分はあまり車体を左右に振ったりフロントをこじったりなダンシングはしてないと思うけど、体重70㎏近い人間が17%位の勾配でダンシングしてもBBから『パキ、パキ』音がしたり、ブレーキパッドとディスクローターが擦れて『シャリ、シャリ』鳴ったりはしない。それなりに丈夫には組んであります。
千曲川展望台に到着ー。(…止まって休憩はしないから写真は無いよ)
『ま、予想通りリムブレーキのヒルクライム用の車体みたいに走る』って訳もなく、タイムも出ないわな。(この時期、このコンディションでタイム出てたらヤバいが)
------------------
『ポジションはこれで良さそうだなー』ってことで帰ってバーテープを巻く。
------------------
で、別の日の話になるけど『じゃあ、雪が無いって所で茶臼山でも上ろうか』と。
茶臼山へ。信里小か川カンへ行くかで分岐するY字の先の所がいつも日当たりが悪いのでそこが霜が残ってるようならそこまでって事でスタート。
普段なら動物園の有る表側ならフロントアウター縛りでイケるけど、今回は中間の材木所~宅老所の辺でインナーに落とす。そこを通過後は動物園手前のストレートの所で再度アウターに入れ、路面状況も悪くなかったので頂上の信里小まで。
下の火の見やぐらまで下ってきてUターンしておかわり。2本目は(速度は全く出ないものの)アウター縛りで上まで行けた。『おぅふ。2本目で疲れてるはずなのにそれでもなんとか踏んでいけるんじゃん』っと。
下り走行中は軽いギヤでクランク回してクランクのグリス飛ばしで。ある程度回転部も馴染んできたので帰りの平坦路は組んだ直後に比べてかなり回りも軽くなったな。
------------------
ちょいっと乗ってみてのディスクロードの感想としては・・・
〇『ジャンルを細かく分けなきゃダメなのかなー』と。
ロードバイク(っぽい)所からシクロクロス、グラベルロードと分かれたように『ロードバイクのヒルクライム向けのリムブレーキ車』と、『ロードバイクのロードレース、ロングライド向けディスクブレーキ車』ってふうに別物として分けなきゃなのかと。
ヒルクライム(レース)として考えると、『ヒルクライムレース』ってのが上り坂を走って上りきるタイムを競うレースなので、以前書いた通りどうにも上ってるレース走行中は(基本的に危険回避をする時位しか)ブレーキをかけないからディスクブレーキの恩恵がはっきり言って全く無い。『雨の時でもよく効くディスクブレーキ』っていっても雨のレースでもそもそもブレーキをかける事が無いのでそれもメリットにならない。レース終了後の下山はゆっくり下れば良いだけの事。
(細かくいうと自分の出てるヒルクライムレースだとツール・ド・美ヶ原ではスタートして最初信号を右折する時や、17㎞過ぎに下り区間があるのでそこら辺はブレーキはかける)
『ヒルクライムの上りだけじゃなくて下りもあるロードレースで(またはロングライド等で)走るので下りで楽に走って体力を回復させたい、下りでアタックしてタイム稼ぎたい』って状況で走るならディスクかと。
------------------
『(このメーカーの)このモデルが乗りたい!』って決めてるならそれがリムブレーキでもディスクでも構わずいっていいと思う。行けばわかるさだけど、リムブレーキかディスクかで迷ってる人なら『自分はその車体を買ったら何処をどんなふうに走るのか』を考えて。
現状だとリムブレーキ仕様とディスクブレーキ仕様の両方を出してるメーカーもありますが、『ヒルクライムレースメインでタイム出す(他の人と競る)のを目標にしたい』ってなら軽量化の沼にどっぷり浸かってしまい抜け出せなくなると最終的には『1g削るに○○千円かけました。インナーワイヤーのエンドキャップを使わず0.3g軽量化』等の言葉が普通に出るようになります。その場合にはディスクブレーキシステムは重量物以外の何物でもありません。(というか多分そこまで行く前にディスク車体を売り払ってリムブレーキ車体を再購入してるはず)
『ヒルクライムレースだけじゃなくて、1台の車体で色々やりたい』ってなら登坂能力は落ちるのを覚悟でディスクもアリ。(それでも速い人は速いが…)
自分も実際乗ってみて『山でもタイム出す走りじゃなきゃ上ることは出来る』ってのは色々実証済み。それに下り走行で指の第二関節までの力でブレーキコントロールできるのは楽。
『ヒルクライムの練習ー』じゃなくて『上り下りのあるルートを走るー』ってならディスク車で多分行くよ。
------------------
販売サイド的にどうしてもディスクロードを広めたいならヒルクライムレースでなら『ディスクブレーキ クラス』を作るしかないのでは?最低重量を(例えば6.8㎏とかに)設定して、『それより軽いディスク車はリムブレーキ クラスで走って下さいねー。』ってするとかは必要だと思うけど…
『下りではディスクブレーキの方がメリットが有る』からと言って、下りもあるロードレースにしちゃうとコースの確保も難しいし、下りで落車事故起きまくって『自転車自体が危ない物』と決めつけられる…かといって平坦基調のクリテリウムを新たに開催するとなると出来る場所(道)の確保が難しい…サーキットコースを借り切るだと開催場所が限られる…
どうしてもこっち(ヒルクライムレース)寄りな意見になってしまうけど、ヒルクライムレースメインで走ってる人なら『ヒルクライムレース用の車体として、タイム出しに行くならリムブレーキとディスク、両方の仕様が有ったらどっち買う?』って聞かれたらやっぱ現状ならまだリムブレーキを選ぶでしょ。
どこかがどこかに圧力かけてリムブレーキの車体やパーツを出さなくさせない限りはまだリムブレーキには乗れるしね。
ヒルクライムっていう一つのジャンル、『上ったら終わり』って特殊な走行状況だからやっぱそうなるんじゃないかな。
昨日(1/24)の大相撲 十三日目の炎鵬は上手い足取りからの押しだった。
155㎏の相手を持ち上げてるように見えるけど、そうじゃなくて相手の片足を取って、相手がケンケンして宙に浮いてるところを斜めから押すっていう絶妙なタイミング。相手が自らを宙に浮かせてるので相手の力を利用しての押しっていう。それに押しに行っても炎鵬は両足をしっかり土俵の中に残してる。全力でも冷静。
今日のは大栄翔の下に潜れず距離を取られ、土俵際でも押しに来る相手の勢いを利用して回って回ってだったけど突かれ負け。それでも最後の最後まで粘る土俵際は勝ちでも負けでも『ん――!おお~!!』っと見てると思わず声が出る。
それに比べ土俵際に押されたら上体を起こして背中伸ばしてたらダメなんじゃないか?御嶽海…
------------------
さて、さて、さて、順番的には前回でハンドル、レバーの組立が終わってるけど、今回はSTIレバーの方を。
今回組んだSTIレバーはST-R8020。油圧ブレーキで機械式変速。
訳アリの新車取り外し品で訳ってのが5㎜以下の小さなキズがあった物って事で定価の半額位で購入。
シクロクロスの方で油圧ブレーキレバーST-RS685を使っているけど、685は初期モデルってことで、重かったり大きかったり。
ST-RS685の実測重量。カタログ値では左右ペアで649gってなってる。
ちなみの同年のリムブレーキ用機械式レバーST-6800はペアで425g。
油圧だとレバーだけで224g重いって事になる。
ちなみの同年のリムブレーキ用機械式レバーST-6800はペアで425g。
油圧だとレバーだけで224g重いって事になる。
ST-R8020の実測。カタログ値ではペアで554gとのこと。
色々と仕様変更されていて、まずブレーキホースとレバー本体の連結のボルト。
左がST-RS685のボルトでブレーキキャリパーやマウンテン用のレバーの連結ボルトと共通品だったが、右側のフランジボルトに変わってる。スペーサーも追加されてる。ボルトのサイズ、ネジピッチが違うため互換性はありません。
ブレーキオイルを補充するフタになるボルト。ここもネジサイズが変わっていて、エア抜き作業をする際にブリーディングキット(下の画像で右側のじょうご状のもの)に追加で延長アダプター(マニュアルだとファンネルアダプター)を付けないとオイルがダダ漏れ。
他にも調整ネジの位置が変わってたり。
ファンネルアダプターは購入しとかないとエア抜き作業が出来ないので注意。
------------------
組立作業的には新旧モデルで大きく変わってる所は無いが、ちょこっと注意する点といえば、まずホースにインサートコネクターを入れる所、バイスに挟んで打ち込む場合
インサートコネクターを打ち込んだ後でもオリーブは抜くことが出来るのでバイスを開放する前にオリーブは外しときましょう。
オリーブを外さずにバイスを開放してしまうとホースの巻きぐせが戻る力でバヒューンとオリーブが吹っ飛んでいきます。
------------------
ブレーキホースがハンドルバーに内装する場合、レバーとホースの連結作業をする時はハンドルバーにはレバー本体を取り付けずに連結作業をした方が組込ミスが防げるかと。(マニュアルだと内装じゃないハンドルバーに添わせる場合でのみ説明されてますが)
こんな感じでレバー側と接続しますが
マニュアルにも書いてある通り、ホースを真っすぐ押し込みながら最初は工具を使わず手で連結フランジボルトを締めこまないとホースが確実に一番奥に入っていなかったり、オリーブが斜めになった状態でもフランジボルトは締込出来てしまうため、ちゃんと締めこんだつもりでもオイルを入れて握るとオイル漏れになります。(一番最初に一度やらかしました)

『オイルが漏れてきてるから』とそこで増し締めしてもオイル漏れは止まりません。ボルトを外して再組付けになります。その際一度使ったオリーブは再使用できません。一度締め付けてオリーブに締め付けスジが入っているとそこからオイル漏れします。オイル漏れを止めるつもりで無理矢理強く締め込むとネジ山が当然ナメて終わりです。
ブレーキホースは固いのでバーに内装する時にはレバーは取り付けてない方がホースを真っすぐ押し込みやすいと思います。ブレーキキャリパー側もキャリパー本体を車体に取り付けてない方がやっぱりホースを押し込みやすいかと。
------------------
チョイっと走ってレバーの取付位置が決まったためバーテープは巻いた。ゴムゴム的にグリップするのが好みなので今回はリザードスキンの1.8㎜に。
また、あるものを使ってブレーキホース、シフトアウターの色はブラックではなく色付き(赤にしたかったが若干ピンク寄り)にしてます。
全然自転車ネタじゃないけど大相撲の炎鵬が凄い。
身長168㎝、体重99㎏と力士としては超軽量級になるが、身長差20㎝~以上、体重差80㎏~の相手を投げて転ばすっていう…
身長差があり小さいから低い組み位置から相手の重心を崩して投げるって事が出来る技なんだろうけど。
立ち合いも小兵故速く、潰される前に相手の下に潜り込み、土俵際ではギリギリのところで回ってかわすしで、相手の見て動きの先を読んでいて要所要所で相手の勢いを利用する合気道みたいな動きもしてる。力だけでも技だけでもない相撲。舞の海とはまた違う小兵力士。
相手に上から被せられて体重かけられて潰されそうな体勢の時には『首とか肩とか背骨、大丈夫かよ!?』と心配になるが…
------------------
さて、さて、さて、今回はハンドルの方を…
『形状がエアロハンドルで『丸ハンっぽいのないかなー』で探してた。
市場に出てるのはコンパクトハンドルが多いけど、以前にも書いた通り下ハン握りの時にカクっと曲がっている為ブレーキレバー位置が合わない(遠くなる)…

そしたら見つけた。エアロ形状で丸ハンっぽい曲がり形状のカーボンハンドル(中華)。
下ハン部の曲がり具合(赤マル部)がわずかに違うだけだけれども、下ハン時のブレーキレバーのかけやすさ、手首の楽さは段違い。

バーの上部分はステム近くまでバーテープは巻かないが、そのままだと滑りやすくなるためこんなのを使って滑り止めに。
本来は釣り竿の滑り止め用として販売されている熱収縮のラバーグリップ。(カラーバリエーションは黒以外にも有り)取り扱いメーカーは知ってる人は知ってるでしょう『共和ミリオン』。一般車の自転車のタイヤ、チューブを取り扱っているところ。
表示サイズは内径35㎜となっているが、測ると50㎜有るけど…?(最大で1/2まで収縮する)
ドライヤーで温めて収縮させる
バーテープは一度走ってブラケット角度とか確かめてから巻くって事で。
収縮させるとバーにフィットするためズレたりはしない。
バーの上部分をエアロ(フラット)形状の物にしたかったのは、自分は肘付近をバーに乗せるエアロポジション乗りをよくやる為。
------------------
ちなみにシフトは機械式でブレーキは油圧。
『ディスクでレースでの使用が前提なら重量、ブラケット形状のスリムさ等でDi2一択』では有るのだろうけど、今、シマノの11速で電動にしてしまうと、おそらく近々12速化になる可能性があり、どうせ11速との互換性は無いと思われるのでSTIレバー、前後ディレイラー、スプロケ、多分ホイール(フリーハブ)、チェーンが使えなくなったりして?。新型になってまた直ぐ全部積み替えとか自分にゃ金額的に無理。
それもあってすでに12速化、ワイヤレスの『スラムのFORCE eTap AXSが面白そうでいいなー』とは思っていたが、今回は見送り。(スーパークロス野辺山の出店でeTap AXSのサンプルとか有ってガチャガチャ動かしといて、スタッフの人からカタログまでもらってきてたが…)
------------------
『ディスクロードで上り(ヒルクライム)で(ある程度自分が納得するくらいは)タイムが出せるのか?』ってのを今回試しでやっているのだけれど、重量的な点で比べると(余り物のパーツメインで組んでるって事が大きく)速くなる要素は正直まるで無い。
だからといって(軽量な)上のグレードのフレーム、パーツに高額つぎ込んで購入して『やっぱり遅かった…』になるのも怖いため試しでやっている。
カタログスペックではリムブレーキに近い完成車重量のディスク車も有るが、重量だけですべて決まるわけじゃないとは思うが…
フレームのグレードはもしかしたら乗り方によってはトップグレードよりミドルグレードの方が良いなんて事は人によってはあるかもね。
------------------
チェーンリング 50-34T→52-36Tで重量増
スプロケ 30-11T→32-11Tで重量増
Rディレイラー SS→GSで重量増
STIレバー リムブレーキ→油圧で重量増
ホイール ディスクローターが付くので重量増
そもそもフレーム+Fフォークが重量増
これで山上ってタイムアップしちゃったら今まで自分でやってきたことが色々ガラガラ音を立てて崩れちゃうわ…
それでも今年はGRXの48-31Tのチェーンリング使ってのクルクルケイデンス ヒルクライム仕様のディスク車ってのも出てくるんじゃないかな?
さて、さて、さて、とりあえず2019年のレースは終わったわけで、『この戦いが終わったら故郷に帰ってスノースクートの準備をするんだ…』と思っていたけど、雪はまだ積もっていないので『まだ準備してもなぁ…』なので、スノースクートはまだ。
------------------
シクロクロスレースが一区切りついたところで、『雪が積もる前に乗れるならロードに乗っとこう』と2ヶ月ぶりにロードを出して乗ることに。
走ったのは茶臼山。時間があまり無かったので表側の動物園までを2本。表側の動物園までなら日陰部は無いので先日の雨が乾いてなかったり、霜が降りてたりは無いので滑る事は無い。 …が、頂上の信里小までだと日陰部があるので路面凍結があるかも。
完全冬装備なので動きづらいってのがあるし、2ヶ月ぶりにロード乗って山を上ったのでタイムはさっぱり。一応、自分の体調の目安となるアウター縛りで2本とも上れることは出来た。
茶臼山動物園入り口から
朝7時頃の走行だったけど、頭にインナーキャップ、ネックウォーマー、フルカバーのシューズカバーと防寒装備。冷たく感じるのは指先位だったけど、それも山を上り始めると暑い感じにはなる。ネックウォーマーは上る前には外した。
走ったのは4日の朝で、ギリギリプラスの気温だったと思うけど、『5日の夕方から北信も平地で雪』の予報なので、もしかしたら今回がロードで山を上るのは走り納めになるかも…(平地は走んないので…)
------------------
一応、時期なのでこんな事もやってます。リンゴの箱詰め、出荷。
いつもの人から頼まれてる分だけを基本的にやってるので大量ではないけど。
今年はなんせ台風の影響で豊野方面のりんごは少なめではあるけど、(市場に)出てる分で言うと出来は悪くないと思う。
緑色の型紙(業界用語で?『モールド』と言ってるけど)に入れて梱包。13玉位の大きさだと大体2Lサイズか。この1つは形がちょっと良くなかったのでハネた物だけれども切ってみると…
中は問題無し、蜜も有ります。※蜜が有り過ぎだと傷みやすくなるけど。
このリンゴはこの後おいしくいただきました
さて、さて、さて、先週、先々週の連続3連休とか全く関係無く普通に仕事だったけど、通常だと金曜日が基本的には何も無きゃ昼位から仕事は休みになるが、今週は仕事が入ったため代わりに木曜日(今日 26日)の午後が休みになった。
『…台風過ぎて、今週末までは好天続きが確定…それじゃあ…』って事で、マウンテンサイクリングIN乗鞍に出れなかった借りを返しに乗鞍エコーラインに突撃することに。
------------------
準備って言っても着る物とフロアポンプと走り終わった後に軽く車体を拭くためのウエスとワックスを積んで、途中でコンビニで食べ物を買ってく位でサクッと出発。
PCから見た現地、乗鞍観光センター付近のLive温度は11:50頃で24℃だった。
正午頃に長野出発して、道中は渋滞も無しでカーナビ通り14時チョイ前に乗鞍観光センターに着。
国道158号から左折して乗鞍方向に上り始めた所に有る電光掲示板の温度計は20℃の表示。松本市街地は晴れだったが、乗鞍付近は若干雲が多めで陰ると風は強くないが涼しいって感じ。
観光センター前から
------------------
観光センター駐車場は自転車の人が多く停める奥の方は空いてた。さすがに午後になってるので上る人より下りてくる人の方が多い様子。トイレ行って走行準備。
服装は上はノースリーブのインナーに半袖ジャージ、アームカバーに指切りグローブ。下は春秋用のロングビブで。
雨は無さそうだったので下山装備はアームウォーマーとスーパーの大き目なレジ袋(新聞紙みたいに腹の所に入れとくと多少だけど防風になる。小さく畳めるのでかさばらない)のみ。
------------------
で、スタート。
…いつもの練習走行とは違ってフロントアウターのままで三本滝ゲート過ぎまで行けるんだけど、練習用のホイール、タイヤだからかどうにもタイムは出ない。三本滝ゲートまでで22分…
(スキーの)リフトくぐる辺りまで上って来ると汗は出て来るけど、風は涼しいので割と走りやすい。『上ってりゃー暑くなるだろう』と思っていたが、やっぱりそうなりアームカバーは外して頂上まで半袖で走行。
が、走りやすい気温とは裏腹に(自分的に)それなりのペースで上っていくけど位ヶ原山荘ですでに1:00経過…
『こりゃー1:25分ペースだなぁ…』の予想通り1:25でゴール。
------------------
そこまで疲れは無かったので(疲れよりも骨折の影響で体のどこかが部分的に痛くなるって事が無く良かった)またまた雷鳥を探しにちょっとスカイライン側を下る。
ちょっと下ると山側には何か鳥が居るので停まってカメラを用意するが、どうも雷鳥じゃない鳥が多く居るみたい。。。(雷鳥みたいに鳩っぽく丸くなくて細長い鳥。)
停車してると下から雲が上って来る来る…あっという間に先が見えなくなる…
下からの風が冷たいので畳平に戻る。と…
------------------
スカイライン側にも行ってたので畳平には15:50時頃到着。畳平で休憩ー。気温はスマホの温度計で14℃。雲が多く少し風もあるので涼しいではなく、若干寒い。
30分位休憩してたが雲も多く、日が落ちてくるのもあって少し薄暗くなってきたので下山に。『フルフィンガーのグローブ有ってもいいなー』って位の気温。
------------------
木々は少しずつ緑だけじゃなく黄色やオレンジも増えてきてる。
4号カーブにて
------------------
休暇村辺りまで下ってくると木もあるのでフロントライトが有っても良い位な薄暗さ。観光センターまで無事下山っと。
『帰りがけに風呂に入ってこう』と思ってたけど、いつもの所が今日は26日なので(2=ふ 6=ろ の日)で入浴料が安いため激混みなので諦めたのでここで試合終了ー…
------------------
とりあえず乗鞍上れてスッキリした。『上り距離があるので何処か痛くなるかも…』という不安があったけど、それも無しで一安心。『今日位踏めてれば、本番用のホイールでもう一段重いギヤ使えて同じように回せてたかも…』って感触ではあったので来年に期待しとく事に。
じゃあ、次は。と…
さて、さて、さて、ロードの方では普段の走行ではツールボックス1つ有ればスペアチューブ、工具類が入るのでボトルケージ1つで収まるけど、パンク率が高いシクロクロスではスペアチューブを2本持っててチューブの太さも太くかさばる為サドルバッグも追加して普段から付けてた。
※サドルバッグを付けたりした時でもリヤリフレクターかテールライトは必須です。付いてないと違反になります。
付いていてもバッグ等で見えなくては意味が無いので、バッグの後ろに取り付けるか(トピーク等はサドルバッグの後方にクリップ式なんかになっていて自社テールライトを取付出来るようになっている物も有る)シートステイに取り付けましょう。
シートステイに取り付けるなら後ろから見て車道側になる右側後ろにまず取り付けましょう。
左後ろ側に取り付けてしまうと、(左側通行の場合は)後方からくる自動車等からするとフレームや車輪等でリフレクターが影になってしまい視認性が悪くなります。
(一般車の1本スタンド車で多く純正取付されているリヤリフレクターが右後ろ側に付いているのはそのためです。法的にそう決められているのかは分からん。。。)
------------------
※小さめなサドルバッグも初めて購入する時はサドルよりも幅の狭い物を選んだ方が良いかもしれません。
『大きい方がやっぱり入るから良いだろう』と幅の広い物を選んでしまうと、ペダリングする度に太もも後ろにバッグが当たったりするとかなり鬱陶しいです。
------------------
マウンテンの方はシートポストがドロッパーシートポストなのでシートポスト下げるとサドルバッグに当たる為、サドルバッグは付けずにバックパックを背負ってた。
シートポストが高い位置だと問題無いけど…(クローズドコースを走る時にはテールライトは外します)
下げるとベルト部を引きずるようになる。(一番下まで下げなきゃいいんだけれども。。。)
しかしバックパックも背負ってると邪魔だし、サドルバッグもダート走行で激しく左右に揺れてるとモノによってはベルトや車体とのジョイント部が千切れてバッグが落ちかけるので(経験済み)、『何か小さなフレームバッグないかなー』と探してたらコレを見つけました。
------------------
SKS RACER EDGE(レーサーエッジ) フレームバッグ
容量は0.6ℓとの事で、とりあえずこの位は入る。
タイヤレバー3本、小銭入れ、ミニポンプ、CO2の16gボンベ1本、ディレイラーハンガー、CO2のヘッド、パンク修理の時に使うスポーク削ったヤツ。(チューブやヘキサゴン等のミニツール類はもう一つのツールケースの中に入れてる)
小銭入れを止めてポンプもCO2と手入れの兼用のヘッドの物にして、ロードの700×25c位のチューブ1本ならミニツールと共に全部このバッグに入れられるんじゃないかな?
上の画像のを入れてもまだ若干入る。バッグ内部の横面にネットでの仕切りも有る。
ファスナーは左右に付いているのでどちらからでも開けることが可能。
------------------
バッグ自体の寸法は横で最長部 約240㎜
縦が最長部 約80㎜
横幅は取り付けてみた車体(GIANT TCX アルミ)のトップチューブ幅とほぼ同じで約50㎜
------------------
GIANT TCX フレームサイズMに取り付けてみた感じ。
フレームのジオメトリはBB~シートチューブトップ 525㎜、ホリゾンタル換算トップチューブ 545㎜。
ボトルはエリートのコルサで550mℓの物。ボトルを差そうとする状態でもバッグとのクリアランスがあるのでボトルの抜き差しには影響しなさそう。
※『ボトルの抜き差しがしやすそうなヤツ』という小さめなのがバッグを選んでいた条件なのでコレは満足。(大型のフレームバッグなら他にいくらでもある)
------------------
(パッケージ裏面より)向きを変えてヘッドチューブに取り付けたりも出来るとの事。(ヘッドチューブが短めなフレームは取付できないかも)
取り付けるフレーム側にはベルトで擦れて塗装が傷まないように何か保護的な物をフレームに付けた方が良いかも。(TCXはマットブラックだったのでいつもの配線用のテープが目立たないのでソレを巻いたけど。)
また、バッグ本体横のメーカーロゴはリフレクト素材になっているので夜間はライト等で反射します。
------------------
マウンテンには・・・BB~シートチューブトップが短かったり、クマ避けベルが有ったりなので、しょうがないので上下ひっくり返して取付か…(とりあえずマウンテンのコース走行の時には工具を入れなくても良いので、携帯1つ入ればそれで良い。(ジャージの後ろポケットだと落としても気づかなさそうだし、パンツのポケットだと太ももに当たって邪魔だった。+コケた時に液晶画面割れそう)メカトラ等のトラブル時は最悪の場合は押して下る。車まで戻れればどうにかなる。
------------------
CCM(信州シクロクロスミーティング)第1戦の白樺湖にエントリーしました。
(去年まではCM1+2+3という(40歳から60歳代まで速い人、遅い人、全部ひとまとめ)クラスだったけど)今年はレギュレーション改定が有り、M40(男子40歳から44歳まで)クラスへのエントリー。
…レギュレーション改定で競技時間40分、C2と混走ってキッツイなー。
今までのCM1+2+3クラスでもバリバリ現役の実業団で走ってる40代の人や50代、60代の人でも過去にかなりなレースリザルト出してる全く普通じゃない人と同クラスな上、C4クラスで優勝したりして昇格してきたC3の人達と混走(時差スタート)だったのに、今年は単純に年齢で5歳区切りで分けて尚且つ(C3から昇格してきてる)C2クラスとの混走(時差スタート)…
※…だったのだけれど、レース進行表(タイムテーブル)を見るとC2とL1(エリート女子クラス)が先にスタートして1分後にM40、M45が追っかけるという時差スタートだった。(自分だと前に追い付くなんてのはまず無理。)去年まではマスターズの自分達が先にスタートして後ろからC3に追いつかれて突かれるだったのでそれよりは良いか。。。
CM3クラス(40歳以上の初心者クラス)はC4と時差スタート位で丁度良いと思ってたくらいなのに…だからといってC4は自分的には『若い人達同士で競ってレースやって、どんどん経験積んで速くなって上(C3クラス~)に行きなはれ~。超えろワウト・ヴァンアールト、マチュー・ファンデルポール。』と思っているので、一応40歳過ぎててもC4にエントリー出来るけど、エントリーするわけにもいかん…
ブエルタ・ア・エスパーニャも終わったな…「ログリッチ、ユンボ・ヴィズマが強かった。」に尽きる。
ログリッチは各ステージの映像でもチームメイトに守られていた為かほとんどキツそうな表情ってのが無く、淡々と走っていたように見えた。そう見えるがゆえにスタート前、ゴール後でも口を「へ」の字にして無表情、な事も多かったけど、さすがに第21ステージ、マドリードのゴールライン過ぎた後は嬉しそうだったねぇ。「最後まで気を抜かない」ってのがやっと終わった瞬間だったからか。
来期は各チーム大量移籍でどんなシーズンになるか。コレはコレでまた楽しみ。
と、まだ今シーズンのレースは終わってなく、次は世界選手権か。(マチューが大金星上げちゃうかも?)
------------------
さて、さて、さて、シクロクロス車体のTCXのヘッドセットが入荷。(パーツは『在庫切れ』ではなく、送料の関係で荷物がまとまらないと発注出来ないための入荷遅れ)
手前が古パーツ、奥が新品。見た目はそうでもないが、古の方は若干の錆も出てる。
------------------
交換ー。ヘッドカバーの向きは『H2291』って品番が乗車状態で読める向きで組む。
------------------
GIANT独自規格サイズの『OD2』上が1-1/4、下が1-1/2というベアリングサイズなので、一応ヘッドセットと合わせてヘッドスペーサーセット(t=0.25㎜×10枚入)も購入しといた。(普通のオーバーサイズ(1-1/8)なら入手しやすいが、1-1/4だと入手しにくいのでついでに)『どうにも(スペーサーが摩耗したりして)ハンドル引っかかる感じがある』な場合の為用。。※GIANTの公式WEBカタログではぱっと見、分からないけど、t=0.25㎜のスペーサーはOD2用ヘッドセットには一枚付属していました。
これで車体は終わり…シクロクロスミーティングの出れるステージの予定を考えてエントリーしないとな…
------------------
千曲川CRを走ってての一枚。
カラスが多く飛んでるような時期になると路面に落ちてるんですよ。コレが
カラスが多く飛んでるような時期になると路面に落ちてるんですよ。コレが
胡桃の殻
カラスがサイクリングロードの路面に落として割ってたり、農作業の軽トラに踏ませて殻を割ってるんだけど、胡桃の殻は固いので上の写真よりも小さな破片を自転車で踏むとガラスを踏んだのと同じようにパンクします。(運が悪いとタイヤも裂けて即交換)
走ってる時に地面にカラスが集まってる所には胡桃が落ちてる可能性が有るのでチョット避けて走りましょう。
聖を上ってたりすると栗とか大量に落ちてるし。。。実りの秋ですなぁ。。。
さて、さて、さて、コケて骨折して入院から始まって、お盆とか色々あって長かった8月がやっと終わり9月に。
今年のヒルクライムレースへの出場予定は8月最終日曜の乗鞍が最後なので、DNS(出場せず)でシーズン終了ーって事に。これから秋~冬にかけては10月から始まるCCMシリーズ戦、(信州)『シクロクロスミーティング』に出る予定って事でシクロクロスはこれからシーズンinになる。
------------------
体の方は正直まだダートを走るってトコまでは治ってなく、右肩がバンザイし辛い。フルジップタイプのサイクルジャージを着る時にも左腕から着て、右腕を袖に通す時に腕を後ろにした時にまだ痛みが有り、左腕からだと着ることが出来ない。Tシャツなんかも着たり脱いだりで右腕を上げる時に肩が痛みがある。それに出来ない体勢っていうと、『腕立て伏せ』が肩甲骨にかなり力が入る為、まだ痛くて全く出来ない。
肋骨の方は大分良くなり、骨折してた個所が胴の前、右横、右後ろと3ヶ所あったが、前と横の痛みはほぼ無くなった。前側の痛みが無くなったのでクシャミをしても痛くはならず、寝てて起き上がる時(腹筋を使う時)にも痛みは無し。
あとは右後ろの肋骨と肩甲骨が治れば…なトコロ。
体は自然に治ってくのを待つとして、車体の方(TCX)を先にボチボチやっていこうかと。
ブレーキパッド、ブレーキフルード、シフトワイヤーは交換決定で、後は外してみてからってとこで。
------------------
ダート走行はまだ出来なさそうなので、昨日(日曜)の朝は山へとー。時間があったので『ちょっと上り距離を増やそうか』と思って聖へ。
篠ノ井橋→千曲川CR→403号だけで普通に聖湖方向へ上り(激坂区間無し)→聖湖手前の37号カーブでUターンなルート。
山の方はまだ雲がかかっていて、『もしかしたら霧や前日の雨で路面濡れてるかも』な感じだったので『明らかにウエット路面ならそこまででUターンすんべか』って事で。
山にかかってる雲より上に行くって事になる。
いつも自販機コーナーのチョイ先のこの看板から上り始めってことにしてて、サイコンのLapボタンをポチって上り開始ー。
------------------
路面はウエット個所は無かったので(KOMの)37号カーブまで行けたが、雨の影響で路肩側に砂や木の枝が多め。曇り気味だったのでそこまで暑くはなくなってきたね。
茶臼山よりノンストップで上る距離が増えても上れることは上れるが、『満足に走れた』って感触にはまだ程遠い…
さて、さて、さて、iPhoneがバッテリー交換で返ってきたので雨が続く天気で外では自転車には乗れない日は屋内で固定ローラーに乗ってハムスターの気分に。
…と、真面目なトコロ入院してから乗ってない日が多く、骨折してからもう4週間が経過し、ここ最近はボチボチ怪我も治ってきてるので乗れるなら1日30分でも良いから乗るようにしてる。
下に汗が落ちる位は回す。(バッテリー交換から戻ってきたので)スマホで音楽聞きながら乗れるのでほんの少しだけ飽きないで乗ってられる。
------------------
今朝は雨が降ってきそうだったが、『それでも1時間位は天気がもつだろう』と思って、いつもの茶臼山へ。
時間的に1時間位しか走れないので表(動物園側)を2本上るって練習で。
雨は降ってくること無く2本走行。今回は一応、ダンシングが出来るようになった。
フルパワーかけてギャインギャインの踏んでくってのはまだ出来ないが、上り始めのちょっとした勢い付けやシッティング縛りで同じ姿勢で居るののリセット(休憩、リラックスするためのダンシング)はほぼ痛み無しで出来る。
ちょいとダンシング混ぜて上ることが出来るおかげでアウター縛りで茶臼山は上れる(2本とも)
------------------
もうちょい肩甲骨の痛みが減ればホントは今年のヒルクライムレースシーズンは終了しちゃったんで、ヒルクライム練習じゃなくてシクロクロスの練習に移りたいんだが…
どうにも悪路走行だとハンドルを抑えるのに背中+肩甲骨を使うんで高速走行は難しいが、低速のスラローム走行ならイケるかも?
------------------
ブエルタ・ア・エスパーニャも落車続きでリタイヤ続出になってるな…
アスタナとモビスターで総合を争う感じか。ユンボ・ヴィズマはやはり初日の落車の影響でクライスヴァイクが消えたのが痛い。EFのウランも落車で鎖骨と肩甲骨を骨折してリタイヤって…今ならその骨折の痛みの半分(肩甲骨の骨折)は分かる…
昨日の24時間TVのドラマ見て、ツール・ド・ラブニールの誰がどう動くか全く分からないカオスなレース見て、ブエルタ・ア・エスパーニャがチームTTで開幕と。
・・・じゃダメなんだわ。本当ならここで『乗鞍お疲れーしたー』って言って、とりあえず20.5㎞のレースのログでもあげてなきゃいけないんだわ。
エントリーしといてスタートラインに立てないん(DNS)じゃお話になんない。返すのに一年かかる借りを作っちゃったな。
さて、さて、さて、乗鞍のはこのまま来シーズンに持ってくとして(上るだけなら今年のうちに借りを返しに行くかも?)、ドラマも面白かったっすよ?(アンビリバボーを以前見てるのでストーリーは分かってましたが…美人ジャーマネは居なかったはずだが…)
これを見て自転車始めるも良し、他の何か(例えば別のスポーツ競技)を始めるも良しです。(ホントに一番トップを目指すってんでなければ)物事を始めるのに遅いって事はないので。
(例えばツール・ド・フランスを目指す等の)世界戦クラスの自転車競技でいえば年齢的にどうしても結果が出せずに無理って事も有りますが…(世界トップクラスの選手でも40歳位で現役引退になる)それでもホビーレースなら例えばヒルクライムレースだと年齢別にクラス分けされているので、小、中学生位から上は70、80歳~でも出てる人が居ますので。クラス優勝は目指せます。
自分が出てるシクロクロスって自転車競技カテゴリーだと40歳~60代の人で分けた『マスターズクラス』ってのがあり、マスターズクラスの全日本選手権も開催されてます。(トラック競技(超ざっくりで言うと競輪みたいなの)など別カテゴリーでも在ります)
自分もスポーツ自転車(最初はクロスバイク)に乗り始めたのは確か38か39歳の時(5、6年前?)、それからレース(ヒルクライム)に出始めてるんで30歳代でヒルクライムレースを始めるとかはわりと普通かも。(実際の所、ヒルクライムレースで一番クラス人数が多いのは30歳代じゃないかな)
しかも自分の場合は自転車に乗り始めるまでバイク(オートバイの方ね)には乗ってはいたけど、特にスポーツはやってなく、(仕事は肉体労働ですが)10年以上タバコを一日50本以上は確実に吸ってました。ちなみに体重もレースやってる今ですら68㎏位有りますが。。。(身長は174㎝)全然痩せてない体型。(自転車に乗る前にはタバコは止めてましたが。止めて10年位になるか?)そんな感じからの自転車競技スタートでしたが、なんとか各ヒルクライムレースでチャンピオンクラスにギリギリ引っかかるか?(クラス順位で10~25%位)ってトコにはなれてます。
逆に(年齢的に)早く自転車競技を始めてれば良いか?というとそれも必ずしも良いとは言えないかもしれません。
確かに早く(競技を)初めていれば『レース(現場)に慣れる』という経験値は多く溜まりますが、肉体的に『自転車だけ』をやっているのは良くないかもしれませんし、乗りすぎたり、キツ過ぎたりするとヒザ、腰等の故障、(肉体の部分的な短寿命)のもとになるかもしれません。
高校野球で投手の投球数が制限されたりして無理をしないような処置を取ったりしていますが、自転車でも無理に重いギヤをギャインギャインに踏まないようにギヤ比で制限されてたりします。
今回の宮澤さんは幼少時から(競技は中学生から)ずっと自転車ですが、前にも書きましたが(ってか丁度今回のチャリダーで新城選手のやってるし)新城 幸也選手は最初は本格的に自転車競技はやってなく、中学2年から高校3年までハンドボールをやっていて、その後自転車競技を始めて日本を代表するトッププロまで登り、本場ヨーロッパでツール・ド・フランス等のグラン・ツールに出場する選手になっています。他にも他競技からの選手っていうと真っ先に思いつくのは現ユンボ・ヴィスマのプリモシュ・ログリッチ選手。スキーのジャンプ競技(~2012年まで)出身です。
『そんな短時間でトップレベルになれるのは本人の才能』の一言で終わりじゃないとは思います。体の使い方、バランス感覚等別の競技でも共通する所を鍛え続けた努力の結果かと。新城選手の場合だとトライアスロンを少しやってたとの事なので、『水泳』ってのが基礎になってるのかも。
ブエルタの方は優勝候補の筆頭のユンボ・ヴィスマがTTでいきなり集団落車でタイムロス+怪我。落車は見たくなかった…
そしてトップタイムはアスタナ。
今年のブエルタのコース設定は最初の週からキツイから怪我の痛みが有ると厳しいぞ…
・・・で、乗鞍に出る予定だったので、昨日、今日は仕事を休みでお願いしていた。
結局、乗鞍には出れなかったが休日のままだったので自転車で走る時間はあった。
骨折の痛みが減ってきたところで、近場で済む茶臼山での上り練習をすることに。
時間的には余裕が有るが、肉体的に長時間乗ってるのは無理なので『1時間位の走行練習で…』って事で2本上る予定で走行開始。
肩甲骨が痛いので例によってシッティング縛りで上る。いつもならダンシング有りのフロントアウター縛りで上れるが、今日は何ヶ所かあるキツイコーナーはインナーに落とすけど、それ以外は出来るだけアウターで。
日曜の昼間に練習ってほとんどやったこと無い(基本的に日曜日は仕事)が結構、茶臼山を上ってる人居るんだな。
信里小まで上って1本目終了でUターンして下り。スタート地点に戻るチョイ前で上り始めてる人にすれ違う。『これでスタート地点からあの人を追い始めれば2分位タイム差有ってスタートになるな…』
2本目の走行で、しかもシッティング縛り走行で2分差を詰められるかは分からんけど『今日ここ(乗鞍に出ずに長野)に居る人には負けられんのよ!』の気持ちでスタート地点の火の見やぐらまで下って再び上り始め。
頂上の信里小まで上ったが…はたして結果は…
乗鞍のリザルト見たけど、チャンピオンクラスは中村選手が連覇。もしかしたらMt.富士ヒルに出たジョン・エブセンが乗鞍にも来たりして…なんて思ってたが、来なかったのね。
トップ常連選手の人達が車体の方をボトル、ボトルケージ、バーテープ、レバーブラケット(フード、ゴムのカバーの)まで外して軽量化してるのに中村選手はそこまでせずに上位常連してるので『まだ限界までいってないのか』と一昨年から注目してた。
…アレ?一般Eクラスの優勝者って…?(今は)一般人か。
・・・じゃダメなんだわ。本当ならここで『乗鞍お疲れーしたー』って言って、とりあえず20.5㎞のレースのログでもあげてなきゃいけないんだわ。
エントリーしといてスタートラインに立てないん(DNS)じゃお話になんない。返すのに一年かかる借りを作っちゃったな。
------------------
さて、さて、さて、乗鞍のはこのまま来シーズンに持ってくとして(上るだけなら今年のうちに借りを返しに行くかも?)、ドラマも面白かったっすよ?(アンビリバボーを以前見てるのでストーリーは分かってましたが…
これを見て自転車始めるも良し、他の何か(例えば別のスポーツ競技)を始めるも良しです。(ホントに一番トップを目指すってんでなければ)物事を始めるのに遅いって事はないので。
(例えばツール・ド・フランスを目指す等の)世界戦クラスの自転車競技でいえば年齢的にどうしても結果が出せずに無理って事も有りますが…(世界トップクラスの選手でも40歳位で現役引退になる)それでもホビーレースなら例えばヒルクライムレースだと年齢別にクラス分けされているので、小、中学生位から上は70、80歳~でも出てる人が居ますので。クラス優勝は目指せます。
自分が出てるシクロクロスって自転車競技カテゴリーだと40歳~60代の人で分けた『マスターズクラス』ってのがあり、マスターズクラスの全日本選手権も開催されてます。(トラック競技(超ざっくりで言うと競輪みたいなの)など別カテゴリーでも在ります)
自分もスポーツ自転車(最初はクロスバイク)に乗り始めたのは確か38か39歳の時(5、6年前?)、それからレース(ヒルクライム)に出始めてるんで30歳代でヒルクライムレースを始めるとかはわりと普通かも。(実際の所、ヒルクライムレースで一番クラス人数が多いのは30歳代じゃないかな)
しかも自分の場合は自転車に乗り始めるまでバイク(オートバイの方ね)には乗ってはいたけど、特にスポーツはやってなく、(仕事は肉体労働ですが)10年以上タバコを一日50本以上は確実に吸ってました。ちなみに体重もレースやってる今ですら68㎏位有りますが。。。(身長は174㎝)全然痩せてない体型。(自転車に乗る前にはタバコは止めてましたが。止めて10年位になるか?)そんな感じからの自転車競技スタートでしたが、なんとか各ヒルクライムレースでチャンピオンクラスにギリギリ引っかかるか?(クラス順位で10~25%位)ってトコにはなれてます。
逆に(年齢的に)早く自転車競技を始めてれば良いか?というとそれも必ずしも良いとは言えないかもしれません。
確かに早く(競技を)初めていれば『レース(現場)に慣れる』という経験値は多く溜まりますが、肉体的に『自転車だけ』をやっているのは良くないかもしれませんし、乗りすぎたり、キツ過ぎたりするとヒザ、腰等の故障、(肉体の部分的な短寿命)のもとになるかもしれません。
高校野球で投手の投球数が制限されたりして無理をしないような処置を取ったりしていますが、自転車でも無理に重いギヤをギャインギャインに踏まないようにギヤ比で制限されてたりします。
今回の宮澤さんは幼少時から(競技は中学生から)ずっと自転車ですが、前にも書きましたが(ってか丁度今回のチャリダーで新城選手のやってるし)新城 幸也選手は最初は本格的に自転車競技はやってなく、中学2年から高校3年までハンドボールをやっていて、その後自転車競技を始めて日本を代表するトッププロまで登り、本場ヨーロッパでツール・ド・フランス等のグラン・ツールに出場する選手になっています。他にも他競技からの選手っていうと真っ先に思いつくのは現ユンボ・ヴィスマのプリモシュ・ログリッチ選手。スキーのジャンプ競技(~2012年まで)出身です。
『そんな短時間でトップレベルになれるのは本人の才能』の一言で終わりじゃないとは思います。体の使い方、バランス感覚等別の競技でも共通する所を鍛え続けた努力の結果かと。新城選手の場合だとトライアスロンを少しやってたとの事なので、『水泳』ってのが基礎になってるのかも。
------------------
ブエルタの方は優勝候補の筆頭のユンボ・ヴィスマがTTでいきなり集団落車でタイムロス+怪我。落車は見たくなかった…
そしてトップタイムはアスタナ。
今年のブエルタのコース設定は最初の週からキツイから怪我の痛みが有ると厳しいぞ…
------------------
・・・で、乗鞍に出る予定だったので、昨日、今日は仕事を休みでお願いしていた。
結局、乗鞍には出れなかったが休日のままだったので自転車で走る時間はあった。
骨折の痛みが減ってきたところで、近場で済む茶臼山での上り練習をすることに。
時間的には余裕が有るが、肉体的に長時間乗ってるのは無理なので『1時間位の走行練習で…』って事で2本上る予定で走行開始。

肩甲骨が痛いので例によってシッティング縛りで上る。いつもならダンシング有りのフロントアウター縛りで上れるが、今日は何ヶ所かあるキツイコーナーはインナーに落とすけど、それ以外は出来るだけアウターで。
日曜の昼間に練習ってほとんどやったこと無い(基本的に日曜日は仕事)が結構、茶臼山を上ってる人居るんだな。
------------------
信里小まで上って1本目終了でUターンして下り。スタート地点に戻るチョイ前で上り始めてる人にすれ違う。『これでスタート地点からあの人を追い始めれば2分位タイム差有ってスタートになるな…』
2本目の走行で、しかもシッティング縛り走行で2分差を詰められるかは分からんけど『今日ここ(乗鞍に出ずに長野)に居る人には負けられんのよ!』の気持ちでスタート地点の火の見やぐらまで下って再び上り始め。
頂上の信里小まで上ったが…はたして結果は…
------------------
乗鞍のリザルト見たけど、チャンピオンクラスは中村選手が連覇。もしかしたらMt.富士ヒルに出たジョン・エブセンが乗鞍にも来たりして…なんて思ってたが、来なかったのね。
トップ常連選手の人達が車体の方をボトル、ボトルケージ、バーテープ、レバーブラケット(フード、ゴムのカバーの)まで外して軽量化してるのに中村選手はそこまでせずに上位常連してるので『まだ限界までいってないのか』と一昨年から注目してた。
…アレ?一般Eクラスの優勝者って…?(今は)一般人か。
タグ :ヒルクライム