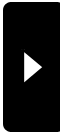さて、さて、さて、今年は出る予定だったヒルクライムレースは全て開催中止となり、しゃーねーんでロードの練習よりもシクロクロスを増やす感じで『シクロクロスに気持ちを切り替えて…』なんて言ってたけど、マウンテンの方も乗るってね~。
------------------
去年から白馬岩岳MTBパークへ行き始め、ガコン、ガコンなギャップや土壁みたいなバンク、ジャンピングポイントがあるロングダウンヒルコースを楽しんでいるワケですが、どうにも車体の方がエントリーモデルな為、車体の方の限界が…(アレ?ピョンピョン ジャンプはしないはずだったが…?)
------------------
純正状態のFフォーク。XCM30 というモデルらしくトラベル80㎜。ロックアウト無し。回してもあまり固さが変わらないプリロード調整は有る。
トラベルが80㎜と少ないために頻繁にフルボトム(底突き)してしまい、路面状況にプラスされ尚更衝撃がガン!、ガン!に。
また、写真では分かりにくいがあまりにもダウンヒル走行で激しくサスペンションが動いている為、摩擦熱でインナーチューブのメッキが茶色く焼けてきてるっていう…
『もうちょい(オートバイだといつも≪ストローク≫って言ってたが)トラベルを増やしたサスを…』と思い、春前にパーツを探していたけど、なんせエントリーモデル車体で旧規格なため、条件が全て揃ってる物が見つからなかった。
●9㎜クイック、OLD100㎜、1-1/8ストレートコラム、ロックアウト付き、トラベル120㎜~でエアサス。って条件。
まず9㎜クイックってのが減ってきてる。コラムもテーパー(下1.5インチ)が主流に。そこにトラベル120㎜~となるとかなり少ない。(80㎜とかならある。ア〇ゾンだと商品説明は120㎜とか書いてあるが、実物は後からトラベル変更が出来ず、80㎜~100㎜なものが多いようなので注意)
9㎜クイックじゃなくてもφ15㎜スルーアクスルのハブでホイール組めば少しは選択肢も増えるが、ずくが無ぇ…(ここは使う所) φ15㎜アクスルで1-1/8ストレートコラムってのもそんなに多くない。(っていうか、『もうフレーム替えた方が早いだろ』なんだけれども…)コレで車体の限界まで逝ったら考える。。。の、前に先立つモノが無いってね…
------------------
で、条件に合うのが見つかったので『在庫有り』で発注したが、後日向こうから連絡があり、『ネットでは在庫有りになってましたが、現物は在庫切れです。1~2ヶ月待ってもらえるなら受注生産でこれから作って送ります』と。マジか。気合入ってんな。。。
『では待ちます。別にせかしませんのでお願いします』に。
------------------
この前の今年初の岩岳の走行には間に合わなかったが、先日届いた。(コロナウイルスの影響で輸送にも遅れが有り2ヵ月~かかったが)

トラベルの追加変更は出来なかった(一度バラした)が120㎜。前のサスに比べてサイズが大きくなっているが重量は0.5㎏ほど軽くなってる。
写真も撮らずにコラムカット等済ませ一気に換装。(予想通りFブレーキホースは長さが足らなくなったのでホースも交換)
コラム長も前より短くしたが、トラベル量増でサスペンションの自由長が長くなったのでこれで走ってみてまだポジションが前上がり気味なら追加でまたコラムカットするかも。
セッティングシートが付属してて、ライダーの体重で目安のエア圧量が記されてる。とりあえず柔らかめ数値にして様子見。
------------------
サスペンションのインナーチューブとオイルシールとの接触面や、オートバイだとリアブレーキのプッシュロッド等、ゴムと金属が接触する所用にいつも使ってるケミカル。
------------------
通勤でも使ってるので(上の画像のタイヤも街乗り用の)ライト、ベルの安全装備にサイコンマウント、カメラマウントが有り、前後ブレーキホース、前後シフトワイヤー、Fサスのリモートロックアウトワイヤー、ドロッパーシートポストのワイヤー(街乗り用でも信号待ちの時とかサドル高をリモートで操作出来ればやっぱ楽。街乗り専用車にドロッパー付けるのは贅沢な気がするが…)
で、なんだかハンドル周りが凄い事に…
------------------
マウンテンバイク乗りの師匠曰く、
『昔は26インチのチューブ入りタイヤで、止まらないカンチブレーキ、サス無しでダウンヒルやってたんだから』
『・・・で、前輪グシャったり、ヘッドパイプとダウンチューブを繋げてる溶接が割れたりでフレーム破損してコケて骨折とか普通にあったんだけどな』
何んすか、その命がけな遊び…おかしいですよ、カテジナさん…
さて、さて、さて、今朝は今にも降ってきそうな曇り空だったけれども、『軽めのスラローム練習を…』と思い、シクロクロス車のTCXでウエットコンディションのダート練へ。
------------------
練習場所は水溜まりが残っていたけど、8の字スラローム練習でグルグル周回を。
流石にここまで重馬場なのも久々だったので、小回りの回転走行だとハンドルを切ってもタイヤが泥の轍にハマってしまい回れない。。。
ハンドルをフルロックに近い状態に切りながらバランス取ってペダルを踏まないと回れない。尚且つつま先がフロントタイヤにあたらないようにしないとコケる。意外と難しい…
スピードは出さなくてもいいですが、舗装路でロードバイクだとしても惰性でペダリングせず小回り、じゃなくて、フルロックに近い状態でペダリングしながら回るって意外と難しいっすよ?
腕に力が入り過ぎると小回りできないし(もしくはハンドル切り過ぎてコケる)、サドル高が極端に合ってなかったり、体幹で上体を支えられず上体がふらつくと間違いなくコケます。
------------------
1時間位やってたら雨が強く降ってきたのでここで終了ー。
こんな天気ならではの練習が出来て良かったが。
------------------
で、別車のマウンテンの方。
先週、白馬岩岳MTBパークで走行したけれども走行後、Rブレーキレバーのストロークが大きくなってきたのが気になった。オイルも減ってたが、『そろそろブレーキパッドが…』と思い、外してみたが…
結構パッド残量が少なくギリギリの所だった。もうチョイでサポートプレート(正式名称不明。パッド押さえの板バネのヤツ)に当たりそう。。。
------------------
パッドはB01Sのレジンで¥1,000もしないで購入できるので交換。
シマノの純正ブレーキパッドもいつの間にか品番(価格も)が変わっていたりするので、パッドを買い替える際には今付いているパッドの品番と、ブレーキキャリパーの型番も一応、控えときましょう。
パッドの裏の品番と材質 『B01S RESIN』
ブレーキキャリパーの品番はモデルによって場所が違うかもしれないけど、ウチの油圧のだとシャーペンで指してるフレームとボルトで固定する台座の部分
拡大(キャップボルトの緩み止めの黒いプラのが有って見づらいけど)・・・『BR-M315』が型番。
気付くのが遅れるとパッドのベースプレートの金属の板でブレーキローターを削るまでいっちゃいますからね(多分その状態だともの凄い悲鳴のような金属音がしてきてブレーキ効かなくなってると思うけど)
いよいよ梅雨入りしてしまいましたね…しかし、強く降ってきたと思ったらすぐに止んでしまい蒸し暑くなるだけっていう…(マスクしてるから尚更暑い…)
しかもこの降り方だと夜になると(カゲロウみたいな)虫が大発生してしまう…
そういえば今年はサイクリングロードを走ってても茶色い毛虫が少ないのでマイマイガの大発生周期は来年辺りか?7年だか5年周期でしたっけ…アレも怖い…
------------------
さて、さて、さて、前回からの続きでシクロクロス用ディスクブレーキの前輪のホイール組みを。
------------------
リムは『DTスイスの RR411db アシンメトリックリムで組む』と決めたけれども、TNIのAL22Wも(やっぱり)候補だった。
しかしRR411リムで組んだ後輪がペアになるため
後輪を組んだ時の過去記事 ↓
『ペアで合わせるか』って事と、重量がAL22WよりRR411の方が(ニップルワッシャー込みでも)軽いようなので、今回はRR411で、ということに。
金額的にはRR411はAL22Wの倍近い金額だけど、今年はC19の影響でレースが無いのでエントリー費やその他費用が浮いてたり、3月からあまり外で買い物してなかったりで出費が少なかったので残ってるうちにコッチに回した。
------------------
で、『どう組むか』だけれども前のはオフセット無しリムで逆イタリアン6本組で結線有りだった。このホイールでもシクロクロスレースでは野辺山のフライオーバーや白樺湖の前輪ウイリーしちゃうような坂や、南信州の土手3連続の上りなんかでも体重70㎏位の人間がえっほえっほ踏んでもホイールがヨレてブレーキローターにシャリシャリ擦れて音がするなんてことはなく丈夫だった。
後輪の方も今回は上手く足に合ったようで?シクロクロスのレースだと白樺湖や野辺山ではコーナーの立ち上がり加速で前の人を抜くってのが上手く走れてる時の自分のパターンだった。…しかしその反面長いストレートの多いコース(南信州や清里 丘の公園)は苦手。。。
今回組み直す目的が『ちょっと悪あがきで軽くしたい』なので、オフセットリムでスポーク張れるって事もあるので、4本組にして(6本組よりスポーク長が短くてすむのでわずかにだけど軽量になる)結線有りで組む事に。
(昨年末に組んだロードディスク用の前輪(TNIのAL22(ナローリム)とREVO ROAD ディスクハブ 24H)でも弱いとは感じない位で使えてるので、
過去記事に飛びます。 ↓
自分位体重有っても今の乗り方で28Hなら6本組から4本組にクロス数減らしても大丈夫なんじゃないかな?ってのもある)
------------------
開梱したらニップルホールからのバリ取りを
今回のバリは少な目で小さ目。(ジョイント溶接されてる両隣の穴から大き目なバリが取れる事が多い)
重量計測。414g
------------------
アシンメトリック(オフセット有り)のリムって事ですが、(ディスクブレーキ車の)前輪だとリムのオフセットはこの向きになります。(ハブのフランジ高がどうこうってのは考えない事にします…)ディスクローターが付く左側がリムサイド面が緩やかになり、ディスクが無い右側が急な面になります。リアとは逆向きになります。(リアはスプロケットが有る側(右側)が緩やかな面になる)
------------------
4本組の逆イタリアンの基本形です。真下のドライバー差してる所がバルブ穴。右(ローター無い側)から見てます
スポークヘッドが外を向いているスポークがペアとなる右側の4つ目の内側向いてるスポークと交差する時に外側にくる。
左側(ディスク側)は外を向いているスポークの左側の4つ目の内側に向いてるスポークとペアになる。(どうにも文章だけで説明するのはムズカシイ。。。)
次回からは頭が外を向いているスポークの事を『外ーク』、内側を向いているスポークを『内ーク』ってしようかと…

で、改めて左落としで
全部の穴に通します。自分は『バルブが真下に有る時にハブのロゴが真上に来る位置』で決めてます。
『写真撮る時にはバルブって真下にするでしょ?その時でもハブのロゴもちゃんと見えるから』
ってそれだけの理由です。
以前組んだ6本組のがコチラ↓
------------------
『リムサイドに貼ってあるシールの厚みが邪魔だな』と気になる位はフレ取りもやる。
とりあえず組んでの重量は765g。前のから75g軽量になったってことで。
(追記 軽くなったのはリムの重量分だけで、スポークの組み数を6本組から4本組に減らしてもDT専用のニップルとニップルワッシャーを使ったため重さは相殺されてる)
------------------
リムにチューブレステープ(STAN'S 21㎜幅)を巻く。巻き数はバルブ部は重ねる1周チョイ巻きで。
穴あけ用のポンチ(5㎜)の先をライターで炙って加熱させ
バルブ穴部に当ててクリクリっと回すのを2、3回繰り返すと
開通。
チューブレスタイヤを履く前に一度適当なチューブ入りのタイヤを履かせてエアを入れ、チューブレステープをリムに圧着させる。
これでチョイと放置になるかな。(本番用の)チューブレスタイヤ履かせるのはまだ先かと…
梅雨入りしてウエットコンディションが増えるので、これからはダート練習多めでいきまー
------------------
KCNCの6ボルト式ローターをセンターロック式のハブやホイールに取り付ける「センターロックアダプター」。
『コレ出てくれないかなぁー』と思ってた。
センターロック式だとハブは軽くなるがディスクローターは重くなる。6穴式だと逆になるけど、トルクスボルトをナメやすい。
センターロック式のローターを軽くさせようとすると材料費、コストがハネ上がり、ローター1枚¥1万、2万とか普通にしちゃうと思ってたから。これなら低コストで軽量化できる。
(しかしアダプターはともかく、ああいう肉抜きしまくりのローターって大丈夫なんだろうか…)
さて、さて、さて、シーズンInはまだまだ先ですが、シクロクロスの本番用Fホイールを組み直そうと思ってたのをやってしまうことにしました。
------------------
今まで使っていた本番用のホイール。
詳細(正体)不明のオフセット無しリム、TNI エボ2ディスクハブ 28H φ15㎜アクスル、DTのスポークとニップルで逆イタ6本組で組んで結線した物。
------------------
まず6穴のブレーキローターを取り外す。以前にも書きましたが、ここのトルクスボルトはナメやすいので、精度の良いT25のソケットを垂直にセットして、しっかり押しながら緩めるで。押しながらじゃないとヌルっと工具が浮いてしまってナメます。携帯ツールのトルクスレンチとかだと力が入れづらく、ナメる率が高くなると思うのでやらない方が…
1本だけ緩めてしまうのではなく、6本少しづつ対角的に緩めましょう。
------------------
ブレーキローター、チューブレステープ、チューブレスバルブ無し、φ15㎜アクスルアダプター有りでの完組重量は840g。
------------------
φ15㎜アクスルアダプター有りのハブ重量 154g。
リム重量489g。
------------------
このリムをDT スイスのRR411 db(オフセット有り、28H)に換えて組む事します。
次回に続く
30度超えてくると暑いよな…
さて、さて、さて、先日の岩岳MTB パークでのDH走行中にサイコン(LEZYNE SUPER GPS)が吹っ飛んで行方不明になってしまった。
まともな状態なLEZYNEは本体裏側が十字形状になっていて受け側になるサイコンマウントに45度回した状態で押し込んで車体にセットするが、自分のサイコンは落としたりして十字の「ツメ」が欠けていた。
そのため普通には固定出来ず、ゴムのバンド(っていうか古チューブを輪切りにしたもの)2本で止めていたが、そのバンドが走行中の振動で切れ、サイコンが落下した模様…
DH走行中は振動も凄まじく、前を見てないとほんとヤバいので「いつ落ちたか」なんて全く分からん…1本ごとにラップタイムを録ってたけど、1本下ってきてラップボタン押そうと思ったら「スカッ」と押せず、「アレ?無い?…やってもうたぁぁぁぁー!!」って感じ…
------------------
サイコン無しってわけにもいかんので新たに購入することに。
で、『どの機種にするか?』ってところだけど、
●ハイエンドモデルは別に必要無し。
●カラー液晶もタッチパネルも不要かな。
●画面をガン見して走行はしないけど、1ページで多めに項目が表示できるヤツがいいな。
●ナビは頻繁には使わないけど、有った方がやっぱいいか。
●レースで使うから前周(もしくは区間)のラップタイムが見れるものを。
ってのを希望にして…
------------------
コスパ良さそうなのはヒルクライム車体の方で使ってるBryton Rider530の後継モデルのRider420、もしくはナビ無しでRider320か。ナビ付(センサー無しの本体のみ)でも定価¥15,000は安め。ナビ無しの320だと¥12,000ほど。(+¥3,000でナビ付くなら420にするわな。。。)
っと、『Rider420にしようかな』とネットを見ていたが、とあるものがセールにかかってた…
・
・
・
で、ポチってしまいました。
再度、LEZYNE SUPER GPSを購入しました。
¥15,000以下だったけど、日本語対応の正規品、2年保証付き(ちゃんと保証書が付属されてて、ストアスタンプと購入日も捺印、記入されている)
------------------
SUPER GPSだと車体が5台まで表示画面等の設定が個別で出来るってのも長所。(車体5台も持ってないけど)
画面は小さめだけれども、慣れちゃってるし。100点満点な製品じゃないけどね。(実際、吹っ飛んで紛失って最悪な事が起きてるわけだが。。。)
車体側のマウントもチョチョッと手を加えて今までの物を基本使い回しで。サイコン本体の初期設定と自転車各車のセンサー、ハートレート、スマホとのペアリングもサクッと済ませて液晶にも保護シール貼って使える状態に。
------------------
とりあえず脱落防止の命綱(ストラップ)は付けた。(※補償対象外になる恐れがある作業だと思うので、真似する際は各自の判断で)
------------------
これで今週末辺りから梅雨入りしそうなんで、ヒルクライム練が減り、ウエットダート走行練が増えるんで、お前さんには早速、泥まみれになってもらうかもしれん。
昨日は夕方からゴロゴロ盛大に雷が鳴っていて雨降り。
今朝は山の方は雨上がりでセミウエット路面なんだろうと思い、ダート練をすることに。
------------------
走行後
1回ダート走れば、まぁ泥だらけになるわな…
1回ダート走れば、まぁ泥だらけになるわな…
洗車後
------------------
チェーンは前回のメンテでCN‐HG601(105グレード)からHG701(アルテグラグレード)に換えたけど、
過去記事を参照で ↓
------------------
インナー、アウタープレート共SIL-TEC(シルテック)加工がされていると(スプロケも)やっぱり洗車が楽。ついでにCN-HG701だと中空ピンではないのでピン内部に泥が詰まらないので更に楽。
昨日、今日と連日北信で暗いニュースが立て続けにあり、なんだかね…
------------------
さて、さて、さて、今朝は走る時間があったので雨上がりのダート練を。
練習が終わって帰り道を走っていたが、かなりな泥まみれになったので、チェーンがギチギチ鳴ってるような状態。。。
『いつもの年に比べて暖冬で雪も少なく、走る回数が多かったし、やってなかったからシクロ車体も一旦バラしてメンテするか…』ということに。
------------------
ロードの方は例年のこの時期ならヒルクライムレース本番前にクランク外してグリスアップしたり、ブレーキパッドとホイールを本番用にして慣らしみたいなのをやってるんだけど、今年はC19の為レースが無いのでホイールの慣らしはやらないが、クランク外してクリーニング、ブレーキ本体もクリーニングってのを先日(写真撮ってないので記事にしてない)やった。
------------------
シクロクロスの方は『2020-2021シーズン向けに部品換えて~』ってのはまだやらないけど、部品交換無しのクリーニングで済ますことにした。
------------------
作業前
中間
ヘッド、BB、ペダル等は取り外してバラして洗浄後、グリス入れたりしたけど、手がグリスまみれになってるので途中の写真は無し…
チェーンは外して洗浄液に漬けとく(走行後、毎回水洗いして注油してはいるが、洗浄液が汚れる汚れる…)
シートポストを外すと…めっちゃ砂だらけ!
シートポストがズレるのが嫌なんで外したことが無かったが、コレは酷い。。。フレーム内部(シートチューブ)も
フレーム内部を水洗いすることに。試験管用ブラシでシートチューブ内部の汚れを落とす。
どうにか汚れは取れたな…
洗い終わったら、エアガンでフレーム内部を吹きまくり、向きも変えたりしてフレーム各部の水抜き穴(というか溶接時の熱抜き穴)から内部の水抜き。
------------------
フレームを拭きながら見たが、Rブレーキの台座のところ(写真映り悪い。。。)

やっぱりフレームが削れてる。

BB後ろ、チェーンステイ部もスレキズが有る。やっぱり泥走行では擦れる

※シクロクロス車に限らず定期的にディレイラーハンガーを固定してるボルトは緩んでないか確認しましょう(車種により固定方法は様々です)

------------------
シートポストも綺麗になった。(シートポストはカットせずに使ってる)
(組付け時に防水、防砂加工を施したんで、もうシートチューブには水、砂は入らないと思う。)
------------------
洗浄液に漬けといたチェーンを出してみたが、チェーンの伸びを見るチェーンチェッカー(シマノのTL-CN42)に当てると、どこで当てても抵抗なく入ってしまいNG値に…
寿命か…って事で昨シーズンの本番用のチェーン(CN-HG701)を練習用に回す。
さすがにこっちはあまり使ってないのでチェッカーは入らない。
------------------
各部組み直し終了ー。
次は4ヵ月位したら換えるパーツは換えるでよ。もうチョイがんばって。
さて、さて、さて、自転車に乗ることが出来るようになったところで、『今日、乗れれば乗ろうか』とロードのタイヤを触ったらグニャっとペコリーヌ。。。空気抜けてら…
『…これは明らかパンクしてんな…いつやったんだべ?』
------------------
ってことで、パンク修理(今回はチューブ交換)をまたネタに書きます。。。
------------------
まずバルブの位置をタイヤにマーキング
マーキングするにはいわゆる『白ペン』的なのを使ってます。
で、タイヤを外す前に何か刺さってないか目視で探す。今回は細かなガラスが2ヵ所タイヤに刺さってたのでそこにもマーキング
タイヤをタイヤレバーで外すけど、下の写真の状態からタイヤレバーを横に滑らせるようにして素早く外すことも出来るけど、ロードで高圧にエアを入れてる場合はチューブがタイヤに張り付いてレバーが引っ掛かる時が有るのでその時はチューブにキズが付く可能性が有るので滑らせずに少しづつ外す方が安全。
------------------
チューブを取り出したら回転方向の矢印を書いておく。(自分は組付け時に書いてるけど)

水を入れたタライやバケツに少し空気を入れて膨らませたチューブを入れ、穴の個所を確認。
盛大に穴が開いてーら…(シューシュー音がしてたが…)
穴が1ヵ所とは限らないので必ずタイヤ1周水に入れて確認しましょう
今回はとりあえず穴は外側に1ヵ所だった。穴の所にもマーキング。いつも自分は穴の位置を中心にして十字みたいに書いてる。※リム打ちパンクの場合は開いている穴のすぐ横にもう一つ穴が開いていたり、開きかけていてチューブにキズが付いている場合があるので見逃さずに!(リム打ちだと内側(リムの方)か横に穴が開いてる)
------------------
マーキングしたチューブを再度タイヤに合わせる
すると、さっきタイヤにガラスが刺さってたところと位置が合う。

タイヤに穴が有る所とチューブの穴の場所が一致する
異物を取り除いてタイヤの内側も1周異常が無いか確認。ガラスの破片など残っている場合があるので指先をケガしないように!
------------------
今回はパンク修理せずにチューブ交換することに。
ロードバイクでパンクって2年ぶり位かも。少なくてもこのリアホイールを組んだのが(過去記事を見ると)2018年の10月アタマ頃なので、それ以後タイヤは交換したけど、チューブは換えた記憶が無い。
逆にチューブレスにする前のシクロクロス車の方は何回パンクしたか多すぎて覚えていない…
------------------
チューブ交換ついでにリムフラップを交換することに。前のホイールからなので正直、何年使っているか分からないリムフラップ。エア圧でニップルホールの所が凹んでる。
あまりに凹みが深くなりすぎたり、ニップルホール部にバリがあったりするとこの部分が原因でパンクすることが有ります。
新品に交換。
------------------
推奨することではないけど、タイヤに開いた穴は瞬間接着剤で補修。ちょこっと塗って乾燥させる。中の糸が見えてるくらい大きな亀裂の時はやると危険。
一応、タイヤを折り曲げても割れてはこない
------------------
タイヤとチューブをリムにはめていく。チューブにはほんの少しエアを入れた状態で嵌めるとチューブがねじれたり折れ曲がったりしにくくなる。が、エアを入れ過ぎるとタイヤが嵌めにくくなるので…
新品のチューブにはさっきも書いたけど、組込時に回転方向の矢印を書いておく。(コレを組込時からやっておくと出先でチューブ交換する時にどちら向きでチューブが入っていたか間違えなくて済むので。)
嵌めていって残り僅かなところで嵌め辛くなるけど、タイヤレバーは可能な限り使わずに、親指でめくり上げるように嵌める。。。
------------------
タイヤ、チューブをセットしたらバルブナットはまだ取り付けず、一度バルブを中に押し込む。コレをやることでバルブ口でチューブが噛みこむのをまず防止できます。最初にバルブナットを取り付けるとバルブ付近でのチューブ噛み込みの原因になります。
タイヤをつまんでリムとの隙間にチューブがはみ出てないか左右2周確認。
写真撮りながら片手でやってるんで分かりにくいけど…
悪い例としてもの凄くワザとチューブはみ出さしてますが、隙間からチューブが見えるこの状態でポンプでエアを入れるといわゆる『噛みこみバースト』が発生します。

チューブの噛み込みが無かったら、まだバルブナットを取り付けずにポンプで1アクション軽くエアを入れます。そしたらもう一度、噛み込んでないか(特にバルブ口付近)確認すれば確実です。※中古チューブだと若干チューブが伸びて長くなってたりするので、エアを入れるとはみ出てくる時が有るために再度見ます
噛み込みが無ければ目標エア圧の半分位まで入れます。そしたらリムラインが左右全周出ているか確認します。出ていない個所が有るとホイールを回転させるとうねるはずです。また、タイヤが一部分だけ膨らんでたりする時はチューブがタイヤ内部で折れ曲がっているか、噛み込んでいます。
リムラインが出てたら目標エア圧まで補充します。そしてここでバルブナットをバルブキャップと共に締めます。(バルブナットは一番最後で良いんです。)
------------------
7気圧入れた状態の瞬間接着剤で補修したところ。穴は塞がってます。

------------------
ホイール外したついでにスプロケも軽く拭き取り。
前
後 あんまり綺麗になってないな
------------------
今回はチューブ交換したけれど、パンク修理のも以前書いてるのでそっちも参考にしてみて下さい。
パッチ貼るパンク修理のポイントはなんせ『しっかり削る事と直ぐにパッチを貼らない事』です
下の画像か青文字クリックで過去記事に飛びます。
------------------
追記
『エアが抜けてる』って事でチューブを取り出して水に入れてもパンク穴が無い、だけど少しずつやっぱり抜ける。という時にはフレンチ、米式バルブの場合、『バルブコアからのエア漏れ』の可能性が有ります。
バルブコアからのエア漏れの場合はただチューブを少し膨らませただけの低圧状態ではエア漏れせず、高圧の時に少しずつ漏れる事が有ります。
この場合のエア漏れの確認方法はリムにタイヤ、チューブが嵌っている状態で、いつも入れてる規定エア圧の時にフレンチバルブならバルブコアの先端のネジ部を締めた状態で適当なキャップ(フタ)みたいなのに水を入れ、バルブ先端を水に漬けると確認できます。漏れている場合は交換可能なバルブコアの時ならネジ部からわずかずつエアが漏れてきます。
自分が使ってるのはコンタクト洗浄液に付いてくる洗浄ケースで確認してる。ペットボトルのフタでも確認出来ないことも無い。
バルブコアの増し締めでエア漏れが止まる事もあるけど、シールがヘタってきてエア漏れの時はバルブコアの交換を。(バルブコアが交換できないチューブの場合はチューブ交換)
------------------
『桜 写日記 5/22 No. 11 最終回』
さすがにもう桜は終わり
さすがにもう桜は終わり
上ってる時は暑いが、下ってる時の風は涼しいね~
さて、さて、さて、『シクロクロスを始めるなら』の5回目…えらい長くなってしまった…
車体の方でまとめにいきます。
メーカー名、モデル名も書きますが、すべてを把握してませんし、現物を見ているわけでもありません、乗ってもいません。そんなですが。
------------------
フレームサイズは別のスポーツ車を乗っている方ならある程度自分の適性フレームサイズは把握しているかと思います。フレームに関しては、『ある程度乗って走らないと分らない(感じない)』というのが正直なところだと思いますので深く考えなくてもいいかも。と酷いことを言っときます。
だって、『肉体的(手足や胴体長)には(サイズが)合うフレームでも、そのフレームが自分の乗り方にも合うかは分からない』でしょ? 全く同じジオメトリのフレームが複数のメーカーからもし出てたとしても、フレームの部分的な肉厚なり材質(アルミなら番数)、接合方式なりで必ず違いはあるはずでしょう?(OEMでロゴ、ペイント、あとはほとんど同じ…みたいなのは置いといて。
ある程度は乗る側が車体に合わせないと…とは思います。その中で『自分にはこういう乗り方も出来るのか』と発見することもあるかもしれませんね。
------------------
で、結局は『自分がやってきたことを勧める』というオチになり、エントリーな価格ではなくなってますが、『レースで使い、それで走りきれてレースでちゃんとリザルトを出せる車体構成』で考えています。
------------------
一応、なんちゃってだけどクラス優勝もありましたよ?
信州シクロクロスミーティング 2019-2020シリーズ 開幕戦 白樺湖ステージにて
戦利品も頂きました。
(この戦利品(お酒)はいつもアドバイスをしてくれる先輩自転車乗りにお供えしました)
信州シクロクロスミーティング 2019-2020シリーズ 開幕戦 白樺湖ステージにて
戦利品も頂きました。
(この戦利品(お酒)はいつもアドバイスをしてくれる先輩自転車乗りにお供えしました)
ホントのエントリーモデルで金額も安い車体も有りますが『トラブルで走りきれずリタイヤ』、『どういう風に走るか(レースをするか)を考える余裕もない』そういう車体でレースに出ても面白くないでしょう? 実際、自分のシクロクロス初出場レースは泥詰まりでホイールが回らずリタイヤですしね…なので泥トラウマは有るかもしれません…
------------------
●フレーム素材はアルミ
形状で考えると『ワイヤーは出来るだけフレーム内蔵かフルアウター化が出来、BB裏にブリッジが無く、前後φ12㎜のEスルーアクスル固定な車体』が良いかと。
だけど、走るコースが激しい泥コースでなければブリッジが有っても泥詰まりの問題は無いかもしれません。アルミフレームのエントリーモデルは各メーカーから出ていますが、形状に条件を付けるとかなり絞られてしまい、金額も高めになってしまいますが…それにシクロクロスは完成車販売が多く、フレームセット販売が少ない
●ブレーキは油圧ディスク
シクロクロスではドロップハンドルのブラケット持ち(上持ち)での走行がほとんどなのでブラケット持ちで連続フルブレーキングしてると機械式では正直、握力が無くなってきます…(ダート走行はしてませんが、TRPのHY/RDハイブリッドキャリパーを通勤仕様車で現在使っています。機械式に比べてタッチは固め、引きも軽くストロークも少ないので完全油圧には劣るけれど使えないことも無いと思う。インナーワイヤーを日泉ケーブルに換えれば尚良し)
ディスクローターはブレーキ熱によるフェード現象が発生して効かなくなるなんて事はシクロクロスレースではまず起きないので、サードパーティー製の物で冷却フィンとか無しの物でも指先1つで
正常な状態でもパッドがキュルキュル音鳴りすることもありますが、あんまり気にしない事…水場突破した後とかは大抵鳴ってますし。。。
●シフトは11速(シマノなら105以上のグレードを)
この部分(油圧ブレーキで11速)は金額がかかる所だけれど、やった方が良いと思う。
作動は機械式でも電動でも好みで。(電動だと金額がハネ上がりますが…)
●クランク、スプロケの組み合わせ(ギア比)はお好みで
フロントシングルならサードパーティー製のエントリーモデルクランクでもナローワイドチェーンリングと組み合わせれば変速トラブルは起きにくく、金額も抑えられるが(クランクの)重量的には不利。また、泥詰まり、メンテナンス性の点もフロントシングルはメリットになるけど、ワイドギアすぎると脚が疲れやすいかも… フロントシングルにするならナローワイドチェーンリングにしたとしてもチェーンデバイスは付けた方がいい。
●ハンドル、ステムはアルミで十分。
最初はおそらく散々コケますので『軽いから』でハンドルバーをカーボンにしちゃうとあっさり折れますよ?
●ホイールはアルミリムで問題無し
エントリーモデルで多く採用されているカップアンドコーン式の純正のホイールで、玉押しの所に水、砂が入ったりして乗りっぱなしノーメンテだと1年も持たずにハブ軸がガタガタになりますからね(ラジアルボールベアリングならノーメンテでOKって事でもないです)
●タイヤはチューブレスを
メーカー完成車ではチューブレスタイヤを採用しているのがほとんどになりましたが、チューブレスタイヤの取り扱い方、パンク修理、(もしもの時の)チューブ交換の知識と技術も
●ペダル、シューズはマウンテン用を
ホントに最初ならビンディングペダルじゃなくてフラットペダルで慣れるのも良いかも。(フラットペダルなら滑りにくいものを)また、泥でヌルヌルな斜面を自転車を担いで上るってのがあるのでシューズも滑りにくい物を。
------------------
こんな感じで挙げてくと・・・
完成車なら
●TREK Crockett 5 Disc ¥229,000(税抜)
●GIANT TCX SLR 2 ¥190,000(税抜)
(TCXは機械式ブレーキレバーだけれど、ステム部で油圧ブレーキに変換(CONDUCTシステム)してる。シートポストがD型断面)
※現状(2020年4月)で両車ともコンポはSRAM、フレームセット販売は無し、カラーリングは1パターンのみ
フレームセットでなら
●ブリヂストン アンカーCX6 ¥120,000(税抜)
105ベースの完成車 ¥235,000(税抜)もあるけどブレーキは機械式、フロントチェーンリングはダブル。フレームセット重量も出てるが、どの状態の重量なのか不明。(自分が乗ってるTCXより若干(0.4㎏前後)重いかも。)
●KOGA COLMARO Disc ¥169,800(税別)
2018年より新しい情報が無い?『シクロクロス』ではなく『オールロード』として出てる。関心したのは自分が『チェーンステイとタイヤサイドのクリアランスに注意』と書いたけど、COLMARO Discは擦れそうな部分に溶接を盛って厚くしてある点。驚いた。
他にも有る(ワンバイエスの#805Zとか。電動だとケーブル内臓だけど、機械式シフトだと外通し)のだけれど、情報が更新されてなかったりなので…
どうしても『BB裏にブリッジが無いフレーム』ってのがあまり無いので挙げてる車体が少なくなります…その条件を外せば他にもあるんですが…(ケーブルはとりあえずフルアウター化してタイラップ止め。がまず思いつく手段か)
------------------
もし、自分が次の車体に選ぶとしたら、(というか実際検討してる)(重量がちょっと気になる所だけれど)アンカーのフレームセットで手持ちパーツを使いバラ組するのを考えています。新型にモデルチェンジして一番自分の希望構成的なフレームになったし、カスタムカラーリングも出来るしね。
(もしかしたら全くの新規で始める時もバラ組で作ってもTREKとさほど変わらない金額でシマノの105メインで油圧ディスクでフロントシングルなら組めるかも。自分で組立、ホイールも自分で手組って条件だけど…)
------------------
また、定期的にレースに参戦するなら練習用ホイールと本番用ホイールって感じでスペアホイールを用意するか、スペアスプロケとチェーンは有った方がいいので…
そういう装備品だったり練習方法など次回以降にしようかと。
------------------
オマケ
ウサギ 写日記 4/30
今日は日中気温が高かったため、ウサギはエサを入れてるお皿が瀬戸物で冷えるからかお皿の上で休んでた。
お前さんたちにやってるエサのキャベツは今、超高級食材だからな?芯まで残さず食べるんだぞ。
さて、さて、さて、『シクロクロスを始めるなら』で、4回目。
コンポの続きでクランク、スプロケットについてで思う事なんですが…
『シマノでGRXが出たことにより凄い選択肢が増えたな』というところなんですが、ドライブ系で酷い個人的な結論を先に言ってしまうと、
『コレがいい。と言える正解は無い』です。
乗る人の脚力、体力や走るコース(土なのか、砂なのか、固い非舗装路なのか、雪なのか)や天気、気温でも状況が変わるため、『コレがいい』とは正直言いきれません。
その辺はメーカーの完成車のスペックをいくつか見てもらってもわかって頂けるかと。
(GRXが間に合わなかったためか)ロードパーツメインで組まれてる物、シマノのシクロクロスクランクで組まれてる物、GRXで組まれてる物、シマノのフロントシングルが出遅れてたからSRAMで組まれてる物…等様々です。
そもそもメーカーの方で『シクロクロス』と『グラベルロード』で分けてたり、分けてなかったりもしますし。
(※言葉遊びではないのですが、シマノのGRXシリーズの紹介(カタログ)でも『シクロクロス向け』とは書いてないようです。『グラベル・アドベンチャー向け』となっていて使っている写真もシクロクロスレースの写真は無いみたい。別で『シクロクロス』というパーツカテゴリーが有るからかもしれませんが…)
------------------
『グラベルロード』という言葉と、『グラベルレース』というのも在ります。
『グラベルレース』は日本ではまだあまりなじみがないかもしれませんが、1周~3㎞位のクローズドコース(レースコース)を周回走行するシクロクロスとは違い、一般道なども使って一日がかりでダートを走ったりする長距離レースと思ってもらえれば良いかと。欧米では流行ってるそうです。
各メーカーの車体紹介の所で『シクロクロス』と『グラベルレーサー』と分けてる場合もあります。(なんとなくだけど、『太いタイヤ履けるよ』とアピールしてるのは『グラベルレーサー』としてる感アリ)
『なぜ日本ではグラベルレースがまだ流行らないのか?』というと、これは自分の想像ですが、道路使用の許可が取りづらいためと、安全確保が難しいからかと。
『レース』なので事故の危険も在るので一般道の使用許可が取りづらく、山道を上ったりもするわけですが、個人なり、国なりが所有してるところなので、勝手にレースコースにするわけにもいきませんし、『道が荒れたり、崖下に転落したら誰が責任とんの?』ってことです…
それでも野辺山グラベルチャレンジやグラインデューロ、SDA王滝(グラベルバイククラス)等、日本でも大きな『グラベルレースイベント』が始まった感じがします。別にシクロクロスだけじゃなくて『グラベルレーサー』もやってもらって良いんですよ?
…にしてもみんな長野県でのイベントですよ。長野はホント自転車県ですな…
------------------
…脱線。
シマノパーツのバリエーションだとクランクは
●ロード用フロントダブル(53-39T~50-34T等)
●シクロクロス用フロントダブル(46-36T)
●GRX フロントダブル(48-31T)
●GRX フロントシングル(40T、42T)
スプロケはロード用11-25TからGRXではマウンテン用の11-42Tまで…
サードパーティ製の歯数まで含めたら一体、何種類の組み合わせが在るのか…(ロードコンポとGRXでチャンポン出来るかは不明。まずシマノは推奨しないな…)
------------------
まずギア段数ですが、11速(シマノだと105グレード以上)をお勧めします。理由は他の方も自分でも書いていますが、10速で始めて後々パーツを(11速に)グレードアップしようとすると互換性が無いため丸ごと交換になるためです。(とはいえ12速化が来ないとも限りませんけどね。。。)
それにブレーキは油圧をお勧めしますので、GRXなら600~、ロード用レバーならR7000~となります。ここが結構値が張る部分になりますか…
電動の方がメリットは有りますが、機械式シフトがダメということはありません。(2年連続で全日本シクロクロスを獲っている前田 公平選手はSRAMの機械式シフトだったはず)
スプロケはRディレイラーとの兼ね合いになるのでロード用SSケージのディレイラーで小さめスプロケからGSケージで34TまでかGRXで最大42Tまでの超ワイド仕様か。
------------------
自分は最初、フロントダブル50-39T、リア11-34Tの10速で始めました(それしかパーツ持ってなかった)がBB部分での泥詰まり、50Tなんてダートでは重くてとても踏めず常にインナー39T走行。フロントは外側には落ちないが、内側にチェーン落ちまくりだったのでフロントシングル仕様の後、油圧で機械式シフト11速に変更して現在に至るです。
ギア比的な話をすると、ヒルクライムレースに出てる方にならなんとなく分かってもらえるかもしれませんが、自分はヒルクライムレース用の車体ではフロントは50-34Tのコンパクトクランク、リアは11-30Tのカセットで乗っています。それでツール・ド・美ヶ原だとCP1の美鈴湖まで、乗鞍だと三本滝ゲートまでアウターのままで~20分のタイムです。
それでシクロクロスではフロント38T、リアは11-34Tの組み合わせでCCMのコースは走ってます。(野辺山含む。コースによってギア比変更はしてません)
『自分にはシクロクロス用標準のフロントシングル40Tは重すぎる』と感じ、38Tにしています。ナローワイドチェーンリングに自作でチェーンデバイスを付けています。この仕様でチェーン落ちは1シーズン中で練習も込みで1回有るか無いか位まで減っています。(少なくともレース中にチェーン落ちで止まった事は無いです。…ホイールは落ちたけどねー)
リアはRD-R8000-GS。自分が車体を組んだ時にはGRXは無く、34Tが使えるのはR8000だけだった。今は105のRD-R7000-GSもあるので34Tまでは対応できるし、11-34Tの11速カセットなら10速のフリーボディのホイールでも使えるというメリットも有る。
チェーン、スプロケのグレードについてはこっちを↓
シクロクロスレースではC4クラスの人達が降りて担いだりしてる坂の個所も自分は乗ったままクリア出来たりすることが多いです。『上れなければ自転車から降りて押すなり担ぐなりすればいい』と思うかもしれませんが、乗り降り、担ぎの繰り返しは『はっきり言って疲れます。』それで自分はストレートの最高速は捨てて低速寄りにして『自分の脚力の範囲で出来るだけ乗車で』でやってます。だけど、2019 スーパークロス野辺山 男子エリートクラスではエミル・ヘケレ選手が担ぎメインでブッチギリ独走優勝してます。(この辺が乗る人の『体力による』なトコロか?)
だからと言って『フロントシングル仕様で40Tにしてリアにデカいの(42T)入れて低速寄りにすればいいや』だと、ワイドレシオになり、チェーンのたるみも増え、焦ってシフト操作すればカセット側でのチェーン外れ率がスタビ付きとはいえ上がりますし、ディレイラーのスプリングテンションがヘタってくれば尚更です。カセットの重量もパーツ価格も上がります。
フロントダブルにすればスプロケは小さいもので済み、地上高もわずかに稼げますが、ギャップで跳ねてる最中のフロントシフト操作は即、チェーン落ちに直結します。それにBB付近での泥の付着が増えます。
それでも泥が付かないようなライン取り、丁寧な操作と踏み込みなんでしょうか?または、アウターとインナーの歯数差を小さくしてチェーンのたるみを少なくしてるからでしょうか?フロントダブルでもノントラブルの人はトラブル無しで走ってます。フロントシングルよりギア比幅が細かく広くなるから脚が疲れにくいか?
こんな感じになってしまい、『どれがいい』とは言い切れません…
------------------
あ、あとGRXクランクは太いタイヤで幅広になったフレームに対応するためチェーンラインが外側にきています。そのためQファクターも通常のロードクランクより広くなってますが、『Qファクターが広くなった分ペダル軸を短いものに換えれば帳尻が合う』と思うかもしれませんが、ペダル軸を短いものに換えると、シューズがクランクに接触しやすくなるので。
普通の状態だとシューズとクランクにスキマが有りますが…
ペダル軸が短くなるんだから当然、シューズは内側にいきますよね?(これは参考でやってるだけなのでペダルは換えてませんが…)『クランクに接触するから』と、クリート調整とかしたら本末転倒ですよ。。。
まだ続いちゃうな…
------------------
『桜 写日記 4/28 No. 9』
緑色が目立ってきた