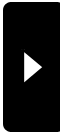さて、さて、さて、『つがいけサイクルクラシック』が終わって、次は6月末の激坂地獄の『ツール・ド・美ヶ原』。
去年の美ヶ原のレースタイムは何であんなに酷かったのかよく分からんけど、今年は初戦のつがいけの感じだと体は悪くはないと思うんだけど…
『美ヶ原に向けて練習をー』と、思ったが昨日は久々の降雨で今日の明け方近くまで降っていて、路面状況がハーフウエットだったため、今朝の練習はシクロクロスでダート練をすることに。

今日のダート練習は8の字走行ではなく、コース周回練習を。
サイクリングロードの水溜まりの周りには真ッ黄緑の縁取りが…春先の杉だけではなく、夏でもなる人はなるでしょう。雑草系(ブタクサ?)のでしょうか花粉です…
ここのところの好天のためか、草がかなり伸びている。。。そんなところも突破。
・・・突破していたんだけど、『ん?、ん―――?』と足元を見ると、草が巻き付いてなんだかエライことに。
Rディレイラーもガチャつくなと思ったら…
プーリーに草が巻き付いてた。。。
こういう草のところの走行なんかでも車体の構成がシフトインナーワイヤーがトップチューブ下でむき出しになっていると、BB下で草が巻き付いたりして変速不能になるんかも。
TCXはケーブルはフレーム内蔵(BB下でアウターワイヤーが少し出るけど)なのでその辺は問題無し。
ブレーキはディスクで地面から比較的高い所にあるので草を巻き込んで効かなくなるとかは無し。
そういえば、この前の『つがいけサイクルクラシック』で他の人の車体を見てたけど、ドロップハンドルでディスクブレーキの人は4台位しか見なかった。(下山時の途中の待機所で見た限りだけれども)
車体はスペシャのヴェンジで1台、ターマックかルーベのどちらか?(エアロではないフレームってので、どっちかは分からなかった)で1台、トレックのマドンで1台、後はジャイアントのANYROAD(トップチューブのスローピングが特徴なの)が1台。(ジャイアントのはアドベンチャー系でそもそもがレース向け設計ではないが…)
多分、実業団の人達でディスク車はゼロだったんじゃなかろうか。やっぱ、(上りオンリーの)ヒルクライムレースでは不利かねぇ…
それでも『もし、今フレームを替えるとしたら』って状況だったら候補としてCANYONのULTIMATEかTIMEのALPE D'HUEZ 21のどっちかのディスクで…なんて妄想してたが、この前のチャリダー見てたら、猪野さん、YONEXからTIME(ALPE D'HUEZ?グレードは分からん)に乗り換え? 先を越された
『つがいけサイクルクラシック』のゲストの福田さんが開会式のあいさつで言ってたけど、つがいけの直前にソルトレイクシティでやってたボーラ・ハンスグローエの合宿に取材で同行してたそうだけど、『日本でヒルクライムレースに出るから取材終わりで、日本に帰る』とペーター・サガンに話したところ『ヒルクライムレースって何?』と聞かれ、『山の麓から頂上を目指して、山を上ったら終わりなレース』と話したら『日本ではそんなクレイジーなレースをやってるのか!』とサガンに言われたそうな。(ここで言ってるクレイジーって『マゾ』って意味だよな…)
日本じゃ上って終わりなヒルクライムだけじゃなくて、下りもアリなロードレースにしちゃうと下りで崖下に落ちる人続出しちゃうから…
ジロ・デ・イタリアも最終週に突入。
デュムランが早々に去り、ログリッチが比較的有利で進んでいたけど(チームメイトにメイン集団の牽引をさせて疲労させたくなかったからか『後で取り戻せるから』とマリア・ローザを着なかった?)、二バリが虎視眈々と後ろから追い始め、サイモン・イェーツは山岳ステージに入ってからはアタックしてるけど、最初の週で失ったタイム差が痛い。チームで戦うモビスター、アスタナもどこまで粘るか
ジロ・デ・イタリア第18ステージ
ダミアーノ・チーマ選手(NIPPOヴィーニファンティーニ・ファイザネ)
よく最後逃げ切った(2位のパスカル・アッカーマン(ボーラ・ハンスグローエ)のハンドル叩きっぷりが凄ぇ…)
去年の美ヶ原のレースタイムは何であんなに酷かったのかよく分からんけど、今年は初戦のつがいけの感じだと体は悪くはないと思うんだけど…
------------------
『美ヶ原に向けて練習をー』と、思ったが昨日は久々の降雨で今日の明け方近くまで降っていて、路面状況がハーフウエットだったため、今朝の練習はシクロクロスでダート練をすることに。
------------------
今日のダート練習は8の字走行ではなく、コース周回練習を。
------------------
サイクリングロードの水溜まりの周りには真ッ黄緑の縁取りが…春先の杉だけではなく、夏でもなる人はなるでしょう。雑草系(ブタクサ?)のでしょうか花粉です…
------------------
ここのところの好天のためか、草がかなり伸びている。。。そんなところも突破。
・・・突破していたんだけど、『ん?、ん―――?』と足元を見ると、草が巻き付いてなんだかエライことに。
Rディレイラーもガチャつくなと思ったら…
プーリーに草が巻き付いてた。。。
------------------
こういう草のところの走行なんかでも車体の構成がシフトインナーワイヤーがトップチューブ下でむき出しになっていると、BB下で草が巻き付いたりして変速不能になるんかも。
TCXはケーブルはフレーム内蔵(BB下でアウターワイヤーが少し出るけど)なのでその辺は問題無し。
ブレーキはディスクで地面から比較的高い所にあるので草を巻き込んで効かなくなるとかは無し。
------------------
そういえば、この前の『つがいけサイクルクラシック』で他の人の車体を見てたけど、ドロップハンドルでディスクブレーキの人は4台位しか見なかった。(下山時の途中の待機所で見た限りだけれども)
車体はスペシャのヴェンジで1台、ターマックかルーベのどちらか?(エアロではないフレームってので、どっちかは分からなかった)で1台、トレックのマドンで1台、後はジャイアントのANYROAD(トップチューブのスローピングが特徴なの)が1台。(ジャイアントのはアドベンチャー系でそもそもがレース向け設計ではないが…)
多分、実業団の人達でディスク車はゼロだったんじゃなかろうか。やっぱ、(上りオンリーの)ヒルクライムレースでは不利かねぇ…
それでも『もし、今フレームを替えるとしたら』って状況だったら候補としてCANYONのULTIMATEかTIMEのALPE D'HUEZ 21のどっちかのディスクで…なんて妄想してたが、この前のチャリダー見てたら、猪野さん、YONEXからTIME(ALPE D'HUEZ?グレードは分からん)に乗り換え?
『つがいけサイクルクラシック』のゲストの福田さんが開会式のあいさつで言ってたけど、つがいけの直前にソルトレイクシティでやってたボーラ・ハンスグローエの合宿に取材で同行してたそうだけど、『日本でヒルクライムレースに出るから取材終わりで、日本に帰る』とペーター・サガンに話したところ『ヒルクライムレースって何?』と聞かれ、『山の麓から頂上を目指して、山を上ったら終わりなレース』と話したら『日本ではそんなクレイジーなレースをやってるのか!』とサガンに言われたそうな。(ここで言ってるクレイジーって『マゾ』って意味だよな…)
------------------
ジロ・デ・イタリアも最終週に突入。
デュムランが早々に去り、ログリッチが比較的有利で進んでいたけど(チームメイトにメイン集団の牽引をさせて疲労させたくなかったからか『後で取り戻せるから』とマリア・ローザを着なかった?)、二バリが虎視眈々と後ろから追い始め、サイモン・イェーツは山岳ステージに入ってからはアタックしてるけど、最初の週で失ったタイム差が痛い。チームで戦うモビスター、アスタナもどこまで粘るか
------------------
ジロ・デ・イタリア第18ステージ
ダミアーノ・チーマ選手(NIPPOヴィーニファンティーニ・ファイザネ)
ステージ優勝おめでとーーー!!
よく最後逃げ切った(2位のパスカル・アッカーマン(ボーラ・ハンスグローエ)のハンドル叩きっぷりが凄ぇ…)
さて、さて、さて、いよいよ『つがいけサイクルクラシック』本番当日。
今回は当日受付なので早めに出発して向こうで朝食取ってのんびり準備するつもり。4時半頃起きて、シャワー浴びて目を覚まし、5時頃出発。
------------------
丁度日の出の時間だった
------------------
まだ6時前なので『白馬長野有料道路』が無料の時間帯なのでトンネル使って白馬方向へ。ちなみに料金所の所の温度計は11℃の表示。
オリンピック道路も空いてるのであっさり白馬に到着。(自転車を積んでる車が全く居ないので『レース、今日だよな?』と不安になったり…)
------------------
つがいけサイクルクラシックの大会本部で受付の栂池村体育館には普通に走ってると『岩岳入口』の信号を左折して上っていけば行けるが、『時間有るから、レースコースの方を回って行くか』とちょっと遠回りを。
------------------
初出走なので分からないんだけど、『STARTのパネルが有るからこの辺がスタート地点なんかな?』と一枚。『…いきなりこの上りで始まんの?』ってのが正直な感想。
------------------
初出走だったが、何度か出てる人に『どんなコース?教えてくだせー』と聞いてはおいたので、それによると『んー…、最初パッパで、中チョロチョロ、最後ボーボー、かな?』と。
『最初の3㎞が勾配キツくて、体育館の辺で若干下りになってスキー場の商店街を抜けてく、緩く上りながらゲレンデに入って、その後に林間コースで緩急が有る区間になって、残り3㎞位で道が狭くなるゴンドラの駅の辺からまた勾配キツくなる。』
って、まとめるとそんな感じの説明。(実際にレースで走った後の感想で言うと、すげー正確なコースアドバイスだったと思う。感謝)
------------------
コースの最初の3㎞上った辺で山を一枚。
(水張った田んぼに映ってて、なんかカレンダーの写真っぽい?)
(水張った田んぼに映ってて、なんかカレンダーの写真っぽい?)
------------------
大会本部の体育館駐車場に6時半過ぎに到着。まだ車が少ないな?朝食取ってのんびり準備に。
いつもの自分の予定だと『レース前の荷物受付の時間に合わせて30分位固定ローラーでアップする』なので受付を済ませてのんびりストレッチで体伸ばして8時ちょい前からローラー台に。
7時頃の選手駐車場の様子。この後まだまだ他の選手は来る。
------------------
ローラー台でアップしてると、時間が8時過ぎてきたので気温がぐんぐん上がってるのが分かる。風が吹くと風が涼しいが、無風だとすでに暑い。選手集合の時間が近いので、準備してスタート地点へ。荷物を預けたらコースの最初の区間をみんな試走してるので自分も走っとくことにした。『うへー、やっぱ、(勾配)キッツイな』
------------------
で、開会式が終わり実業団クラスから順にスタート。エントリー総数数百人でもそれなりに人は居る。(それにしてもここだけの話じゃ無いが、もう少し各イベントの開催日を分散させて参加者を増やさないと…)
------------------
各クラスがスタートするごとに前の方へ進んでいき、自分のクラスのスタート。クラス人数は30数人(少な…)。3列目からのスタート。※ここからはシマノカメラで撮った動画の切り取りです。
スタートして黒い計測ラインを過ぎると…みんな(自分からすると)いきなり超ハイペースで行くんだけど!?
『イヤイヤ、トップ取る人達ならともかくみんなが400W~とかで行けるわけ無ぇ』と、自分はいきなり飛ばさず250W~位でマイペース。
ケツ集団の頭で走りながら1㎞位すると、案の定10人~は落ちてきた。落ちてきた人たちをパスしてくけど、この『つがいけサイクルクラシック』は一般人はジャージの後ろやハンドルにゼッケンを付けず、車体のトップチューブだけにプラのゼッケンプレートを取り付けるため、前を走ってる人、後ろからくる人がどのクラスなのか正直分からない。
『後ろから抜いてくる人はペースが速きゃ別クラスの速い連中だろうから、前に居る人を追いつけ追い越せでいくしかないな』の走り方。
------------------
最初の上り区間を終えて商店街へ。
ここら辺の事をアドバイスされたのは『若干下りで始まって平坦気味になるけど、無理に速く走ろうとして脚を使うな』だったので、この後の上りに備えてあまり踏まずで。
------------------
ちょい道悪な所を通って林間コースへ。
アドバイスだと『ここから緩急が有る区間』って事だったが、自分は『だらだら上り』より『緩急ある上り』の方がまだいいので(決して好きではない)、ここから少しペースアップ。
…とはいえ、やっぱり全くの初走行なので、目の前のブラインドコーナーを曲がった後が上ってるのかそのままなのか分からんので、見える所は攻めていく走り方。コースの感じは美ヶ原や乗鞍エコーラインの中間部分みたいな感じ。
------------------
残り3㎞の『栂の森駅関門』
アドバイスでは『最後3㎞位がまたキツくなる。』だったので、ここまでまだ脚は残してた。前後に(同じクラスの人と思われる)複数人が居るけど、前の人にも追いつかず、後ろの人からも迫られずな感じだったが、『残り1㎞で脚が残ってるなら、そこからペース上げて一気に前の人を抜いてこう』と決めて残り1㎞地点へ。
まだ踏める力があったので一気に前に追いつきパス。(同じクラスの人だった)上の方を見ると、人が大勢居るのが見えるので『あそこがゴールか』と思って前にまだ1人見えるので、なんとか最後追いつき追い越せで。
なんとか追いついた
下山の人が来るので『この左コーナー曲がればゴールか』と踏む踏む。
で、曲がるが『ゴールラインが無いけど!?』と思ったら
その先でした。
ゴールーーーーーー
------------------
タイムは1:12分。目標タイムは『1:10切れれば上出来』と思っていたので、チョイ届かず。ちなみにアドバイスされたときに『タイムは多分マウンテンサイクリングIN乗鞍の5~10分速いタイムになるんじゃねぇかな?』とのアドバイスだったが、確かにそれに近かった。
疲れは有る事は有るがそこまで酷くは無く、コースを覚えればまだタイムアップは出来る感じ。
すごく走りがいがあるコースだった。(来年も出るか…)
------------------
ゴール地点にはまだまだ残雪が。
下山荷物受け取って濡れタオルで顔拭くのがサイコー
------------------
そしてチョイ休憩して下山に。下山はゴール付近は道幅が狭いので個々に1列で最初は下る。
途中で一枚。上ってる最中も見てたけど山がキレイ
で、下山は途中で一旦待機に。コレがみんなかなり(待ち)疲れたんでは?結構な待ち時間だったので飲み物もう1本下山用荷物に入れとくんだった。日差しがキツく正直ヤバかった。(どうにもヤバかったら下山荷物にビニール袋を入れてたので、その袋に雪を入れて首に当ててようかと思ってた。土や木で汚れてるのでさすがに飲むのは無理)
------------------
行列が動き出し、無事下山ー。(運悪く何か踏んだんだろうけど、やっぱり途中でチューブ交換してる人は居た)
車に戻ってきたら炭酸500のペット一気飲み。暑っつー
------------------
片付けやって体育館へ行くと完走証とリザルトが出てた。リザルトは周り(上の人)が速くクラス順位は真ん中から一つ二つ位下。自分の一つ上の人とは分差がついてるのでそこのグループについていけないとな。ついていければ1:10分は切れそう。
ちなみに中間地点の看板までのタイムが41分。コースレイアウトが前半と後半のどちらがキツイのかはわからなかったけど、単純にそのままのペースで走ってたら1:22分ってタイムになる計算だけど(そんな簡単な計算になるわけないが)、今回だと後半でペース上げてって、後半で10分詰めて、まだ脚が残ってたって事になる。(パワー数値は前半、後半であまり変わらないが後半はケイデンスを上げての走行=パワーは変わらずで速度アップになってる)
ただ、去年と比べると途中でスタミナ切れってのが無く、最後まで脚を残せて、最後の1㎞でもう一段ペース上げられるってのが出来たので(脚を残しすぎたが)そこは良かった。
------------------
次は6月末の『ツール・ド美ヶ原』。激坂超えて、美鈴湖過ぎて、笹林超えて、放牧地突破ですよ。
------------------
追記
全国版のニュースで今、知りました。
宮古島のロードレースでゴールスプリント中と思われる落車死亡事故が発生したのですね…御冥福をお祈りいたします。
今日も雲が無い快晴だったねぇ…朝8時頃までは涼しいんだけど、そこからグングン気温上がって昼には30超えかい…
さて、さて、さて、今朝はそれでも自転車で走る時間があったので、1時間未満でも走っとく。
その後、車体から不要な物は取り外していよいよ本番用に仕上げ。
(自作のペットボトルの)ツールケースと中身、ボトルケージ、テールライト等を外して770gの軽量化
これで本番用
ペダル、サイコン、アクションカメラ等全部有りで後はゼッケンとボトル付ければレースに走れるよ。な状態での重量は7.3㎏。(フレームはラピエールのXELIUS SL Ultimate 2017年の1stモデル(19年モデルでマイナーチェンジが加えられた) サイズは52)
ハンドルがアルミだったり、コンポはチェーン以外DURAを使ってないのでまだ軽量化の余地は有る。
・・・余地は有るが、金が無いっと…
で、車に積み込みー
の前に確認。サイコンや各センサーのバッテリー(ボタン電池)残量はOK?
パワーメーター(Stages)のスマホアプリ画面。スマホアプリ画面(右上)でバッテリーの残量が確認出来るが、Stagesはボタン電池の残量が少なくなると、サイコン(Rider530)の画面にも『バッテリー少ないよ』の表示が出てくれる。
ハートレート(ハートレートはリストバンド式のMio)は充電中ー
車体側にスピードセンサーが付いてるのでそこのボタン電池も新品に交換。
そして、バッテリーだけでなく、サイコン、ハートレート、カメラのデータ保存空き容量もOK?
ハートレート(Mio)はMIo自体にデータを保存できる(けどサイコンの方のデータしか見てない)
サイコンの使用容量も問題無し、カメラ(シマノ CM-1000)のSDカードは空っぽ。撮影時間は32GBカードで2時間半位は撮れるけど、バッテリーがフル充電しても1時間半くらいしか持たない…
寝るー
------------------
さて、さて、さて、今朝はそれでも自転車で走る時間があったので、1時間未満でも走っとく。
その後、車体から不要な物は取り外していよいよ本番用に仕上げ。
(自作のペットボトルの)ツールケースと中身、ボトルケージ、テールライト等を外して770gの軽量化
これで本番用

ペダル、サイコン、アクションカメラ等全部有りで後はゼッケンとボトル付ければレースに走れるよ。な状態での重量は7.3㎏。(フレームはラピエールのXELIUS SL Ultimate 2017年の1stモデル(19年モデルでマイナーチェンジが加えられた) サイズは52)
ハンドルがアルミだったり、コンポはチェーン以外DURAを使ってないのでまだ軽量化の余地は有る。
・・・余地は有るが、金が無いっと…
------------------
で、車に積み込みー
の前に確認。サイコンや各センサーのバッテリー(ボタン電池)残量はOK?
パワーメーター(Stages)のスマホアプリ画面。スマホアプリ画面(右上)でバッテリーの残量が確認出来るが、Stagesはボタン電池の残量が少なくなると、サイコン(Rider530)の画面にも『バッテリー少ないよ』の表示が出てくれる。

ハートレート(ハートレートはリストバンド式のMio)は充電中ー
車体側にスピードセンサーが付いてるのでそこのボタン電池も新品に交換。
------------------
そして、バッテリーだけでなく、サイコン、ハートレート、カメラのデータ保存空き容量もOK?
ハートレート(Mio)はMIo自体にデータを保存できる(けどサイコンの方のデータしか見てない)
サイコンの使用容量も問題無し、カメラ(シマノ CM-1000)のSDカードは空っぽ。撮影時間は32GBカードで2時間半位は撮れるけど、バッテリーがフル充電しても1時間半くらいしか持たない…

------------------
寝るー
『ヒルクライムレースに出るなら~』で書き始めましたが、一応今回で最後です。
今回は『レース走行中~ゴール~下山~』です。(下山で終わりじゃないよ)

レースは基本的に道路を車などの一般車を通行止め規制にして行われますが、左側通行が原則です。右側車線は運営車両、サポートカー、緊急車両、報道車両、下山の自転車が走る為走行禁止です。右側走行をしていると審判員から「ゼッケン○○番の人、左側を走って」と注意されますので従わないと失格処分です。
○走り慣れていない時は、左端の白線から1m位のほぼ車線の中央のところを走るのが良いかと。
一番左端側だとレース直前に雨が降った場合に路面のゴミが溜まりやすく、パンクや木の枝をホイールに巻き込むリスクが有ります。
長野のヒルクライムレースのコースは冬は路面凍結するため、ひび割れが発生していることがよくあります。また、車が通り轍となって凹んでいる所も雨の後だと砂やガラスが溜まりやすく、アスファルト剥がれの穴が有ったりします。
そのため左車線の中央辺りのラインが比較的安全かと。(※車線中央にマンホールのフタが有る時もあるので気を抜かないように!)
※センターライン寄りはスピードが速い人が走るので居ると危険。怒鳴られる場合が有ります。
○坂がキツイ時でも蛇行走行はしないこと。「危ない!」と怒鳴られること有り。
※前の人を追い抜く時は「右側から追い抜く」という原則もあります。
追い抜くときに「右(から)、行きます!」など前の人に声をかけてから抜くのもマナーです。逆に追い抜かれる時は急に進路変更をすると接触事故につながるので、出来れば横や後ろを確認してから左に寄れるように走行して下さい。(進路変更せずにそのまま真っすぐ走っていれば抜いていく人が右側から抜いて行ってくれるはずですが…。)※センターライン寄りを走っていると左側から抜かれる時もあるので注意!
同じペースで走っている人が前後にいる場合は追い抜くたびに声をかける必要は有りませんが、接触しないように存分にバトって下さい。
○仲間と横に広がって並走するのはダメですし、縦につながる通称「トレイン走行」ですが、某マンガやテレビ番組で「風の抵抗が減るので、近ければ近いほど効果が高く、走行スピードが上がる」などと言っていますが、タイヤ同士が接触して集団落車の原因になるので、慣れていないと非常に危険なので超接近はお勧めしません。もし、前の人が急停止や落車しても避けられる間隔は開けた方が安全です。
真面目な話、ウチら一般人がヒルクライムレースでは走ってても平均時速13㎞/hとかなので向かい風が超強い時とかでなければトレイン走行の恩恵はあまり期待できません。無理に人のペースに着いていくより自分のペースで走ってる方が気疲れしません。
走り慣れてくると風の抵抗とか関係無しに『あの人の後ろに着いて引っ張ってってもらおうー』ってなりますが…
誰かの後ろに着いての走行の時は、前に走っている人が『前(走るの)、代わって』の合図、肘をクイッと動かしたり、片手運転になって明らかに『先、行って』のサインを出したり、後ろ見て何か言ってる時(風切り音で聞こえない時も多いですが『回って』とか言ってるはずです)は前を走るのを代わりましょう。(ローテーションとか回って走るってやつです)前を走っている人が右側に避けるのでその時に前に出ましょう。
引く時間(距離)はもう、はっきり言ってその時次第ですが、『じゃあ○○秒交代でー』とか『○○メートル交代でー』と言ったり言われたりだったり、無言で適当だったり様々です。(サイコンで引いてる時間や距離見れればそれチラ見して回る。自分が先頭の時はやたら長く引かされてる気分にはなる…)
ローテ走行は慣れてなければ『???』なので実戦で覚えるか、練習会みたいなのやチームなどに参加して覚えるしかないでしょうか。
…とはいっても、最初は自分が坂を上るのに必死で、前の人のサインとか見たり、交代を促されても前に出る余裕が無いってのが普通なので…
○レース中、どうしても体調不良、メカトラブルなどでスロー走行、走行出来ず停車する時は周りの人に「左寄ります」など注意を促して左端へ。
※停まった時でもすぐにはヘルメットは外さないで下さい。競技中にヘルメットを外すと即失格を宣告される可能性が有ります。
リタイヤする場合は停車すれば近くの審判員が来てくれるのでリタイヤを進言し、審判員の指示に従って下さい。メカトラブルの場合はサポートカーを呼んでくれて修理してもらえ、再走行できるかもしれません。
リタイヤはしないが自転車を押して上っている場合は、残念ながら制限時間により足切り(強制リタイヤ)になるかもしれません。その場合はコースオフィシャルの方の指示に従って下さい。
レース途中にCP(チェックポイント)があり、給水やトイレが使用できたりします。
給水はレーススタッフの方がマラソンのように紙コップを手渡しで渡してくれますが、水を受け取るために急減速、急車線変更、片手運転でのふらつき等での落車が非常に多いです。
自分は落車に巻き込まれるのは勘弁なので水が不要な時は給水所には近寄りません…
給水は右側だったり左側だったりまちまちなのでどちらの手でも取れるように。飲んだ後の紙コップは『こっちに投げてー』と人の居ない方に投げるように指示されます。落車の原因になるので下(走行ライン)には落とさないように。
『マウンテンサイクリング IN 乗鞍』の三本滝ゲート前のCP。左側は陣太鼓での応援

また、キャッチが面倒な時は体を冷やすために『その紙コップの水をぶっかけてー』ってスタッフに言えば喜んで容赦なくかけてくれます。(スタッフの多い乗鞍で頼んだら3人位にかけられた)
また、CPには通過制限時間が設けられている場合があり、時間内に通過できないと足切り(強制リタイヤ)で回収車に捕まります…
ゴールは終盤で体力、気力がキツイところですが、過度に左右に車線変更するような走行は禁止です。特に『マウンテンサイクリング IN 乗鞍』、『ヒルクライム佐久』などはゴール直前のコース幅が狭いのでふらつき走行をしないように。
また、「ハンドルから両手を離して走行してはいけない」と規定されているレースも有ります。(要は両手離しのガッツポーズ走行は転倒、接触の可能性が有り、危ないので禁止。ということ)
『マウンテンサイクリング IN 乗鞍』のゴール地点(岐阜と長野の県境の所)。右側車線は下山する人用に仕切られている
ゴールラインを通過してもすぐ停車せずにスロー走行のまま進んで下さい。直ぐ停まると後続車に追突される危険があります。案内係の人がいるので誘導に従い、待機所へ移動します。
自転車を停めて一息ついたらスタート前に預けた荷物を受け取りに行きます。
「ゼッケン○○です」と荷物係の人に言うと、荷物を探してくれるので受け取って体が冷える前に汗を拭いたり、防寒着を着るなどして下さい。
下山は早くゴールした人達から順次グループとなり下山先導員の後について下山します。(ヒルクライム佐久はコース幅の関係から全員ゴールしてから下山。早くゴールしていると3時間以上頂上で待つ場合が有ります。防寒着が無いと多分風邪をひきます。)
これは『ツール・ド・美ヶ原』のゴール地点の様子
繰り返し書きますが
●下山の時の方が事故が発生しやすいので気を付けて下さい
○絶対に速く走ろうとしない事
○下山前に(ブレーキ熱でチューブ内の空気が膨張するのを緩和するために)タイヤの空気を少し抜いて空気圧を落としている人がいますが落としすぎない事。
特にクリンチャーの人。空気を抜きすぎか、ブレーキ握ったまま段差に行っての前荷重過ぎてか下山走行時にリム打ちパンクする人が必ずいます。
○仲間と並走は危険ですので横に広がらないように、また、会話に夢中になって前方確認をおろそかにしないように。
下山してスタート地点まで戻ってくると、受付の近くで「レース完走 証明書」を発行してくれます。(すぐ発行できない場合もあります)
また、ある程度のタイムで走れればリザルト(レース結果)が貼りだされている事があるので、自分の成績、クラス何位で走行タイムがどの位だったか。が確認できます。最近はQRコードを読み取ってサイトにレース速報を出してる場合が多いです。※このQRコードはレース当日の天候状況などでレースの開催可否や天候不順の為コース短縮になる等の連絡ツールにもなっているので、携帯に入れられるなら受付の時に読み込んでおきましょう。
その後は表彰式、閉会式となり(下山したら帰る準備をしてすぐに帰宅しても可)レース終了となります。
車での帰宅の場合は居眠り運転をしないように…家に帰るまでがレースです。
帰宅後は雨のレースの走行後ならシートポストを外すなどしてひっくり返して水抜きを。ボトムブラケット付近に水が溜まったりするとBB部の錆の原因になります。リムの中に水が溜まっている場合も有るので、タイヤ、チューブを一度外して乾かした方が劣化が防げます。
雨のレースでなくても走行後のメンテナンスは当然必要です。
メンテといえば、栂池の本番前の最後の練習をして、いつもの本番前の金曜日のチェーン、スプロケのメンテを。
(金曜日はほぼ昼からは休みなので。仕事が無いと分れば朝から一応休み) 本番用のチェーンに交換して約2週間でこの位汚れる


2週間の時間でも洗浄液は黒くなる

で、清掃後。


これで走れれば明日の朝軽く走って車体は準備完了ー。
その後に不要な物(ボトルケージ1個やツールケース等)を外して、レース当日はローラー台でアップするので後輪は練習用ホイールに戻してで完全に終了。
…なんか日曜日の気温は35℃いくかも。って言うじゃないっすか…まだ5月だぞ…
今回は『レース走行中~ゴール~下山~』です。(下山で終わりじゃないよ)
------------------
レースは基本的に道路を車などの一般車を通行止め規制にして行われますが、左側通行が原則です。右側車線は運営車両、サポートカー、緊急車両、報道車両、下山の自転車が走る為走行禁止です。右側走行をしていると審判員から「ゼッケン○○番の人、左側を走って」と注意されますので従わないと失格処分です。
------------------
○走り慣れていない時は、左端の白線から1m位のほぼ車線の中央のところを走るのが良いかと。
一番左端側だとレース直前に雨が降った場合に路面のゴミが溜まりやすく、パンクや木の枝をホイールに巻き込むリスクが有ります。
長野のヒルクライムレースのコースは冬は路面凍結するため、ひび割れが発生していることがよくあります。また、車が通り轍となって凹んでいる所も雨の後だと砂やガラスが溜まりやすく、アスファルト剥がれの穴が有ったりします。
そのため左車線の中央辺りのラインが比較的安全かと。(※車線中央にマンホールのフタが有る時もあるので気を抜かないように!)
※センターライン寄りはスピードが速い人が走るので居ると危険。怒鳴られる場合が有ります。
○坂がキツイ時でも蛇行走行はしないこと。「危ない!」と怒鳴られること有り。
------------------
※前の人を追い抜く時は「右側から追い抜く」という原則もあります。
追い抜くときに「右(から)、行きます!」など前の人に声をかけてから抜くのもマナーです。逆に追い抜かれる時は急に進路変更をすると接触事故につながるので、出来れば横や後ろを確認してから左に寄れるように走行して下さい。(進路変更せずにそのまま真っすぐ走っていれば抜いていく人が右側から抜いて行ってくれるはずですが…。)※センターライン寄りを走っていると左側から抜かれる時もあるので注意!
同じペースで走っている人が前後にいる場合は追い抜くたびに声をかける必要は有りませんが、接触しないように存分にバトって下さい。
------------------
○仲間と横に広がって並走するのはダメですし、縦につながる通称「トレイン走行」ですが、某マンガやテレビ番組で「風の抵抗が減るので、近ければ近いほど効果が高く、走行スピードが上がる」などと言っていますが、タイヤ同士が接触して集団落車の原因になるので、慣れていないと非常に危険なので超接近はお勧めしません。もし、前の人が急停止や落車しても避けられる間隔は開けた方が安全です。
真面目な話、ウチら一般人がヒルクライムレースでは走ってても平均時速13㎞/hとかなので向かい風が超強い時とかでなければトレイン走行の恩恵はあまり期待できません。無理に人のペースに着いていくより自分のペースで走ってる方が気疲れしません。
走り慣れてくると風の抵抗とか関係無しに『あの人の後ろに着いて引っ張ってってもらおうー』ってなりますが…
誰かの後ろに着いての走行の時は、前に走っている人が『前(走るの)、代わって』の合図、肘をクイッと動かしたり、片手運転になって明らかに『先、行って』のサインを出したり、後ろ見て何か言ってる時(風切り音で聞こえない時も多いですが『回って』とか言ってるはずです)は前を走るのを代わりましょう。(ローテーションとか回って走るってやつです)前を走っている人が右側に避けるのでその時に前に出ましょう。
引く時間(距離)はもう、はっきり言ってその時次第ですが、『じゃあ○○秒交代でー』とか『○○メートル交代でー』と言ったり言われたりだったり、無言で適当だったり様々です。(サイコンで引いてる時間や距離見れればそれチラ見して回る。自分が先頭の時はやたら長く引かされてる気分にはなる…)
ローテ走行は慣れてなければ『???』なので実戦で覚えるか、練習会みたいなのやチームなどに参加して覚えるしかないでしょうか。
…とはいっても、最初は自分が坂を上るのに必死で、前の人のサインとか見たり、交代を促されても前に出る余裕が無いってのが普通なので…
------------------
○レース中、どうしても体調不良、メカトラブルなどでスロー走行、走行出来ず停車する時は周りの人に「左寄ります」など注意を促して左端へ。
※停まった時でもすぐにはヘルメットは外さないで下さい。競技中にヘルメットを外すと即失格を宣告される可能性が有ります。
リタイヤする場合は停車すれば近くの審判員が来てくれるのでリタイヤを進言し、審判員の指示に従って下さい。メカトラブルの場合はサポートカーを呼んでくれて修理してもらえ、再走行できるかもしれません。
リタイヤはしないが自転車を押して上っている場合は、残念ながら制限時間により足切り(強制リタイヤ)になるかもしれません。その場合はコースオフィシャルの方の指示に従って下さい。
------------------
レース途中にCP(チェックポイント)があり、給水やトイレが使用できたりします。
給水はレーススタッフの方がマラソンのように紙コップを手渡しで渡してくれますが、水を受け取るために急減速、急車線変更、片手運転でのふらつき等での落車が非常に多いです。
自分は落車に巻き込まれるのは勘弁なので水が不要な時は給水所には近寄りません…
給水は右側だったり左側だったりまちまちなのでどちらの手でも取れるように。飲んだ後の紙コップは『こっちに投げてー』と人の居ない方に投げるように指示されます。落車の原因になるので下(走行ライン)には落とさないように。
『マウンテンサイクリング IN 乗鞍』の三本滝ゲート前のCP。左側は陣太鼓での応援
また、キャッチが面倒な時は体を冷やすために『その紙コップの水をぶっかけてー』ってスタッフに言えば喜んで容赦なくかけてくれます。(スタッフの多い乗鞍で頼んだら3人位にかけられた)
また、CPには通過制限時間が設けられている場合があり、時間内に通過できないと足切り(強制リタイヤ)で回収車に捕まります…
------------------
○ゴール~下山
ゴールは終盤で体力、気力がキツイところですが、過度に左右に車線変更するような走行は禁止です。特に『マウンテンサイクリング IN 乗鞍』、『ヒルクライム佐久』などはゴール直前のコース幅が狭いのでふらつき走行をしないように。
また、「ハンドルから両手を離して走行してはいけない」と規定されているレースも有ります。(要は両手離しのガッツポーズ走行は転倒、接触の可能性が有り、危ないので禁止。ということ)
『マウンテンサイクリング IN 乗鞍』のゴール地点(岐阜と長野の県境の所)。右側車線は下山する人用に仕切られている
ゴールラインを通過してもすぐ停車せずにスロー走行のまま進んで下さい。直ぐ停まると後続車に追突される危険があります。案内係の人がいるので誘導に従い、待機所へ移動します。
自転車を停めて一息ついたらスタート前に預けた荷物を受け取りに行きます。
「ゼッケン○○です」と荷物係の人に言うと、荷物を探してくれるので受け取って体が冷える前に汗を拭いたり、防寒着を着るなどして下さい。
------------------
下山は早くゴールした人達から順次グループとなり下山先導員の後について下山します。(ヒルクライム佐久はコース幅の関係から全員ゴールしてから下山。早くゴールしていると3時間以上頂上で待つ場合が有ります。防寒着が無いと多分風邪をひきます。)
これは『ツール・ド・美ヶ原』のゴール地点の様子
繰り返し書きますが
●下山の時の方が事故が発生しやすいので気を付けて下さい
○絶対に速く走ろうとしない事
○下山前に(ブレーキ熱でチューブ内の空気が膨張するのを緩和するために)タイヤの空気を少し抜いて空気圧を落としている人がいますが落としすぎない事。
特にクリンチャーの人。空気を抜きすぎか、ブレーキ握ったまま段差に行っての前荷重過ぎてか下山走行時にリム打ちパンクする人が必ずいます。
○仲間と並走は危険ですので横に広がらないように、また、会話に夢中になって前方確認をおろそかにしないように。
------------------
○下山~レース終了
下山してスタート地点まで戻ってくると、受付の近くで「レース完走 証明書」を発行してくれます。(すぐ発行できない場合もあります)
また、ある程度のタイムで走れればリザルト(レース結果)が貼りだされている事があるので、自分の成績、クラス何位で走行タイムがどの位だったか。が確認できます。最近はQRコードを読み取ってサイトにレース速報を出してる場合が多いです。※このQRコードはレース当日の天候状況などでレースの開催可否や天候不順の為コース短縮になる等の連絡ツールにもなっているので、携帯に入れられるなら受付の時に読み込んでおきましょう。
その後は表彰式、閉会式となり(下山したら帰る準備をしてすぐに帰宅しても可)レース終了となります。
車での帰宅の場合は居眠り運転をしないように…家に帰るまでがレースです。
------------------
帰宅後は雨のレースの走行後ならシートポストを外すなどしてひっくり返して水抜きを。ボトムブラケット付近に水が溜まったりするとBB部の錆の原因になります。リムの中に水が溜まっている場合も有るので、タイヤ、チューブを一度外して乾かした方が劣化が防げます。
雨のレースでなくても走行後のメンテナンスは当然必要です。
------------------
メンテといえば、栂池の本番前の最後の練習をして、いつもの本番前の金曜日のチェーン、スプロケのメンテを。
(金曜日はほぼ昼からは休みなので。仕事が無いと分れば朝から一応休み) 本番用のチェーンに交換して約2週間でこの位汚れる
2週間の時間でも洗浄液は黒くなる
で、清掃後。
これで走れれば明日の朝軽く走って車体は準備完了ー。
その後に不要な物(ボトルケージ1個やツールケース等)を外して、レース当日はローラー台でアップするので後輪は練習用ホイールに戻してで完全に終了。
…なんか日曜日の気温は35℃いくかも。って言うじゃないっすか…まだ5月だぞ…
この前の雨が通り過ぎた後は天気はしばらくは晴れが続くそうで、日曜日も晴れるみたいだけれど、長野でも30℃超えるとかいうようなこの時期としてはかなり気温上がるようなので水分補給は密に。(小学校とかも今週末に運動会の所も多いようなのでそちらでも熱中症には注意を)
------------------
さて、さて、さて、『ヒルクライムレースに参加するなら…』というネタで続けて、今日はレース当日のお話。
------------------
ヒルクライムレース現地へ行く時の事として、まずは荷物の積み忘れに注意。
自分は一度レースボトルを忘れた事があります。。。前日の練習で使った後、台所で洗って乾かしてて、そのまま積み忘れという…レース会場に出店が出ていたので現地で購入してそれで済みましたが…
それ以後は自分で荷物のチェックシート作って、積み込み準備するようにしてます。
------------------
(レース当日に受付をする場合は)参加証を忘れずに。で、現地に着いたらもうこれです。
トイレは行ける時に早めに行っとけ
レース当日は仮設トイレをメイン会場など置いてくれる事が多いですが、「開会式の集合の時にトイレに行けばいいや」と思って集合場所に行くと、例外なくトイレ待ちの大行列になってます。20分待ちとかわりと普通です。(ビブタイツだから時間かかるのよ。)「レーススタート直前に行こう」なんて考えだと、最悪トイレに行けずにスタート時間に!なんて事も。
------------------
集合場所には各クラス別に並んで待機するようになっていますが、早い者勝ちで早く前の方に並んでいた方がスタートで有利。という事はありません。※後で理由を書きます。(初参加でいきなりチャンピオンクラスにエントリーする強者はいない前提で書いていきますが)
------------------
これは『マウンテンサイクリング IN 乗鞍』のレース当日の開会式場。この時(2015年)は雨で距離短縮レースだったので、自転車だけ並べて乗り手はテントで雨宿り…
------------------
開会式が終わったらヒルクライムレースだと各クラス別に数分おきにスタートとなります。自分のクラスのスタート時間が近くなると待機場所からスタート地点へ移動するのですが、移動前にサイコンのセンサーがちゃんと送受信するかの動作確認をやっといた方がいいです。 ワイヤレス方式だと個別のセンサーでペアになっていて混線しにくいはずなんですが、乗鞍とかで周りに何千人とか居るとどうも受信しにくくなる時があります。
また、この時も早くスタート地点へ移動した方がスタートで有利。ということはありません。まだあわてるような時間じゃない
------------------
いよいよスタートですが、タイム計測は陸上競技であるような号砲が鳴ったら全員一斉に計測開始、ではありません。(※チャンピオンクラスで例外あり。あと岐阜乗鞍、(今年はもう終了したけど)19年の車坂峠も)「後ろからスタートしたからスタートラインまで○○秒ロスした」、みたいな感じがするかもしれませんが、ヒルクライムレースでは案内の用紙などに「タイム計測はネットタイム方式です」みたいなのが書いてあるはず。 このネットタイム計測方式の為、焦ってスタートポジションを取らなくてもいいんです。むしろ遅くスタートした方が有利?かも。
ネットタイム計測方式は。。。
スタートのラインの数メートル先の地面に(多分、黒か緑の)マットが敷いてあるので、 そこを自分の計測器が通過したら自分のタイム計測が始まります。なので最前列からロケットスタートで先頭で3秒で通過しようが、一番最後で2分かかってようが計測開始地点通過までにかかっている時間は測っていないのでタイム差になりません。 (しかしながらTV収録とかある時はロケットスタートすればTVに映るかも)※スタートの合図で一斉にタイム計測が始まるのは『グロスタイム計測』となります。
------------------
(これはマウンテンサイクリング IN 乗鞍 2018の時の)スタートするとスタートのアーチをくぐりますが、アーチを通過したら計測開始ではありません。
アーチの直ぐ先の地面に(乗鞍では緑色の)マットが地面に敷いてあり、そこを自分の計測器が通過したら計測開始になります。
------------------
ちなみにシクロクロスではグロスタイム計測が多い為、スタートからポジション争いが凄まじい。
そのためスタートで超パワー掛け過ぎてのいきなりチェーン切れや焦ってシフトアップしてのチェーン外れとか見てます。
------------------
※サイコンをオート計測モードにしていると、車輪が動き始めたら計測が始まる為、計測開始地点までの距離とタイム分が公式記録とは誤差が出てしまうので、マニュアル計測にした方が正確になります。
極端な話、スタートの号砲が鳴ってから少し止まってても問題ありません。(実際に記念撮影してからスタートしてる人や膝の屈伸やってからスタートしてる人が居る位)
前にも書きましたが、焦ってスタートしようとしてペダルをキャッチミスしていきなり転倒。ってのも有りますし、スタートの号砲が鳴っても渋滞している為、前が動き出さないと走り出せないので、最前列の方でなければスタートの号砲が鳴ったからといって直ぐにペダルを嵌める必要はありません。
自分は一回深呼吸して前の人が動き出してからゆっくりペダルはめてスタートするようにしてます。
------------------
実際にこの位の密集度からスタートになる。(これは車坂峠ヒルクライム)この時はまだ後ろの方だったので密度が低い方。スタートの号砲が鳴ったからといって、直ぐに動き出そうとしない事!
※とはいえあまりゆっくりしすぎると後ろの人のスタートの妨げになりますので。(完全に一呼吸いれて、遅れてスタートするつもりなら出来るだけ後方からのスタートを)スタート前で殺気立ってますし。。。
------------------
『スタート30秒前ー!』等のアナウンスが有って、みんな一斉に片足のビンディングペダルはめる「バン、バチン」て音が鳴り、10秒前位で会話が無くなって静まりかえるとレースらしく結構テンション上がりますよ。(それでも焦らずスタートしましょう)
渋滞が収まってきたからといって、急に速度を上げて行かないように。とりあえず走行ラインの変更はなるべくせず、出来るだけ真っすぐ走った方が安全です。『1秒でも速く走りたい!』というのであればスタートポジションは前の方が良いです。
自分は『おっしゃー、ボチボチ行くべさー』位なペースでスタートしてます。
タグ :ヒルクライムレース
ヒルクライムレースのレース前日(受付)
ヒルクライムレースはほとんどが日曜日に開催の為、大抵前日の土曜日から受付が始まります。(土曜日と日曜日の2日間やるイベントも有ったりもしますが)
「レース当日の受付は不可」というイベントも有ります。前日に現地入りが無理な場合は代理受付が可能な場合も有ります。『前日に受付に行く人に自分の分の参加証を渡しておき、受付をしてもらう』で済ませる事も出来ます。
●代理でも自分が受付にいく時でも参加証、(提出が必要なイベントでは)整備申告書等を忘れないように
乗鞍スカイラインヒルクライムの受付会場(土曜日の昼頃)の様子。こっち側は受付と車検(乗鞍スカイライン ヒルクライムは現地で車検(有料)も出来ますが、現地では修理が不可な場合もあるので、事前に整備を)写真を撮ってる後ろ側には各店のブースが出てる。
受付をしたら計測チップの動作確認をする場合もあります。
------------------
受付を済ませると大抵大きな袋を渡されるので、リュックを背負っていったが方が楽。
受付会場には色々なブース(出店)が出ていて、掘り出し物が有ったりする(ウェアとかタイヤとか格安だったり)ので、お金(カード支払いが出来ないことが多いので現金で)を持って行った方がいいかも。
ほかにも試乗車を出しているメーカーもあるので100万円~クラスの車体の試乗なんかも出来るので、乗りたい人はヘルメット、グローブ持参で。(べダルはフラットペダルだったり、ペダルを持っていけば換えてくれたり)試乗するのであれば事前に自分の乗っている車体のBBセンター~サドル座面(上面)までのポジション数値を覚えておきましょう。その数値をメーカースタッフの方に伝えれば試乗車のサドル高合わせがスムーズに行えます。
------------------
受付で渡される袋の中身は。。。
1・大会パンフレットや観光案内やお土産、タオルなどの参加賞
2・ウェアに付けるゼッケン1~2枚
3・ゼッケンを止めるための安全ピン
4・自転車用のゼッケン
5・荷札
6・タイム計測機 などです
2から6の付属品については説明書も付いていますが、ここでも順に説明します。
●2のゼッケンは最近は耐水の紙で出来たゼッケンですが、レースによって後だったり横だったり取付場所や向きに指定がありますが、ウェアに●3の安全ピンで取り付けます。あまりピッタリ取り付けると紙製のため破れやすいので少し緩めに取付を。
・・・レースに出てると安全ピンが大量に溜まっていくので『安全ピン回収箱』みたいの有ると助かるかも・・・
●4の車体用のゼッケンはハンドルに取り付けるタイプのものが最近は多いです。(ロードレースみたいにシートポスト付近に付けるヤツがホントはカッコいいと思うんですが、やっぱり正面からゼッケンが確認しやすい為とコストか)
※車体用だけでなくヘルメットの前面に貼るシールタイプを使うレースも有ります。
●5の荷札ですが、レース当日のスタート前に防寒着等を入れたリュックなどを一つ預ける事が出来ます。そのリュックに自分のゼッケンNoと名前を書いた荷札を付けて『下山荷物預け所』に預け、レーススタッフの方がゴール地点まで運んでくれ、ゴール後の頂上で受取る事が出来るようになっています。※レースによってはゴール後直ぐに下山が始まらず、全員がゴールしてから下山開始になるレースもあります。その場合ゴールしてから3時間とか待機になるので防寒着等は有った方が良いと思います。
乗鞍スカイライン ヒルクライムのゴール地点(畳平)の様子。スタート前に預けた荷物(ビニール袋に入ってる)がゼッケンごとに大体分けられていて、スタッフの人に『ゼッケン○○番ですー』と言えば探してくれます。8月でも畳平は15℃以下の気温の時もありますので…
●6のタイム計測機ですが、足首に巻くベロクロタイプとフロントフォークに取り付けるタイプが有ります。
------------------
※レースに持っていくと便利なのが
○荷札に名前を書く為の油性マジックペン
○予備の安全ピン、タイラップ
○タイラップをカットする為のニッパー
○紙ゼッケンが破れた時に補修する用のセロハンテープ
※タイラップはフロントフォークに計測器を付ける時に受付の袋に入っていますが、付け直したりする時用
この準備する時にやっといた方がいいのは、足首に巻くタイプの計測器の時は車体のトップチューブに忘れないように巻いておく。です。
過去に2回見ましたが、レース当日に足首に巻き忘れて焦ってる人を見ています。一人はまだ時間が有ったので取りに行けたようですが、一人はスタート2分前だった為間に合わずタイムが計測できないのでDNS(DNS=Do Not Start 『レース出走せず』の棄権扱い。)となったようです。(その人はそのまま走ってましたが。。。自分ならヘコんでとても走れそうにない)
------------------
コースの試走ですが、≪禁止≫と案内書に書かれている場合
受付会場がスタート地点の場合が多いので、通過する時に会場入口での事故には注意。
レース前日はまだレースの為の通行規制がされていません。地元の住人の方や、たまたま観光等で来ている方も道路を使ってます。止まらなきゃいけないところでは止まり、歩行者が居る所は速度を落とし、仲間と並走で走るなんてのは止めて下さい。
例えばツール・ド・美ヶ原だと野球場前からスタートして直進し、信号を右折して温泉街を抜け激坂区間になりますが、『美鈴湖まで試走でタイムアタック』などのつもりで信号無視で突破や激坂区間が終わる所の美鈴湖線との交差点を一時停止せず右折とかやらないで。
タグ :ヒルクライムレース
ヒルクライムレースに出る前に『上り走行練習』以外でやっておいた方がいい事、慣れておいた方がいいと思われる事を今回は書いていきます。
※実際に今までレース中、練習中に起こった事を元に書いていきます。
○スタート、ストップの練習
シューズを固定するビンディングペダルの人は必ず慣れておいて下さい。
速くスタートしようとして焦って、キャッチミス(シューズをペダルにはめられず)してシューズが滑って転倒。は起こります。
また、ストップ(急停止)時でも焦らずシューズを外せるように。
走行中、前の人がボトルを車体に戻す時にミスってボトルを落とし、拾おうとして急停止、なんてことも。(その地面に落ちたボトルを自分が踏めば前輪がスカッと滑っておそらく落車します)
いきなり目の前の人が突然落車とかホントにあるんで…
------------------
○走りながら(漕ぎながら)飲み物、食べ物を飲食する練習
ヒルクライムレースだと坂道を走行している低速で飲食が必要になります。平坦だとペダリングを止めても良いですが、上り坂だと低速走行になっている所にさらに片手走行となる為、フラフラ蛇行になりやすく危険です。
車体からボトルを取る時は下を見なくても取れる位には慣れた方がいいです。コースの状況が解るなら、坂の傾斜の緩い所で補給するというのも手段の一つです。
------------------
○下り走行の練習
ヒルクライムレースはゴールした後は自走で下山となりますが、レーススタッフの方が先導をして何十人かのグループとなって数分おきとかに分かれて下山していきます。
はっきり最初に書いておきます。下山はレースではないので、スピードを出す必要は全くありません。無理に前の人についていこうとは絶対に思わないで下さい。
これは実際にそうなのですが、ほとんどのレースで下山時に落車事故が起こっているそうです。
転倒は無くても段差でのリム打ちパンク、ブレーキ熱でのチューブバースト、ブレーキ熱でのカーボンホイールの破損、この3つのどれかはほぼ毎回自分は見ています。
慣れていない最初は出来るだけグループの後方で下山した方がいいかと思います。(後ろから煽られる感が少ない為、比較的落ち着いて下れる。それでも一番後方で下っててもゆっくり過ぎると次のグループの先頭が後ろから来るけど)
グループ分けの時に一番コースの左端で待機して、自分が前の方に居ても後の人に「先にどうぞ」と伝え、先に行ってもらう。
走り始めたら無理にペダルを漕ぐ必要はありません。下り坂なのでほとんどブレーキを掛けっぱなしになります。※矛盾するような話ですが、ブレーキ掛けっぱなしで下っていて、リムが高熱になり、チューブのバーストの原因になります。
ずっと掛けっぱなしにはせず、先の見通せるような余裕がある時はブレーキを放し冷やすように。
下る前に先導員から言われると思いますが、ブレーキを掛けて続けて疲れたり、指が痺れてきたような時は無理をせず、コースの左端に寄って止まって休みましょう。※ハンドサインが出せれば良いですが、手を放すと危なそうなときは周りの人に『左に寄って止まりまーす!』と大声で伝えて下さい。出来れば後方を確認しながら徐々に左側に寄りましょう。※最初から左端を走るというのもありますが、路面の端には砂、ガラス等が多く溜まっていることが有り、スリップ、パンクの原因になりますし、人が多いと走行ラインの変更がしにくいのであまりお勧めしません。
実際の下山時では複数回先導員が停車して途中で休憩するかと思います。そのときもハンドサインを出すか、声を出して周りの人にも停車するのが解るように。
前を見ず、下を見て走っていると追突します!ホントに。
------------------
下山の時はディスクブレーキが欲しいねぇ。。。残念ながらレース中(上ってる時)はブレーキはほとんど使わないので完全に(ホイールからして)重量物になってしまうけど…
本当の話としてヒルクライムレースでのディスク車は少ないと思います。各社ディスクモデルを出してきたり、軽量車体も増えてきているので徐々に増えていくとは思いますが、
(ここだけで判断できるものではないですが、(とはいえツール・ド・美ヶ原は後半に下り区間が有ってレースの時だと70㎞/hとか出ますが))ツール・ド・美ヶ原2018のチャンピオンクラスでは(確か)約200名居て、ディスク車はおそらく1台か2台。(自分のクラスのスタート時間が後ろだったので)他のクラスのスタートを自分のスタート時間ギリギリまで見てたり、レース中に抜いたり抜かれたりした人の車体を見てたが出場者1700人居てディスクロードは10~15台居るか居ないか位だった。マウンテンサイクリング In 乗鞍もディスクロード車率はおそらく1%位だと思う。(4000人居て40台位とか)
それでも自分は次の車体はディスクにしようかと検討中だったり…自分はガチじゃないので。
『山の頂上まで上ったらゴール』のヒルクライムレースって方が特殊なのかもしれないけど、アップダウンがあるロードレースやロングライド(速さを競うわけでなくて、疲労を溜めずに楽に下れるって事で)ではディスクブレーキの方が良いとも思う…
------------------
曲がる時はコーナーの内側のペダルは上(上死点)にする。これはペダルが地面に接触しての落車を防ぐため。
ツール・ド・フランスに出てる選手ですらコーナーで焦ってペダルを地面に接触させて落車はたまにあります。(ティボー・ピノやロマン・バルデとかがやらかしてる…)
また、9や3時方向の横にしていると、ハンドルを切った時に前輪にシューズが当たり落車の原因になります。(ある程度速度が出ていればつま先に当たるまでハンドル切って曲がることはないかもしれませんが…)
走行に慣れてきたら横にしていた方が段差をバニーホップ(ジャンプ)しやすいかもですが、ジャンプしないで済むならしない方が良いです。リムによろしくない。。。
------------------
○整備の方の話ですが、正しいタイヤへの空気の入れ方とチューブ交換の技術を身につけましょう
普段ルーズなのに「レースで走るのだからタイヤの空気圧は高圧で!」と最初から一気に強いポンピングで空気を入れると、バルブ口付近でチューブが噛みやすくなりバーストします。入れ始めはあまり力を入れずポンピングしましょう。
レーススタート前の朝の集合待機時にほぼ必ずバーストさせる人が居ます
『ゼッケン○○番の方~、タイヤがパンクしているようなので御確認をお願いします~』と恥ずかしいアナウンスをされますので。
その際にもスタートまでにチューブ交換が出来なければ出走できませんから!
※集合場所にはピットサービスが大抵あって修理してくれるかもですが、無料かどうかは不明。また、バーストした時の衝撃でタイヤが裂けたり、車輪に振れが出たり、バーストした衝撃でリムが変形することも有り、リム即死なんてことも。
------------------
文字ばかりの記事ですが、自分一人で転倒したからって済む話でもありませんし、他人を巻き込んでだと尚更です。
場合によってはレースそのものが中止、来年は開催せず。なんて事もありえますので、『エントリー費を払えば、競技ライセンスなど持っていなくても手軽に参加できる。』確かにそうなのですが、ルールやマナーを知らず、守らずで走っていい訳ではありません。
------------------
次回は 『レース前日(受付)について』 でいきます
------------------
オマケ
昨日の夜から大雨、強風注意報が出ていたが、『今日の昼からは天気は回復方向に』の予報だったので、今日は午後が休みだったので雨が止んだので『ウエットコンディションだから、じゃあシクロクロス練だ』と、出撃。
…走り出して10分位したらまたザーザー降りになってきやがった…
いつもの練習場所に到着したが、大きな水溜まりで池になってる・・・
池の隣に空缶を置いていつもの8の字走行を。
今週末はいよいよヒルクライムレースの本番なので、コケて打ち身とかしないように速く走るではなく、バランス走行の方向で走行練習。
走り出して数分もしないうちに雨は止んだ!
さすがにこの路面コンディションなので、普通に8の字走行をしようにも少しは前後荷重、ペダルの踏む強さ等を考えて走らないと、ホイルスピンしたり、フロントが曲がらずまともに回れない。
シクロ練も泥走行も久々だったので、疲れない程度に練習になった。
スリックタイヤからダートタイヤに履き替えて本来走る場所に帰ってきたTCX。
今年の春のプロロードレースではマチュー・ファンデルプールの快走があったりで、トレーニングとしてのシクロクロス、レースとしてのシクロクロスってのが改めて今冬注目されるかも…なんて思ってる。
前回からの続きです。
レース前の準備編 その2
レース前の準備編 その2
------------------
エントリーするイベントHPや案内書に服装、装備品についても規定があるはずです。
ヘルメットはもちろん必須で、被っていないとスタートラインに立たせてくれません。JCF(レースで使用できる)規格品、もしくはSGマーク品である物を使用するように指定があるはず。(ヘルメット自体にシールが貼って有る、無しで判断できます)。
グローブが必須だったり、上着は袖が無ければ不可、下はショートタイプの膝上までの物でないと不可など細かな規定があるレースもあります。気温が低い場合はアーム(レッグ)ウォーマーは可などの規定も有ります。雨の時に着るカッパにも規定があります。(透明でゼッケンナンバーが目視できる物でないと不可など)
服装に関しては自転車用のウェアがやはり自転車に乗る時の事を考えて作られている為、結局は一番快適かと思います。
サイクルジャージだと後ろにポケットが付いていますよね?そこに補給食やスマホ入れてといて走ったり出来ますが、ポケットが無いウェアを着ている場合だとウエストバッグやリュックを背負ってたりする人も居ますが、ベルトが擦れて痛くなるし、リュックは背中が蒸れるし、呼吸がしにくい等あまりお勧めは出来ません。
服装、装備品については各レースの運営さんによって細かな違いがあるので参加規程は必ず読んでおきましょう。
------------------
小物関係でと言うと、まず飲み物を入れるボトルですが、自転車用のレースボトルだといくつか種類があります。
最近は2重構造になっていて保温保冷機能に優れているボトルという物もありますが、大きさの割に容量が少ない為、取り付け取り外しが若干しにくかったり、中が見えない為、飲み物の残量が把握できない物があります。2重構造になっていないボトルでも不透明も物だと瞬間的に残量が把握しにくいと思います。
しかし透明なものが良いかと言うと、夏場は飲み物がすぐぬるくなりますけど…自分はそれでも透明なボトルを使ってます。
ツール・ド・フランスなどのプロのレース中継を見ていると、飲み物が無くなったら手を上げたりしてサインを出すとサポートやチームカーが飲み物を持ってきてくれるので飲み物の残量は気にしない場面も有りますが、ホビーレースのヒルクライムレースではそんなサービスはありません。
コース途中に給水ポイント(水の入ったコップをレーススタッフの人が持っていて手渡してくれる)がありますが、残量を考えずにボトルの飲み物を飲みきっちゃうと次の給水所まで飲み物無しで行かなきゃなりません。
かといって自転車にボトルを複数付けるとそれだけで重量がかさむので、『自分はどのくらいの距離や時間でボトル1本消費するのか』はある程度把握しておいた方が良いです。
------------------
アクションカメラで走行の動画を撮影する。というのが多くなりましたが、カメラの固定は確実に。付けられるなら落下防止の紐を付けときましょう。※車輪には巻き込まないように!
------------------
走りながら食べる補給食は…ヒルクライムレースだと自分の場合は長くても走行時間が90分かからないのでゼリーなどの補給食は持ちません。いつも使っているのど飴だけです。ほどほどに甘酸っぱく、ほどほどにスースーして呼吸しやすい気がするので。1個で大体2、30分位持つのでレース前の待ち時間分と合わせて6個位持ってるだけです。
※少しハサミで切れ目を入れておくと走りながらでも開けやすく、ゴミも落ちにくくなる。
-----------------------------
●レース前に走る以外のやっておいた方が良い(慣れておいた方が良い)事は次回に。
------------------
SIDIのシューズに取り付けた『アップヒール ロードラバーヒール』(長ぇ)。
自分のクリートはスピードプレイで黒いクリートカバーも付けてますが、アップヒールを付けるとかなり歩くのが楽です。
それ以上に楽なのが、和式トイレで楽です。
今日は長野各地でレースイベントが開催されていましたが、天気が良く暑かったんじゃないでしょうか?お疲れさまでした。
------------------
さて、さて、さて、ここから数回は以前書いたものをチョイっと修正を入れたりしてですが、これからヒルクライムレースに出てみようと思ってる人、初めて出る人向けにレース本番までの準備やレース当日どうすればいいか、などネタにしていきます。(イベントエントリーはしてある。という前提で進めます)
※もうレースに複数回出てる方には解りきった内容になると思います…
まず準備
○車体について
PCからエントリーした場合、イベントホームページに「車両規定」の項目が有る筈ですので、そこを確認してください。
※サイドスタンドは取り外す。が前提となります。普段の街乗り状態のまま出走している人が居ますが、はっきり言って危険です。
●転倒したままで先のとがったブレーキレバーやエンドバー。
●ワイヤーロックをハンドル付近やシートポストに巻きつけたままで出場 (ブレーキの引きずりやハンドルを切った時に引っかかる等)
※この2点は普段の街乗りでも危険なのでやらないで
当然ですが、『確実な整備がされている安全な車体』が出場の大前提です。超強調
(2019年の車坂峠ヒルクライムはこの記事を書いている時点ではもう終了してますが)車坂峠ヒルクライムだと参加案内書の中に『健康管理・自転車点検申告書』という書類が入っていて、自転車の各部が確実に整備されているかのチェック表をレース前日(もしくは当日)の受付の時に提出するようになっています。※イベントによっては「ショップで点検してもらって、ショップのストアスタンプが押してないと不可」というイベントも有ります。
また、レース2週間前には車体の整備はほぼ終わっている位の状態にして下さい。2週間前から整備し始めるでは遅いです。
※自分で整備、調整が出来て、練習も週に100km以上は余裕で走る。という人は別ですが、週末だけ練習できて、整備もお店で。という方は2、3週間の時間の余裕は必要かと思います。
○新品のパーツを付けたり、分解してグリスアップ等したら慣らし走行が必要です。
ワイヤー類を換えたら初期伸びがでますし、新品のタイヤは滑りやすい、ブレーキパッドは慣らしをしないと効かない、グリスアップしたばかりだと回転が重くなる、チェーン、スプロケ類は新品状態だと角が取れていなくて入りが悪い等々…
「明日レースなので前日に新品に換える」だと逆にタイムが遅くなる事も有りますよ。(新品パーツには保管時の錆防止のために過度にグリス付けてる物などもあるので)
目安的には2週間前にはほぼ整備を終わらせ、チェーンやスプロケ等の駆動系を換えたなら平坦路で良いので過度に力を入れずに踏んでゆっくり変速を繰り返し、全てのギヤにスムーズに入るか。の慣らしでギアやチェーンの角(カド)を取る。ワイヤー類の初期伸びが無いかも確認。
ブレーキパッドを換えたなら(後ろに人が居ない所で)ブレーキを握る、放すの繰り返しでパッド表面を一皮剥く。タイヤも一皮剥く。
グリスアップをした個所も回す方向で馴染ませる。
チューブについては自分はパンクとかしていなくても毎年春前に交換していますが、(本番はチューブラー)あまりタイヤに入れっぱなしのチューブだとタイヤとチューブが張り付いて急に高圧かけて空気入れるとチューブ表面のゴムの剥がれてパンクするっていう事が起きますよ。
そして1週間前には微調整してとりあえず車体準備は終了かと。例えばチェーンを交換した場合、ここでもう一度チェーン清掃をすれば凄い切り粉(鉄粉)が出るはずです。
●次は服装と小物や「走る」以外にやっておいた方が良い練習をネタにしようと思います。
(通行止めにならない天気で良かった…) 上ってきたよ乗鞍スカイライン
------------------
昨日の夕方から夜の時間帯の雨雲レーダーだと長野市は雨は降らなかったが、岐阜、長野の県境は雨が降っていたようで、それが今日残らなくて良かった、良かったよ…
------------------
「乗鞍は雨は降って無さそうなので、濃霧が出てなければ通行止めは無いな。昨日の雨で砂埃が舞わないなら、今日は景色が霞んでないかも」と期待。
国道158号線の朝の通勤ラッシュ渋滞を避けたかったので、早めに長野発。乗鞍スカイラインのゲート前、平湯峠の駐車場には7時前に到着。雲はあるけど、霧は無し!朝7時でほおの木平スキー場の駐車場手前の道路の温度計表示は10℃。
乗鞍スカイラインに自転車で上る場合は自家用車では通行止めになる平湯峠ゲートの手前に20~30台分位の駐車場が有ります(無料)
------------------
到着したが、トイレに行きたくなったため一旦ほおの木平スキー場の駐車場へ向かう。
※平湯峠ゲート駐車場にはトイレや自販機等は有りません。あくまで駐車できるだけ。
国道158号線に案内看板が出てますが、ほおの木平スキー場の大駐車場に駐車(こちらも無料)して乗鞍スカイラインに上ることも可能です。24時間稼働の自販機、トイレがあります。
ただし、ほおの木平スキー場の駐車場から上ると走行距離が7㎞位増えます。6%位の勾配の国道158号を3㎞位上って乗鞍スカイラインに向かう左の脇道に入り、その後、8~10%超えの勾配の坂区間を4㎞位上ってやっと平湯峠ゲートになります。 自分はレースの試走でなければ平湯峠スタート…
------------------
畳平の気象状況等は
≪乗鞍岳、乗鞍スカイライン公式サイト≫ https://norikuradake.jp/
や
≪てんきとくらす[天気と生活情報]≫ https://tenkura.n-kishou.co.jp/tk/index.html から『行楽地の天気』→『エリアを選択』→『東海』→『高原・山』→『岐阜県の中の『乗鞍畳平』』
等を参考にしてます。
------------------
平湯峠駐車場に車を停めて走行準備。
服装は冬装備で。晴れていて風はほぼ無風に近いが体冷やして風邪ひくのは勘弁。絶対に回避。
上は薄めの防寒長袖インナーに裏起毛の冬ジャージ。グローブは薄めの指切りの上に春秋用のフルフィンガーを重ね、暑い時には指切りにする。
下はロングのインナータイツに冬用の裏起毛のロングビブ。
シューズは冬用のシマノSH-MW81に薄いソックスと防水ソックスを重ね履き。
心拍数上げてのガチ走行ではなく写真撮りながら、休憩しながら行く予定なので、ハーハー、ゼーゼーの呼吸では上らないつもりなので暑めな装備。
下山用としてインナーキャップ、ネックウォーマー、ウインドブレーカー、防風パンツ、冬用グローブをバックパックに入れていく。
------------------
7:30頃出発ー
ゲートに向かうと門番の係の人が居て、いつもの入山チェック。
『どこから来ました?』『上るの何回目?』等を答えて
『昨日はあられが降ってたけど、今日は路面はほぼ乾いてて、凍結個所も無しです』と。
『熊はー』
『居ますよー。っていうか、向こうの斜面に今居るよ』
『は???』
ゲートの向こうの斜面、直線で400m位は離れてて見えづらいけど、確かに黒いの動いてる!

(これでも)最大望遠撮影
『スカイラインでの目撃報告は今年はまだないけど、気を付けてね』と。。。
(そりゃー、まだ開通して3日目だしな…)
------------------
気を引き締めて、藪の中のガサガサ音に最大限注意して走行ー。
路面は除雪が完璧にされていて、路面に雪は無し。(路肩には大量ー)昨日の雨の影響で日陰になっている所は湿っているが、雪解け水が流れてる事も無く、日当たりの良い所はドライ路面。
風もほぼ無風に近い感じで、上ってる時に風が吹いてくれると涼しい位。無風状態だとウェアに日が当たって暑い位。
ドライ路面は大体こんな(夫婦松駐車場入り口から撮影)
日陰ではこんな。水溜まりとかは無く、ちょっと湿ってる位
最初のチェックポイント夫婦松展望駐車場。
ここでは自転車にまたがったままで写真撮影して通過。
次のチェックポイント、望岳台
時間は7:56分で気温はサイコン表示で14℃(多分3~5℃位実温度より高い表示をしてると思う)
望岳台辺りからちょっとの間は斜度が緩かったり若干の下りも有ったりで気が抜ける。
------------------
しばらくすると右側の視界が開けてくる。
今日は目の前に雲が多いけど、水平線でも地平線でもない(何て言うの?)雲海線?の『地の果て』感が良いんだな。コレが
ぼちぼち森林限界線
森林限界の境目辺りで一枚。
------------------
雪の壁のスポット、四ッ岳S字カーブに到着。気温はサイコンで11℃(実温度は多分ひとケタ)
真ん中に自転車を置いてるけど分からん
雲が多いので暗い…(一番上のタイトル見出し用の写真は日が出てくるまで待ってた)
上から見てみるとこんな
四ッ岳S字カーブのちょっと上にも長い壁がある。丁度バスが下って来たので高さ比較。雪の高さは大体バスの2倍くらいか
まだ朝早めだったので他の自転車の人が居ないのと、15分おき位にバスが通るくらいで他に人がおらず風も強くないので静か…
------------------
雪の壁エリアを過ぎて少し上ると桔梗ヶ原。直線的なチョイ下りに。
去年ココで雷鳥を目撃してるので、今回はしばらく止まって雷鳥を探すが…いない…寒いから動いてないのか?
下り基調の終わりにガンっと上る壁みたいな(感じの)坂があるけど、コイツを超えてしまえばあとは緩くチョット上ってゴールに。
長野側のエコーラインとの合流地点でゴール。
------------------
やっぱり長野側にはいきません。7月には来るから。(歩いて長野、岐阜の県境のゲートまでいけます)
畳平入り口の積雪
鶴ヶ池
------------------
畳平で休憩―――。写真撮りながら、休憩(ボケーっと)しながらだったので疲れはしないが、寒い。サイクルスタンドに自転車を停めたら速攻で汗拭いて防寒着を着る。
時間的には休憩込みで丁度2時間位の走行。
------------------
休憩してるとかなり雲が多くなってきたので(午後から天気が悪くなる予報だった)下山に。森林限界線までチョコチョコ止まって雷鳥を探すが残念ながら居ない…結構ガスって視界が悪くなってきた…
下ってると5分おき位に自転車の人が上って来る来る。(ゲートの係の人に聞いたら開通初日の15日は午前中だけで50人位自転車が居たそうな)
また、電動アシスト車(スポーツタイプの)で走るツアーをやっているようで、車で畳平まで送迎して、雪の壁辺りまでレンタル自転車で下るみたいな事をやってるような?
------------------
無事下山し帰宅。やっと冬物衣類が片付け出来るぜ…
これでヒルクライムレースモードに切り替えて、まず栂池…って、まだ参加証というか封筒が来てないな…
タグ :乗鞍スカイライン