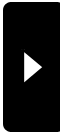さて、さて、さて、今朝は今にも降ってきそうな曇り空だったけれども、『軽めのスラローム練習を…』と思い、シクロクロス車のTCXでウエットコンディションのダート練へ。
------------------
練習場所は水溜まりが残っていたけど、8の字スラローム練習でグルグル周回を。
流石にここまで重馬場なのも久々だったので、小回りの回転走行だとハンドルを切ってもタイヤが泥の轍にハマってしまい回れない。。。
ハンドルをフルロックに近い状態に切りながらバランス取ってペダルを踏まないと回れない。尚且つつま先がフロントタイヤにあたらないようにしないとコケる。意外と難しい…
スピードは出さなくてもいいですが、舗装路でロードバイクだとしても惰性でペダリングせず小回り、じゃなくて、フルロックに近い状態でペダリングしながら回るって意外と難しいっすよ?
腕に力が入り過ぎると小回りできないし(もしくはハンドル切り過ぎてコケる)、サドル高が極端に合ってなかったり、体幹で上体を支えられず上体がふらつくと間違いなくコケます。
------------------
1時間位やってたら雨が強く降ってきたのでここで終了ー。
こんな天気ならではの練習が出来て良かったが。
------------------
で、別車のマウンテンの方。
先週、白馬岩岳MTBパークで走行したけれども走行後、Rブレーキレバーのストロークが大きくなってきたのが気になった。オイルも減ってたが、『そろそろブレーキパッドが…』と思い、外してみたが…
結構パッド残量が少なくギリギリの所だった。もうチョイでサポートプレート(正式名称不明。パッド押さえの板バネのヤツ)に当たりそう。。。
------------------
パッドはB01Sのレジンで¥1,000もしないで購入できるので交換。
シマノの純正ブレーキパッドもいつの間にか品番(価格も)が変わっていたりするので、パッドを買い替える際には今付いているパッドの品番と、ブレーキキャリパーの型番も一応、控えときましょう。
パッドの裏の品番と材質 『B01S RESIN』
ブレーキキャリパーの品番はモデルによって場所が違うかもしれないけど、ウチの油圧のだとシャーペンで指してるフレームとボルトで固定する台座の部分
拡大(キャップボルトの緩み止めの黒いプラのが有って見づらいけど)・・・『BR-M315』が型番。
気付くのが遅れるとパッドのベースプレートの金属の板でブレーキローターを削るまでいっちゃいますからね(多分その状態だともの凄い悲鳴のような金属音がしてきてブレーキ効かなくなってると思うけど)
昨日、今日と連日北信で暗いニュースが立て続けにあり、なんだかね…
------------------
さて、さて、さて、今朝は走る時間があったので雨上がりのダート練を。
練習が終わって帰り道を走っていたが、かなりな泥まみれになったので、チェーンがギチギチ鳴ってるような状態。。。
『いつもの年に比べて暖冬で雪も少なく、走る回数が多かったし、やってなかったからシクロ車体も一旦バラしてメンテするか…』ということに。
------------------
ロードの方は例年のこの時期ならヒルクライムレース本番前にクランク外してグリスアップしたり、ブレーキパッドとホイールを本番用にして慣らしみたいなのをやってるんだけど、今年はC19の為レースが無いのでホイールの慣らしはやらないが、クランク外してクリーニング、ブレーキ本体もクリーニングってのを先日(写真撮ってないので記事にしてない)やった。
------------------
シクロクロスの方は『2020-2021シーズン向けに部品換えて~』ってのはまだやらないけど、部品交換無しのクリーニングで済ますことにした。
------------------
作業前
中間
ヘッド、BB、ペダル等は取り外してバラして洗浄後、グリス入れたりしたけど、手がグリスまみれになってるので途中の写真は無し…
チェーンは外して洗浄液に漬けとく(走行後、毎回水洗いして注油してはいるが、洗浄液が汚れる汚れる…)
シートポストを外すと…めっちゃ砂だらけ!
シートポストがズレるのが嫌なんで外したことが無かったが、コレは酷い。。。フレーム内部(シートチューブ)も
フレーム内部を水洗いすることに。試験管用ブラシでシートチューブ内部の汚れを落とす。
どうにか汚れは取れたな…
洗い終わったら、エアガンでフレーム内部を吹きまくり、向きも変えたりしてフレーム各部の水抜き穴(というか溶接時の熱抜き穴)から内部の水抜き。
------------------
フレームを拭きながら見たが、Rブレーキの台座のところ(写真映り悪い。。。)

やっぱりフレームが削れてる。

BB後ろ、チェーンステイ部もスレキズが有る。やっぱり泥走行では擦れる

※シクロクロス車に限らず定期的にディレイラーハンガーを固定してるボルトは緩んでないか確認しましょう(車種により固定方法は様々です)

------------------
シートポストも綺麗になった。(シートポストはカットせずに使ってる)
(組付け時に防水、防砂加工を施したんで、もうシートチューブには水、砂は入らないと思う。)
------------------
洗浄液に漬けといたチェーンを出してみたが、チェーンの伸びを見るチェーンチェッカー(シマノのTL-CN42)に当てると、どこで当てても抵抗なく入ってしまいNG値に…
寿命か…って事で昨シーズンの本番用のチェーン(CN-HG701)を練習用に回す。
さすがにこっちはあまり使ってないのでチェッカーは入らない。
------------------
各部組み直し終了ー。
次は4ヵ月位したら換えるパーツは換えるでよ。もうチョイがんばって。
さて、さて、さて、自転車に乗ることが出来るようになったところで、『今日、乗れれば乗ろうか』とロードのタイヤを触ったらグニャっとペコリーヌ。。。空気抜けてら…
『…これは明らかパンクしてんな…いつやったんだべ?』
------------------
ってことで、パンク修理(今回はチューブ交換)をまたネタに書きます。。。
------------------
まずバルブの位置をタイヤにマーキング
マーキングするにはいわゆる『白ペン』的なのを使ってます。
で、タイヤを外す前に何か刺さってないか目視で探す。今回は細かなガラスが2ヵ所タイヤに刺さってたのでそこにもマーキング
タイヤをタイヤレバーで外すけど、下の写真の状態からタイヤレバーを横に滑らせるようにして素早く外すことも出来るけど、ロードで高圧にエアを入れてる場合はチューブがタイヤに張り付いてレバーが引っ掛かる時が有るのでその時はチューブにキズが付く可能性が有るので滑らせずに少しづつ外す方が安全。
------------------
チューブを取り出したら回転方向の矢印を書いておく。(自分は組付け時に書いてるけど)

水を入れたタライやバケツに少し空気を入れて膨らませたチューブを入れ、穴の個所を確認。
盛大に穴が開いてーら…(シューシュー音がしてたが…)
穴が1ヵ所とは限らないので必ずタイヤ1周水に入れて確認しましょう
今回はとりあえず穴は外側に1ヵ所だった。穴の所にもマーキング。いつも自分は穴の位置を中心にして十字みたいに書いてる。※リム打ちパンクの場合は開いている穴のすぐ横にもう一つ穴が開いていたり、開きかけていてチューブにキズが付いている場合があるので見逃さずに!(リム打ちだと内側(リムの方)か横に穴が開いてる)
------------------
マーキングしたチューブを再度タイヤに合わせる
すると、さっきタイヤにガラスが刺さってたところと位置が合う。

タイヤに穴が有る所とチューブの穴の場所が一致する
異物を取り除いてタイヤの内側も1周異常が無いか確認。ガラスの破片など残っている場合があるので指先をケガしないように!
------------------
今回はパンク修理せずにチューブ交換することに。
ロードバイクでパンクって2年ぶり位かも。少なくてもこのリアホイールを組んだのが(過去記事を見ると)2018年の10月アタマ頃なので、それ以後タイヤは交換したけど、チューブは換えた記憶が無い。
逆にチューブレスにする前のシクロクロス車の方は何回パンクしたか多すぎて覚えていない…
------------------
チューブ交換ついでにリムフラップを交換することに。前のホイールからなので正直、何年使っているか分からないリムフラップ。エア圧でニップルホールの所が凹んでる。
あまりに凹みが深くなりすぎたり、ニップルホール部にバリがあったりするとこの部分が原因でパンクすることが有ります。
新品に交換。
------------------
推奨することではないけど、タイヤに開いた穴は瞬間接着剤で補修。ちょこっと塗って乾燥させる。中の糸が見えてるくらい大きな亀裂の時はやると危険。
一応、タイヤを折り曲げても割れてはこない
------------------
タイヤとチューブをリムにはめていく。チューブにはほんの少しエアを入れた状態で嵌めるとチューブがねじれたり折れ曲がったりしにくくなる。が、エアを入れ過ぎるとタイヤが嵌めにくくなるので…
新品のチューブにはさっきも書いたけど、組込時に回転方向の矢印を書いておく。(コレを組込時からやっておくと出先でチューブ交換する時にどちら向きでチューブが入っていたか間違えなくて済むので。)
嵌めていって残り僅かなところで嵌め辛くなるけど、タイヤレバーは可能な限り使わずに、親指でめくり上げるように嵌める。。。
------------------
タイヤ、チューブをセットしたらバルブナットはまだ取り付けず、一度バルブを中に押し込む。コレをやることでバルブ口でチューブが噛みこむのをまず防止できます。最初にバルブナットを取り付けるとバルブ付近でのチューブ噛み込みの原因になります。
タイヤをつまんでリムとの隙間にチューブがはみ出てないか左右2周確認。
写真撮りながら片手でやってるんで分かりにくいけど…
悪い例としてもの凄くワザとチューブはみ出さしてますが、隙間からチューブが見えるこの状態でポンプでエアを入れるといわゆる『噛みこみバースト』が発生します。

チューブの噛み込みが無かったら、まだバルブナットを取り付けずにポンプで1アクション軽くエアを入れます。そしたらもう一度、噛み込んでないか(特にバルブ口付近)確認すれば確実です。※中古チューブだと若干チューブが伸びて長くなってたりするので、エアを入れるとはみ出てくる時が有るために再度見ます
噛み込みが無ければ目標エア圧の半分位まで入れます。そしたらリムラインが左右全周出ているか確認します。出ていない個所が有るとホイールを回転させるとうねるはずです。また、タイヤが一部分だけ膨らんでたりする時はチューブがタイヤ内部で折れ曲がっているか、噛み込んでいます。
リムラインが出てたら目標エア圧まで補充します。そしてここでバルブナットをバルブキャップと共に締めます。(バルブナットは一番最後で良いんです。)
------------------
7気圧入れた状態の瞬間接着剤で補修したところ。穴は塞がってます。

------------------
ホイール外したついでにスプロケも軽く拭き取り。
前
後 あんまり綺麗になってないな
------------------
今回はチューブ交換したけれど、パンク修理のも以前書いてるのでそっちも参考にしてみて下さい。
パッチ貼るパンク修理のポイントはなんせ『しっかり削る事と直ぐにパッチを貼らない事』です
下の画像か青文字クリックで過去記事に飛びます。
------------------
追記
『エアが抜けてる』って事でチューブを取り出して水に入れてもパンク穴が無い、だけど少しずつやっぱり抜ける。という時にはフレンチ、米式バルブの場合、『バルブコアからのエア漏れ』の可能性が有ります。
バルブコアからのエア漏れの場合はただチューブを少し膨らませただけの低圧状態ではエア漏れせず、高圧の時に少しずつ漏れる事が有ります。
この場合のエア漏れの確認方法はリムにタイヤ、チューブが嵌っている状態で、いつも入れてる規定エア圧の時にフレンチバルブならバルブコアの先端のネジ部を締めた状態で適当なキャップ(フタ)みたいなのに水を入れ、バルブ先端を水に漬けると確認できます。漏れている場合は交換可能なバルブコアの時ならネジ部からわずかずつエアが漏れてきます。
自分が使ってるのはコンタクト洗浄液に付いてくる洗浄ケースで確認してる。ペットボトルのフタでも確認出来ないことも無い。
バルブコアの増し締めでエア漏れが止まる事もあるけど、シールがヘタってきてエア漏れの時はバルブコアの交換を。(バルブコアが交換できないチューブの場合はチューブ交換)
------------------
『桜 写日記 5/22 No. 11 最終回』
さすがにもう桜は終わり
さすがにもう桜は終わり
上ってる時は暑いが、下ってる時の風は涼しいね~
さて、さて、さて、今朝は走る時間があるにはあったが、天気の方が微妙ー。
それでも1時間位なら降らなそうなので『桜の写日記』撮って、山を1本回ってくるルートで練習に。
国道403号の聖の上り口から。山の上の方は白いんですが…
聖方向には行かず、途中で右折する県道390号の方には雲はかかってきてなかった。
------------------
桜 写日記 4/5 No. 2
一昨日、昨日と日中の気温が高めだったためか開花が進んだ気がする
一昨日、昨日と日中の気温が高めだったためか開花が進んだ気がする
------------------
先日、在った通行止めの看板は無くなっていた。なんとなくで通行止めの理由は想像がついたが。。。
踏切を渡って上りスタート。ゆっくり上ってて雨に降られるのも嫌なんで、踏んでく、で。
頂上近くは昨晩の雨のためハーフウエット路面に。
途中の細い道の所に伐採された木が大量に在った。(画像無し)
ふもとの通行止めの看板の理由はやはりコレ、『着雪のため倒木で通行止めだった』と思われる。(撤去作業ありがとうございます)
回って下ってくると路面もドライに。なんとか雨には降られず終了ー。
------------------
帰宅して車体の方を見ると、ウエット走行気味になったので、砂、水の汚れが…
ササっと汚れ落としの清掃を。
〇車体の方は柔らかめのタオルにクリーナーをつけて軽く拭き取りで。
〇ブレーキやスプロケ、チェーンのメカ系なんかはタオル生地よりTシャツ生地の方が作業しやすかったりします。
タオル生地だと厚みが有って狭い所はやりづらい時もありますが…(例えばブレーキの隙間とか)
Tシャツ生地だと薄目で伸縮性があるので狭い所もやりやすい
取れてる汚れがお分かりいただけるだろうか(ほん呪風に)
汚れを落としたら、可動部分にチョチョッと注油を。
Rブレーキも 清掃前
清掃後
スプロケにもTシャツ生地のウエスで引っ張ってゴシゴシすれば生地が引っかかりにくく、ギアとギアの隙間の汚れも取りやすい。
作業前
作業後(フラッシュ焚いたら逆に暗めになってよく分かんね)
汚れが溜まりやすいBB裏もRホイール外してササっと拭き取り終了
チェーンオイルと砂などの汚れが混ざってこびりついたままにしてると落としづらくなるので、こまめにやってると楽に汚れが落とせます。
------------------
専用のウエスもあったりしますが、古タオルと綿の古Tシャツ生地で十分なので、古着を使ってみては?
家族に古着をとっとくように頼んだり、自分の場合だと 仕事時の制服=普段着=作業服なのでTシャツ生地には困らない。。。
作業用のイス(オイル缶)
の、中身はウエスが大量。。。
さて、さて、さて、『最後に一回滑りに行けるか?』と考えていたが、どうにも都合がつかないので物足らない感がもの凄くあるが、ウインターシーズン、スノースクートはこれで終了、夏眠させることに…
------------------
※バラす前の写真を撮って無かったので1、2枚目の写真は去年の物を再利用。。。
フレームからボードを外していく…
ボードのポジションセッティングのため埋め込みナットが3ヶ所ずつ有るが、今シーズンINの時に使わないナット穴はグリスを入れたうえであらかじめ塞いでおいたので
ナットネジ山等にサビは無し。
保管する際にもグリスを詰めて塞いで保管する。
------------------
(ボードの)エッジは、まだ大丈夫?錆は無いよ。
------------------
ステム、ヘッド周りをバラす。リテーナーにもレースにも錆、打痕は無し。(水が入りやすい箇所なので、ちょこちょこグリスアップはしてた)
あとは去年と同様の作業をして(去年の記事)夏眠に。 おつ様ー。
------------------
そして自転車メインに移行。ヒルクライムレースも出れるレースは出るつもりでいるし、シクロクロスもスーパークロス野辺山には当然、今年も出るつもりでいます。
あの場所のあのコースで、あのどこでもカウベルの音が聞こえるお祭り騒ぎのノリの中を走りたいんっす。
『風評被害が~』のボスのコメントはキツイ…
タグ :スノースクート
先週は『警報級な大雪になるかも』と天気予報で言ってたがそうはならず、それどころか気温高めで雨が降ったりしてスキー場の下の方のゲレンデは雪解けが凄く、地面が見えまくってた。
『これは暫く滑れないかも…』と心配したが、戸狩とかは連日降雪になり一気に積雪量がアップ!良かった良かった…(また気温上がって溶けなきゃいいが)
------------------
県境の方は徐々にではあるけど積雪も増えてきているが、市街地は雪は無いのでこっちの車体も例年より早くOHして走行準備に。
ハンドルは交換するけど他の部分はパーツ交換無しの予定なので各部外して清掃とかして摩耗、破損が無ければ再組付け。
ってか、去年(2019年)のロードは練習抜きでレースで走った距離っていうと栂池サイクルクラシックの17.1㎞と雨天で短縮になったツール・ド・美ヶ原の4.7㎞の合計距離21.8㎞しか本番は走ってない。練習もマウンテンの走行距離が増えたり(別にマウンテンのレース出た訳じゃないが)、8月に骨折して入院後はほとんどロードは距離乗れずにシクロクロスのシーズンINした為、ロードの走行距離自体は例年に比べ少なかった。
------------------
シフトレバーを外してワイヤー類を外す。インナーワイヤーは日泉ケーブルのSP31を使っていたがワイヤーのタイコの近くの所、シフトレバーの中で90度曲がるワイヤーにとって負担がかかる所でもそんなにワイヤーの曲がりが無いように思える。(写真はシフト操作が多い右レバー)普通のステンシフトワイヤーは交換の時はもっと曲がりグセが付いてた気がする。
インナーワイヤーは使えそうなんで、ハンドル交換するとシフトワイヤーの長さが足りなくはなるが、今まで使ってた後ろ用のワイヤーを前用にして再利用で。(ブレーキワイヤーも)
------------------
去年はアウターワイヤーは黒だったけど、今年は赤(ニッセンのアウターではなく別の余ってたのが有った)で。
去年
今年
ブレーキ、シフトとも機械式な為、ケーブルを2本ともハンドルに内装すると取り回しが厳しいのでブレーキは内装、シフトは外通しで。あとは油圧の時と同じ感じで組立。
ブレーキ、シフトとも機械式な為、ケーブルを2本ともハンドルに内装すると取り回しが厳しいのでブレーキは内装、シフトは外通しで。あとは油圧の時と同じ感じで組立。
------------------
…それでも今週辺りから『今シーズン一番の寒波』が来るとか天気予報で言ってんのね…降るのはスキー場で…
------------------
グラインデューロの2020年大会が
信越エリアにて5月23日(土)に開催決定。
信越エリアにて5月23日(土)に開催決定。
年間6戦のGRINDURO 世界シリーズ戦の開幕戦が日本だそうです。
エントリー、コース等詳細はまだこれからみたいだけど、コースは去年走る予定だったコース(台風で距離短縮になった)をリベンジすれば良いんじゃないの?なんて。。。
シリーズチャンピオンもあるらしいですが、そんな世界中を転戦するような豪華な生活してみたいもんだ…
さて、さて、さて、相変らず『朝は寒く、昼は気温が上がる。曇ってても降りそうであまり降らない』って天気が続いてるけど、乗れるときはロードに乗って茶臼山を上り、霜が降りてそうな時は河川敷へシクロクロスでって感じで走行してた。
それでもそろそろ『雪山の準備をねー』って事でスノースクートを夏眠から覚ますことに。
------------------
倉庫の奥から引っ張り出してきて…
ヘッドセットパーツやネジ部なんかにはグリスを塗って袋に入れたりして保管してたのでサビは無し
チョイチョイっと防水、防錆加工とかを施して組み立て終わり。(板にワックス塗ってるので逆さまだけど)
------------------
スノースクートの準備はしたが、スキー場の積雪がどうにも少なく、長野県全体で見てもオープンしてる所は少ないよう…もうチョイの辛抱か。
------------------
それと一応、来月の1/13で希望休のお願いを出しといたんで、休みになれば『シクロクロスミーティング 第8戦 清里 丘の公園ラウンド』に出る予定。
タグ :スノースクート
さて、さて、さて、2019 Rapha Super Cross NOBEYAMA(スーパークロス 野辺山)まであと2週間…と思ったけど、野辺山は土曜日レース開催だったのでもう実際10日ほどしかない。
------------------
11/10のシクロクロスミーティング 飯山ラウンドから帰ってきた後に洗車をしてたらタイヤサイドがおそらく固まった泥で擦れてきていて薄くなってきているのでタイヤ交換をすることに。
ドライバーで指してる所が擦れてきてる。
チューブレスタイヤ(シラク CX クロスガード).なので内側にゴム層も有って漏れないとは思うけど、センター部のヤマも減ってきてるし、「今シーズン中には換えなきゃな」とは考えていたので今回で交換することに。
同じような感じで擦れてる練習用のタイヤ(非チューブレスだけどチューブレスで使えるらしい)の方はここからエア漏れするためチューブレスとして使うことが出来ず、練習+試走用としてチューブ入りで使ってた。
------------------
飯山の試走では雨上がりの路面状況というのも有って練習用のチューブ入りタイヤだとエア圧が高く、土手(キャンバー)部や泥区間ではどうにもグリップしなかった。かといってエア圧を落とすと木の根っこなどでリム打ち(パンク)する可能性が高くなるためエア圧を落とせなかった。
しかし、試走用でもある程度は本番用に近くないとコース状況が分からないので、試走用のホイール(タイヤ)もチューブレスにすることにした。
------------------
練習用のホイールは完全チューブレスホイールのニップルホールレス(シマノ XT WH-M785 29er)ホイールなので(コンプレッサーを使うため) 楽にビードは上がる。
(今まではタイヤが非チューブレスのためチューブ入りで使ってたけど)
チューブレスバルブに交換。(エア漏れ予防としてシリコンシーラントを塗っとく)
また、本番用のホイールは前輪はオフセット無しのリムのため、チューブレステープは交換無しでビードは楽に上がり、タイヤ交換終わり。
------------------
やっかいなのはオフセットリムの場合のチューブレスのタイヤ交換。
オフセットリムだとニップルホールもセンターに無いため一度使ったチューブレステープだとニップルホールの所がエア圧で丸くへこんでしまいここからエア漏れするためコンプレッサーを使ってもビード上げが上手くいかない。(テープは1周巻きでバルブ部だけ重ねてる。)

へこんでる所がタイヤと密着しない為ここからシューシューエアが漏れてビードが「パン!!」と上がらない

------------------
「テープ交換無しでなんとか上げられないもんかなー?」と考えた末、上げられる方法があったので一応、紹介を。
※この方法自体はバイクでのタイヤ交換でビードが上がらない時の手段としての方法の応用です。自転車のタイヤ、ホイールはバイクの太く丈夫なタイヤ、ホイールとは違うのでリムや、スポークの変形、エア圧での工具の外れによる破損、怪我の可能性があります。決して良い方法としては推奨しませんので。
コンプレッサーを使ってエアを入れる、というのが前提になるけど、用意するのはウエス2枚(ある程度厚みが有る方が良いのでタオル)と荷積み用のベルト(ホームセンターに売ってる)。(ラチェット式の方が楽なので。バイクでの昔から紹介方法だとトランポに車載する時のラッシングベルトを使う。となっているかも)
タイヤをリムにはめたらラチェット部が(バルブ部を破損させない為)バルブ部の反対側になるようにラチェット部を合わせタイヤにベルトを巻く。 ※ヒモ状の物を巻くよりベルト状の幅がある方がタイヤを押さえやすくエア漏れしにくいかと思う。
ベルトのラチェット部、フック部はタイヤやリムへの傷つきを防ぐためタオルを敷いておく。(※作業中の写真はすでにエアを入れ終わったヤツとか使ってたりしてます)
ようはベルトを使ってタイヤを締め、タイヤとリムの密着度を上げる訳ですが、注意点が2つ。
〇1つ目はベルトはタイヤの中心に沿って押し付ける事。この後コンプレッサーでエアを入れるのですが、センターからズレてるとエアを入れてる最中にベルトが外れます。
〇2つ目はラチェット式のベルトな為、カチカチ締めてるとかなりキツくまで締まります。しかし締めすぎるとエアを入れた時にエア圧の逃げ場が無くなる為やはりベルトが外れやすくなるし、リムやスポークの変形の原因になります。
軽くタイヤに密着する程度でエアを入れてみて締め付け具合を調整します。
------------------
今回は一度では上がらなかったけど、ビードに指で水を塗って再度やったらあっさり上がりました。
※エアを入れる時はラチェット部が外れても大丈夫なように段ボールとかで覆って作業しましょう。また、エアを補充してる手から遠くなる(怪我する率が下がる)ためにバルブの対局にラチェット部を持ってきています。
シクロクロスの700c×32Cタイヤとダウンヒル用の27.5×2.3のタイヤはこの方法でビードを上げてます。ロードのカーボンホイールとかだとリスク高いかも。((チューブレスの)カーボンホイールとか持ってないのでやったことが無い)
------------------
今朝は暖かかったが、午後から急に気温が下がるようで、長野県でも標高1000m以上の所だと氷点下になるかもって天気予報で言ってるし…
ウェザーニュースの週間予報だと野辺山は11/21日は予想最低気温はマイナス6℃で最高気温は4℃になってんぜ…(というか明日から最低気温はずっとマイナスになってるし)
スタッドレス履いてこ…
台風19号の災害から今日で1ヵ月。自分は早く過ぎたと思う。
しかし、台風の前の状況に戻ってるのはほんのわずかだとも思う。
しかし、台風の前の状況に戻ってるのはほんのわずかだとも思う。
------------------
11/10のシクロクロスミーティング飯山ラウンドは転倒してメカトラが発生して11速シフトが8速になってしまったものの、とりあえず完走したという最悪のリタイヤよりマシ、という結果。(それも最下位ではなかったよう)
落車での怪我の方は腕は上がるし、物を持ち上げることも出来るし、クシャミをしても痛くはない。が、サイクルジャージのバックポケットに手を入れる姿勢だと痛い。あと擦過傷が数ヵ所。
------------------
泥や芝の所でコケたのではなく、少し速度が出てるアスファルト上でコケたので車体の方は破損部品がある。ぱっと見で右バーテープとRディレイラーの2ヵ所は部品交換が必要。
------------------
右バーテープ。下部分がざっくり切れてる
(作業自体はレースから帰ってきた日曜日にやったことだけれども)家に帰って『とりあえず洗車して、その後ディレイラーハンガーの交換だけで直るかは早めに確認しとかんと』に。Rディレイラー交換なら¥9,000位はするよなぁ…(RD‐R8000‐GS)
------------------
まず洗車。今回の泥は乾燥するとカチカチに固まってしまい、ちょっと水圧がある位のガーデニング用のホースノズルで水を掛けただけでは泥が落ちない。
タイヤサイドなんかは水をかけてちょっと時間をおいてブラシ掛け。タイヤの泥に水をしみ込ませてる間に『ペダルの泥を落とそう』と思ったのだけれど…
スキマに泥が入り込んで固まってしまい、ハンバーグと化したSPDペダル。レース中もキャッチしづらくなっていてシューズの裏でガチガチ踏んで泥を落としてた。
表面の泥を落としても長い芝草が鉄筋コンクリートの鉄筋の如く絡んでる…
(ハンバーグ食べ終わったらキャベツの千切りが出てきたみたいな?)
なんとか落ちた。。。
------------------
いつもよりかなり時間がかかって洗車終わり。交換前のRディレイラーハンガーの状態。これでもレース中に手で外側に曲げたんだけれども。。。
外したディレイラーハンガーと新品の。昨日の画像と同じ物。
※街乗りスポーツ自転車も右側に風やなんかで立ちゴケした位でもディレイラーハンガーは曲がってしまう場合があります。曲がっていることに気付かずMaxローギアに入れてペダルを踏んでしまうとチェーンが内側に落ちやすくなり、チェーンがスプロケとスポークの間に噛みこんでしまい後輪がロックして回らなくなり、変速機がもげて変速機交換、最悪フレーム即死(ディレイラーハンガーだけでなくフレーム自体が破損)する場合があります。
『便利だから』と車重の軽いスポーツ車に安易にサイドスタンドを取り付けると強風などで立ちゴケしやすくなるので、Rディレイラー(というか自転車自体)の破損に繋がります。
サイドスタンドより壁などに静かに立て掛けた方が良いと思う。(ただしサドルの横が擦れやすくなったりするが…)
ディレイラーハンガーの交換で直って一安心。リヤは修理完了ー
------------------
右のバーテープを剥がすとバー自体のアルミも削れてる…バーテープも予備を持ってたので削れた部分をサンドペーパーで均して…
つや消しのタッチペンで塗って(塗らなくてもバーテープ巻けば見えないんだけれども)
バーテープ巻いて終わり
------------------
直しついでにFフォークも外してベアリングの清掃、クランクも外して清掃までやって復活。
------------------
風呂のお湯が擦り傷に染みらぁーね。。。(一日経ったら傷口は乾いてかさぶたになってるけど)
------------------
タイヤを洗ってたらタイヤサイドがちょっとヤバそうなのに気付いたんで、次回はタイヤ交換(オフセットリムでのチューブレステープの交換無しでチューブレスタイヤのビードを上げる方法)とかを書こうかと。
さて、さて、さて、10月も最終週に入り11/9、10に連日開催となるシクロクロスミーティング第3のナイトレース、4戦のデーレースの飯山ラウンドまで2週間を切った。
レース出場は2日連続出場は色々と厳しいため出場するのは11/10(日)のデーレースのみ。
------------------
シクロクロスレースは一昨年から始めたけど、2017年の飯山ラウンドが初出場、初レースだった。しかし30分のレース、コース3周を完走出来ずDNF(リタイヤ)。
その時のはこっち ↓ でも見てもらって
2017/11/12
今年はどうなる事やら…というよりまずレースを開催してくれることがまず嬉しい。(台風19号の被害が飯山市内でもあるため)
・・・なのだけれど、AJOCC(日本シクロクロス競技主催者協会)の公式HPの最新情報(10/29)を見たら…
https://www.cyclocross.jp/news/2019/10/3.html
------------------
昨日(10/28)シクロクロスの練習に千曲川近隣に行ったが、台風19号通過後初めて以前練習していた河川敷の方へ行った。
…が、自転車に乗っては練習場所に行けなかった。
あぜ道は倒木で寸断。歩いて行くことに
スラローム練習をしていた広い所は台風19号が来る直前位に撮ったのがコレ
上の画像とほぼ同じ向きで撮ったが、10/28では泥が被っていてまだ水が引かない。元の地面が完全に泥で埋まっていて草が見えない
下の2枚の赤丸の木は同じ物

乾いて砂になってきてはいたけど、30㎝~は被っている

あぜ道があったはずなんだけど、流されてきた稲わらや木で道が埋まってる…
今回の増水は今までのと比較にならない。地形が完全に変わってる…
------------------
その後戻って土手の空いてる所でスラローム練をやって、家に帰ってから本番前のメンテを。
本番用のチェーン、スプロケを換えるのでついでにチェーンリングもストックしといたRACEFACEのナローワイド(38T)に交換することに。
左側が古いチェーンリング、右側が新品(RACEFACEの方が元々歯厚が有るよう)
BBも外して洗浄。その後グリス詰め。グリスを詰めるのにグリスガンとグリスパッカーを使って詰めてる。使ってるグリスは普通の(確か)シャーシグリス。
普通にそのままグリスパッカーを使うとかなり無駄にグリスを出してしまうためベアリング内径に合わせて適当なスペーサー(分かりづらいけど、画像だと手前のグリスまみれになってる黒い筒みたいなの)を入れてグリスを節約。。。
手で刷り込むよりはやっぱり楽で確実。
余分なグリスを拭き取ってシールをはめてフレームに圧入して終わり
…本当は圧入BBは何度も取付、取り外しをやらない方が良い(BBシェルが擦れて寸法が変わってきて勘合が緩くなりそう)とは思うけど…
------------------
チェーンリング、スプロケ、チェーン、Rホイールを一旦本番用にして慣らしを。
スーパークロス野辺山Day2(11/24) 野辺山グラベルチャレンジはショートにエントリー。(初開催なので見てるよりやっぱり走ってみたいって事で。)