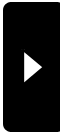さて、さて、さて、『シクロクロスを始めるなら』の5回目…えらい長くなってしまった…
車体の方でまとめにいきます。
メーカー名、モデル名も書きますが、すべてを把握してませんし、現物を見ているわけでもありません、乗ってもいません。そんなですが。
------------------
フレームサイズは別のスポーツ車を乗っている方ならある程度自分の適性フレームサイズは把握しているかと思います。フレームに関しては、『ある程度乗って走らないと分らない(感じない)』というのが正直なところだと思いますので深く考えなくてもいいかも。と酷いことを言っときます。
だって、『肉体的(手足や胴体長)には(サイズが)合うフレームでも、そのフレームが自分の乗り方にも合うかは分からない』でしょ? 全く同じジオメトリのフレームが複数のメーカーからもし出てたとしても、フレームの部分的な肉厚なり材質(アルミなら番数)、接合方式なりで必ず違いはあるはずでしょう?(OEMでロゴ、ペイント、あとはほとんど同じ…みたいなのは置いといて。
ある程度は乗る側が車体に合わせないと…とは思います。その中で『自分にはこういう乗り方も出来るのか』と発見することもあるかもしれませんね。
------------------
で、結局は『自分がやってきたことを勧める』というオチになり、エントリーな価格ではなくなってますが、『レースで使い、それで走りきれてレースでちゃんとリザルトを出せる車体構成』で考えています。
------------------
一応、なんちゃってだけどクラス優勝もありましたよ?
信州シクロクロスミーティング 2019-2020シリーズ 開幕戦 白樺湖ステージにて
戦利品も頂きました。
(この戦利品(お酒)はいつもアドバイスをしてくれる先輩自転車乗りにお供えしました)
信州シクロクロスミーティング 2019-2020シリーズ 開幕戦 白樺湖ステージにて
戦利品も頂きました。
(この戦利品(お酒)はいつもアドバイスをしてくれる先輩自転車乗りにお供えしました)
ホントのエントリーモデルで金額も安い車体も有りますが『トラブルで走りきれずリタイヤ』、『どういう風に走るか(レースをするか)を考える余裕もない』そういう車体でレースに出ても面白くないでしょう? 実際、自分のシクロクロス初出場レースは泥詰まりでホイールが回らずリタイヤですしね…なので泥トラウマは有るかもしれません…
------------------
●フレーム素材はアルミ
形状で考えると『ワイヤーは出来るだけフレーム内蔵かフルアウター化が出来、BB裏にブリッジが無く、前後φ12㎜のEスルーアクスル固定な車体』が良いかと。
だけど、走るコースが激しい泥コースでなければブリッジが有っても泥詰まりの問題は無いかもしれません。アルミフレームのエントリーモデルは各メーカーから出ていますが、形状に条件を付けるとかなり絞られてしまい、金額も高めになってしまいますが…それにシクロクロスは完成車販売が多く、フレームセット販売が少ない
●ブレーキは油圧ディスク
シクロクロスではドロップハンドルのブラケット持ち(上持ち)での走行がほとんどなのでブラケット持ちで連続フルブレーキングしてると機械式では正直、握力が無くなってきます…(ダート走行はしてませんが、TRPのHY/RDハイブリッドキャリパーを通勤仕様車で現在使っています。機械式に比べてタッチは固め、引きも軽くストロークも少ないので完全油圧には劣るけれど使えないことも無いと思う。インナーワイヤーを日泉ケーブルに換えれば尚良し)
ディスクローターはブレーキ熱によるフェード現象が発生して効かなくなるなんて事はシクロクロスレースではまず起きないので、サードパーティー製の物で冷却フィンとか無しの物でも指先1つで
正常な状態でもパッドがキュルキュル音鳴りすることもありますが、あんまり気にしない事…水場突破した後とかは大抵鳴ってますし。。。
●シフトは11速(シマノなら105以上のグレードを)
この部分(油圧ブレーキで11速)は金額がかかる所だけれど、やった方が良いと思う。
作動は機械式でも電動でも好みで。(電動だと金額がハネ上がりますが…)
●クランク、スプロケの組み合わせ(ギア比)はお好みで
フロントシングルならサードパーティー製のエントリーモデルクランクでもナローワイドチェーンリングと組み合わせれば変速トラブルは起きにくく、金額も抑えられるが(クランクの)重量的には不利。また、泥詰まり、メンテナンス性の点もフロントシングルはメリットになるけど、ワイドギアすぎると脚が疲れやすいかも… フロントシングルにするならナローワイドチェーンリングにしたとしてもチェーンデバイスは付けた方がいい。
●ハンドル、ステムはアルミで十分。
最初はおそらく散々コケますので『軽いから』でハンドルバーをカーボンにしちゃうとあっさり折れますよ?
●ホイールはアルミリムで問題無し
エントリーモデルで多く採用されているカップアンドコーン式の純正のホイールで、玉押しの所に水、砂が入ったりして乗りっぱなしノーメンテだと1年も持たずにハブ軸がガタガタになりますからね(ラジアルボールベアリングならノーメンテでOKって事でもないです)
●タイヤはチューブレスを
メーカー完成車ではチューブレスタイヤを採用しているのがほとんどになりましたが、チューブレスタイヤの取り扱い方、パンク修理、(もしもの時の)チューブ交換の知識と技術も
●ペダル、シューズはマウンテン用を
ホントに最初ならビンディングペダルじゃなくてフラットペダルで慣れるのも良いかも。(フラットペダルなら滑りにくいものを)また、泥でヌルヌルな斜面を自転車を担いで上るってのがあるのでシューズも滑りにくい物を。
------------------
こんな感じで挙げてくと・・・
完成車なら
●TREK Crockett 5 Disc ¥229,000(税抜)
●GIANT TCX SLR 2 ¥190,000(税抜)
(TCXは機械式ブレーキレバーだけれど、ステム部で油圧ブレーキに変換(CONDUCTシステム)してる。シートポストがD型断面)
※現状(2020年4月)で両車ともコンポはSRAM、フレームセット販売は無し、カラーリングは1パターンのみ
フレームセットでなら
●ブリヂストン アンカーCX6 ¥120,000(税抜)
105ベースの完成車 ¥235,000(税抜)もあるけどブレーキは機械式、フロントチェーンリングはダブル。フレームセット重量も出てるが、どの状態の重量なのか不明。(自分が乗ってるTCXより若干(0.4㎏前後)重いかも。)
●KOGA COLMARO Disc ¥169,800(税別)
2018年より新しい情報が無い?『シクロクロス』ではなく『オールロード』として出てる。関心したのは自分が『チェーンステイとタイヤサイドのクリアランスに注意』と書いたけど、COLMARO Discは擦れそうな部分に溶接を盛って厚くしてある点。驚いた。
他にも有る(ワンバイエスの#805Zとか。電動だとケーブル内臓だけど、機械式シフトだと外通し)のだけれど、情報が更新されてなかったりなので…
どうしても『BB裏にブリッジが無いフレーム』ってのがあまり無いので挙げてる車体が少なくなります…その条件を外せば他にもあるんですが…(ケーブルはとりあえずフルアウター化してタイラップ止め。がまず思いつく手段か)
------------------
もし、自分が次の車体に選ぶとしたら、(というか実際検討してる)(重量がちょっと気になる所だけれど)アンカーのフレームセットで手持ちパーツを使いバラ組するのを考えています。新型にモデルチェンジして一番自分の希望構成的なフレームになったし、カスタムカラーリングも出来るしね。
(もしかしたら全くの新規で始める時もバラ組で作ってもTREKとさほど変わらない金額でシマノの105メインで油圧ディスクでフロントシングルなら組めるかも。自分で組立、ホイールも自分で手組って条件だけど…)
------------------
また、定期的にレースに参戦するなら練習用ホイールと本番用ホイールって感じでスペアホイールを用意するか、スペアスプロケとチェーンは有った方がいいので…
そういう装備品だったり練習方法など次回以降にしようかと。
------------------
オマケ
ウサギ 写日記 4/30
今日は日中気温が高かったため、ウサギはエサを入れてるお皿が瀬戸物で冷えるからかお皿の上で休んでた。
お前さんたちにやってるエサのキャベツは今、超高級食材だからな?芯まで残さず食べるんだぞ。
さて、さて、さて、『シクロクロスを始めるなら』で、4回目。
コンポの続きでクランク、スプロケットについてで思う事なんですが…
『シマノでGRXが出たことにより凄い選択肢が増えたな』というところなんですが、ドライブ系で酷い個人的な結論を先に言ってしまうと、
『コレがいい。と言える正解は無い』です。
乗る人の脚力、体力や走るコース(土なのか、砂なのか、固い非舗装路なのか、雪なのか)や天気、気温でも状況が変わるため、『コレがいい』とは正直言いきれません。
その辺はメーカーの完成車のスペックをいくつか見てもらってもわかって頂けるかと。
(GRXが間に合わなかったためか)ロードパーツメインで組まれてる物、シマノのシクロクロスクランクで組まれてる物、GRXで組まれてる物、シマノのフロントシングルが出遅れてたからSRAMで組まれてる物…等様々です。
そもそもメーカーの方で『シクロクロス』と『グラベルロード』で分けてたり、分けてなかったりもしますし。
(※言葉遊びではないのですが、シマノのGRXシリーズの紹介(カタログ)でも『シクロクロス向け』とは書いてないようです。『グラベル・アドベンチャー向け』となっていて使っている写真もシクロクロスレースの写真は無いみたい。別で『シクロクロス』というパーツカテゴリーが有るからかもしれませんが…)
------------------
『グラベルロード』という言葉と、『グラベルレース』というのも在ります。
『グラベルレース』は日本ではまだあまりなじみがないかもしれませんが、1周~3㎞位のクローズドコース(レースコース)を周回走行するシクロクロスとは違い、一般道なども使って一日がかりでダートを走ったりする長距離レースと思ってもらえれば良いかと。欧米では流行ってるそうです。
各メーカーの車体紹介の所で『シクロクロス』と『グラベルレーサー』と分けてる場合もあります。(なんとなくだけど、『太いタイヤ履けるよ』とアピールしてるのは『グラベルレーサー』としてる感アリ)
『なぜ日本ではグラベルレースがまだ流行らないのか?』というと、これは自分の想像ですが、道路使用の許可が取りづらいためと、安全確保が難しいからかと。
『レース』なので事故の危険も在るので一般道の使用許可が取りづらく、山道を上ったりもするわけですが、個人なり、国なりが所有してるところなので、勝手にレースコースにするわけにもいきませんし、『道が荒れたり、崖下に転落したら誰が責任とんの?』ってことです…
それでも野辺山グラベルチャレンジやグラインデューロ、SDA王滝(グラベルバイククラス)等、日本でも大きな『グラベルレースイベント』が始まった感じがします。別にシクロクロスだけじゃなくて『グラベルレーサー』もやってもらって良いんですよ?
…にしてもみんな長野県でのイベントですよ。長野はホント自転車県ですな…
------------------
…脱線。
シマノパーツのバリエーションだとクランクは
●ロード用フロントダブル(53-39T~50-34T等)
●シクロクロス用フロントダブル(46-36T)
●GRX フロントダブル(48-31T)
●GRX フロントシングル(40T、42T)
スプロケはロード用11-25TからGRXではマウンテン用の11-42Tまで…
サードパーティ製の歯数まで含めたら一体、何種類の組み合わせが在るのか…(ロードコンポとGRXでチャンポン出来るかは不明。まずシマノは推奨しないな…)
------------------
まずギア段数ですが、11速(シマノだと105グレード以上)をお勧めします。理由は他の方も自分でも書いていますが、10速で始めて後々パーツを(11速に)グレードアップしようとすると互換性が無いため丸ごと交換になるためです。(とはいえ12速化が来ないとも限りませんけどね。。。)
それにブレーキは油圧をお勧めしますので、GRXなら600~、ロード用レバーならR7000~となります。ここが結構値が張る部分になりますか…
電動の方がメリットは有りますが、機械式シフトがダメということはありません。(2年連続で全日本シクロクロスを獲っている前田 公平選手はSRAMの機械式シフトだったはず)
スプロケはRディレイラーとの兼ね合いになるのでロード用SSケージのディレイラーで小さめスプロケからGSケージで34TまでかGRXで最大42Tまでの超ワイド仕様か。
------------------
自分は最初、フロントダブル50-39T、リア11-34Tの10速で始めました(それしかパーツ持ってなかった)がBB部分での泥詰まり、50Tなんてダートでは重くてとても踏めず常にインナー39T走行。フロントは外側には落ちないが、内側にチェーン落ちまくりだったのでフロントシングル仕様の後、油圧で機械式シフト11速に変更して現在に至るです。
ギア比的な話をすると、ヒルクライムレースに出てる方にならなんとなく分かってもらえるかもしれませんが、自分はヒルクライムレース用の車体ではフロントは50-34Tのコンパクトクランク、リアは11-30Tのカセットで乗っています。それでツール・ド・美ヶ原だとCP1の美鈴湖まで、乗鞍だと三本滝ゲートまでアウターのままで~20分のタイムです。
それでシクロクロスではフロント38T、リアは11-34Tの組み合わせでCCMのコースは走ってます。(野辺山含む。コースによってギア比変更はしてません)
『自分にはシクロクロス用標準のフロントシングル40Tは重すぎる』と感じ、38Tにしています。ナローワイドチェーンリングに自作でチェーンデバイスを付けています。この仕様でチェーン落ちは1シーズン中で練習も込みで1回有るか無いか位まで減っています。(少なくともレース中にチェーン落ちで止まった事は無いです。…ホイールは落ちたけどねー)
リアはRD-R8000-GS。自分が車体を組んだ時にはGRXは無く、34Tが使えるのはR8000だけだった。今は105のRD-R7000-GSもあるので34Tまでは対応できるし、11-34Tの11速カセットなら10速のフリーボディのホイールでも使えるというメリットも有る。
チェーン、スプロケのグレードについてはこっちを↓
シクロクロスレースではC4クラスの人達が降りて担いだりしてる坂の個所も自分は乗ったままクリア出来たりすることが多いです。『上れなければ自転車から降りて押すなり担ぐなりすればいい』と思うかもしれませんが、乗り降り、担ぎの繰り返しは『はっきり言って疲れます。』それで自分はストレートの最高速は捨てて低速寄りにして『自分の脚力の範囲で出来るだけ乗車で』でやってます。だけど、2019 スーパークロス野辺山 男子エリートクラスではエミル・ヘケレ選手が担ぎメインでブッチギリ独走優勝してます。(この辺が乗る人の『体力による』なトコロか?)
だからと言って『フロントシングル仕様で40Tにしてリアにデカいの(42T)入れて低速寄りにすればいいや』だと、ワイドレシオになり、チェーンのたるみも増え、焦ってシフト操作すればカセット側でのチェーン外れ率がスタビ付きとはいえ上がりますし、ディレイラーのスプリングテンションがヘタってくれば尚更です。カセットの重量もパーツ価格も上がります。
フロントダブルにすればスプロケは小さいもので済み、地上高もわずかに稼げますが、ギャップで跳ねてる最中のフロントシフト操作は即、チェーン落ちに直結します。それにBB付近での泥の付着が増えます。
それでも泥が付かないようなライン取り、丁寧な操作と踏み込みなんでしょうか?または、アウターとインナーの歯数差を小さくしてチェーンのたるみを少なくしてるからでしょうか?フロントダブルでもノントラブルの人はトラブル無しで走ってます。フロントシングルよりギア比幅が細かく広くなるから脚が疲れにくいか?
こんな感じになってしまい、『どれがいい』とは言い切れません…
------------------
あ、あとGRXクランクは太いタイヤで幅広になったフレームに対応するためチェーンラインが外側にきています。そのためQファクターも通常のロードクランクより広くなってますが、『Qファクターが広くなった分ペダル軸を短いものに換えれば帳尻が合う』と思うかもしれませんが、ペダル軸を短いものに換えると、シューズがクランクに接触しやすくなるので。
普通の状態だとシューズとクランクにスキマが有りますが…
ペダル軸が短くなるんだから当然、シューズは内側にいきますよね?(これは参考でやってるだけなのでペダルは換えてませんが…)『クランクに接触するから』と、クリート調整とかしたら本末転倒ですよ。。。
まだ続いちゃうな…
------------------
『桜 写日記 4/28 No. 9』
緑色が目立ってきた
さて、さて、さて、『シクロクロスを始めるなら…』って事で3回目、コンポについて。
…っとなるけど、以前にも『シクロクロスを始めるなら』的な事を書きましたが、(小さな画像か下の青文字クリックで過去記事に飛びます)
------------------
(10/10から複数回。今回のはそれをベースにまた書いてる)この時とは状況が変わりました。
------------------
そう、ご存知の方も多いと思いますが、シマノからグラベル用コンポーネント≪GRX≫シリーズが2019年に発売になりました。(今回の『その1』の所で、『グラベルロード』じゃなくて『ダートロード』って書いてますが、主流な呼び方は『グラベルロード』でしたね…)
しかし、自分は全くGRXについては導入していないのでメリット、デメリットは分かりません!ので、もし書く時は『・・・じゃないかなぁ…』でGRXについては書いていきます。(ってか電動(Di2)も無いよ)
それに自分は主にシマノパーツで組んでいるため、SRAMについても全く無知ですが…
(妄想が過度にあるかもしれません)
------------------
とはいえ、基本的な所はフレーム、パーツ各社、共通な所が考えな事もあるようなのでそんなところをちょこっと参考になれば。って事で。
そりゃー、各パーツ一番上で高いものが良いのかもしれませんが、『これから始めよう』って人に『全部トップグレードで揃えろ』なんて勧め方で敷居高くしてもしょうがないでしょ?
『こういうところは上のグレードにした方が良い、ここにお金かけるならコッチにかけた方が良いと思う』って感じに最終的にはなるかと思います。(まとめるまで長くなっちゃうけど…)
------------------
●ブレーキ
もうここ最近の新型やラインナップされててマイナーチェンジしたシクロクロス車体はほとんどが『ディスクブレーキ』で製造されてるんじゃないでしょうか。
『最初だから中古車体(フレーム)で…』と考えている方もいるでしょうが、カンチブレーキ、Vブレーキ車体が中古で安く出ている場合もありますが、ディスクブレーキ車体の購入を迷わずお勧めします。
理由は、軽い力でブレーキが効くので、腕に力が入らないで済む(疲れにくい)、がまず挙げられます。
ロードバイクで平坦路や山の下りを走っているよりシクロクロスはスピードは出ません。おそらく自分がシクロクロスのレースで出てる最高速はいいとこ45㎞/h位だと思う。しかし、『最高速で走っててブレーキかけてスピードを落とす』より、シクロクロスはテクニカルなコースの周回レースなので、20数㎞/h以下の平均レーススピードでも『フルブレーキ、曲がって、フル加速、またフルブレーキで180°ターン』みたいなのの繰り返しになります。ブレーキングの回数は非常に多いので、指先の力だけで速度が落とせるディスクの方が間違いなく楽で、ブレーキング動作より曲がる方に集中できます。
作動方式は『油圧式』とリムブレーキのシフトレバーのままワイヤーで動かす『機械式』が有りますが、油圧の方が安定して軽い力で作動します。但し、金額は油圧の方が高額になります。
油圧と機械のハイブリッド式って方法もあります
------------------
ブレーキキャリパーのフレーム側への取付方法ですが、最新だと『フラットマウント』方式がほとんどじゃないでしょうか?
左がポストマウント、右がフラットマウントのキャリパー。解りやすいと思って適当なボルトを立ててます。取付ピッチが違います。ポストマウントはマウンテン車体は標準で、少数になってきてますがエントリー向けグラベルロードで採用され、フラットマウントはロード、シクロクロスのディスク車体で標準的な取付方法になってきているかと。
シマノや他各社からアダプターが出ているのでポストマウント⇔フラットマウントの変換取付は出来ます(下の画像の左側のキャリパーに付いてる板状の物がアダプター。これはフラットマウントのキャリパーをFフォークに取り付ける際の物。向きを変える事によりφ140㎜とφ160㎜両方のローターサイズに対応出来たりします。) フラットマウントの取付ボルトを外す際には緩み止めの『割りピン』を抜きましょう(矢印の)

------------------
●ディスクローター
ロードの方では主流になっているサイズは前がφ160㎜、後ろがφ140㎜になってきています。一応、『大径の方が効く』です。シクロクロスだといくつかのメーカーの完成車を見るとローターサイズにはバラツキ有るよう。F、Rともφ160㎜の車体もあればロードと同じってトコもあったりしてる。
ホイールへの取付方式は6本のトルクスで固定する『6穴式』(左)と、スプロケットのロックリング工具や、(シマノの)BBサイズの工具で締め付ける『センターロック式』(右)の2種。サードパーティー製では6穴式が若干種類が多く金額も安めかと。
※6穴式はボルトが固着すると(ネジロック剤も付けるし)面倒なので…ここのトルクスボルトを緩める際には『精度の良い丈夫な工具を垂直にセットし、しっかり押しながら回して緩める』で。じゃないとあっさりボルトをナメます。
また、以前も書きましたが、シマノでは6穴のφ140㎜というローターはラインナップに在りません。(6穴取付のハブもほとんど無い)6穴式をセンターロック式に変換するアダプターも出てますがクリアランスが狭くなり、キャリパー等に接触する場合もあるようなので注意。
------------------
●ハブ、ハブ軸
まずO.L.D(オーバーロックナット寸法、エンド幅)はフロントが100㎜、リアは135㎜から現在は142㎜が標準となってきました。
軸はリムブレーキで主流なクイック方式からφ12㎜のEスルーアクスルがディスク車では標準になってきています。
Eスルーの方は長さ、ネジピッチ等統一されていないので注意。半回転で脱着が出来るの物も有り。また、メンテナンススタンド(リアのハブ軸にかけるディスプレイ型スタンド)はディスク用でないと使えなかったり…
自分が現在乗っているシクロクロス車体は中古フレームで入手した(おそらく2014年モデル)GIANT TCX SLR(アルミフレーム+カーボンフォーク)でフロントがφ15㎜のEスルーでリアは135㎜のクイックな旧規格なもの。
コレで起こったトラブルは 段差を超えた衝撃でリアのクイックがズレてストップしたってのが起こりました。その後対策はしましたが、(もし再発したらその時はフレーム買換えを検討)前後φ12㎜のEスルーの方が良いんじゃないかな、と。
一応書きますが、自作で車体組む際にエンド幅が合わないからって、やたらスペーサーかまして142㎜幅のフレームに135㎜ハブを入れたり、逆に無理矢理フレームを広げて135㎜エンド幅の車体に142㎜のハブを入れるとかは止めましょうね。
------------------
●ホイール
リムはチューブレス、もしくはチューブレスレディリムを推奨します。
以前は練習用はチューブ入りでやっていましたが、どうしてもリム打ちパンクを防ぐために自分は45psi(3.1bar)~は入れてないとダメでした。(冬の凍結土だとリム打ちしやすかったし、ダート走行は異物が刺さってのパンクも多い)チューブレスだとリム打ちパンクは起きません。
パンク防止+シクロクロスではエア圧は低圧(人によっては2bar以下)にしてグリップを稼ぐ手段にもなります。(自分にゃそこまで下げられん…『ホントのリム打ち』でリムが曲がるな…)
それにシクロクロスではレース当日にコース試走が出来るため試走用(練習用兼スペアホイール)ホイールもチューブレスにしてコース状況を確認できるように変更しました。
チューブ入りでやってればパンク修理(チューブ交換)は慣れますが…
チューブラーもありますが、水気でのセメント、テープの剥がれでタイヤが外れちゃってるのを何度か見てる…
リムの素材はアルミ、カーボンとありますが、最初はアルミで良いと思います。乗り始めはなんせ滑って転びますし、路面のギャップ等への対応が直ぐ出来ず『ガツッ!』とリムを打ったりします。なので最初は軽さより丈夫さを優先した方が良いかと(というか、自分はカーボンホイール持ってませんし)
------------------
一回、切って続きは次回に
------------------
『桜 写日記 4/25 No. 8』
残り僅か
残り僅か
ここの桜は若干、山の方に在るけど、平地はもうほとんど散っちゃったね
さて、さて、さて、シリコンバンドが破損し、感度が怪しくなったリストバンド型心拍計(Mio FUSE)をMioの別製品Mio LINKに換えました。
これまで使っていたMio FUSEは自転車専用じゃなくて通常生活、ランニング等でも使用できるので、心拍数だけではなく歩数、消費カロリー、距離、ペース、タイムなどもログが取れた。
…が、自転車で使ってると、必要なのは心拍数だけ分れば良く、時計も表示することが出来たがサイコンの方に心拍数も時計も表示させていたためMio FUSEを操作して腕時計のように数値を見るって事は結局しなかった。ログもサイコンで取ってたので心拍計の方でログデータが溜まると消去しないといけないのが手間だった。
今回は心拍数をとるだけのシンプルなMio LINKにした。(約7,000円)ANT+対応の心拍計って少ないからねぇ…
本体部の横幅は約30㎜。Mio FUSEとほぼ同じ
バンドサイズはLで商品案内の通り約149-208mmの調節幅
おおよそ最小140㎜
最大200㎜チョイ
------------------
開封してとりあえず充電ー。
充電時間は計ってなかった(放置しといていつのまにか充電ランプ消えてた)…
充電器はMIo FUSEとは端子数が違い互換性無し(Mio LINKは端子4本)
------------------
公式の『SUPPORT』→ユーザーガイド→PDFユーザーガイドで取説が見れるけど、『満充電で約8~10時間使用できます。』とのことなので、ロングライドだと電池切れになるか?
------------------
充電終わってスマホ(iPhone 6)とペアリング。
公式に2019年9月1日 【アプリ Mio PAI Health、Mio GO 配信/サービス終了のご案内】 この度、Mioアプリ「PAI Health」、ならびに「Mio GO」の配信が終了となりました。
と出ているけど、『Mio GO』ってアプリで前のMio FUSEの時から使ってるので、旧アプリのまま使う。
腕に巻いて真ん中辺を長押し。ランプが点滅して心拍を探してるので安静にしてしばらく待つ。速く点滅してたのが遅くなるのでそうなったら動いてOK。そしてMio GOアプリでペアリング。
MAX心拍数やなんかを設定してペアリング終了ー。(心拍数は46ってなってるけど、これで合ってる)
サイコンとのペアリングも終了。
------------------
精度は胸バンド式の方が良いとは思うけど、サイコンの表示数値をガン見してるわけじゃないし、明らかずっとおかしな数値を表示しっぱなしって事は無いんで『目安で心拍数がわかれば良いか』なのでMio FUSEの時から普通に使えると思ってるけど。
------------------
『桜 写日記 4/22 No. 7』
散り盛ん
散り盛ん
先日、雨降って風強かったから…
6/28開催予定だった『ツール・ド・美ヶ原 2020』
が開催中止となってしまった…
が開催中止となってしまった…
これで自分の今年の予定だと8月末の乗鞍ヒルクライムまでヒルクライムレース無し…というか今年は乗鞍だけかも…
------------------
えー、あー、さて、さて、さて…
とりあえず自分が実際に乗ってみて、整備して、レースで見ててで思ったシクロクロス用フレーム素材についてを。かなり独断と偏見の目線で。以前書いたヤツを編集で
1年目、2年目はGT GRADE(アルミフレーム、フルアルミFフォーク)で走ってた
------------------
〇『レースに出て、上位を目指し、上のクラスで走りたい!最初の車体購入金額も¥30万~でも出せる』
って人は各メーカーのトップモデルを迷わず買ってください。おそらくカーボンかクロモリ車体になると思う。
ただし、上のカテゴリーに行くほど競技時間が長くなり、トップカテゴリーだと走行時間が1時間とかになります。どうしても走行時間が長くなると泥詰まり、メカトラブルが発生しやすくなるため、上のカテゴリーだとコースに『ピットエリア』があり、メカスタッフに居てもらったり、スペア車体を用意するようになります。つまり車体は2台は必要になります。
これ、ピットがあって車体交換が可能ってのを自分は全く知らなかった。(あくまで上級クラスのレースでの話ね。初心者クラスは競技時間が30分位、ピットは無しだと思う。)一台で走りきることも当然可能だけど、スペア車体が有った方が絶対的に有利かと。ガチでいくなら最終的に(車体約¥30万~上限無し+カスタム費)×2台分の費用は軽く必要になります。(シリーズ戦など多く参戦するなら車体2台+装備品なども積載できる車も必要かと。)
〇『今どきレース用の自転車なら当然軽いカーボンでしょ。担ぐことも有るんだし。けど2台分も金は出せん』
って人でカーボンフレーム購入を考えてる人へ。
メリットはまず確かに軽いこと。ワイヤーが内装の物が多いので障害物に引っかかりにくい。確かにレースでは絶対的に主流。
デメリットは転倒してフレームを地面にぶつけた衝撃で打ち所が悪いとフレームが割れて一発フレーム即死の可能性もある。
どうしてもダート走行しているとチェーンが落ちやすいので下手にBBの所で落としてチェーンがチェーンリングと絡むとBB部破損するかも。
リアエンド(リアディレイラーとフレームの接合部)までカーボンで一体成型しているとメカトラでRディレイラーがもげた時にリアエンドも割れる可能性がある。
『(車体がもったいないから) 転ばずに速く走る』(確かにそれが出来れば理想だが)を目指すならカーボン。
だけど『転ぶ直前の今の自分のマシンコントロール限界点を知らず、ギリギリの攻めの走りをしないで速くなれるのか?』と思う。
〇『レースに出て、転んででも速くなりたい。』って人には最初の1台目にはアルミかも。
メリットはエントリー向けとして車種が豊富なので予算に応じて色々選べる。
デメリットとしては矛盾しちゃうけど、エントリー向けのパーツ構成のものが多いから車体の戦闘力を上げようとするとコンポ、ホイールの一式積み替えが必要になることがあるため完成車で購入するとパーツ交換の費用が後々かかる。機械式ブレーキを油圧式に替えるとかだとほぼ丸ごと交換。(ジャイアントので『機械式ブレーキワイヤーにアダプターを付けて油圧に変換』みたいなのも有るけど。あとHY/RDキャリパーとか)
Rホイールもシマノスプロケで11速に対応していないホイールだと10速→11速に積み替えする時にはホイール(もしくはフリーボディ)の交換が必要。(34-11T カセットで例外有り)
ワイヤーが外通しでインナーワイヤーがむき出しの物が多いので、泥詰まり、冬に低温で凍って動かなくなることも有る。
冬の極寒時(およそマイナス5℃以下)の雪道走行をしているとこんな感じにダウンチューブに雪がついてしまう。
こうなってしまうとダウンチューブ下にシフトインナーワイヤーがむき出しで通っていると凍結してしまう。BB下でも。凍結状態のワイヤーを無理に動かしていると、シフトレバーのギア機構が壊れたり、インナーワイヤーが切れてしまう事が有るので。なのでワイヤー類はフルアウター化やライナー加工して凍結防止を。お金が有れば電動化して下さい。(電動でも着雪注意)
この時のGTはワイヤーフルアウター、フロントシングル仕様だったので着雪してもインナーワイヤーは凍結せず問題無しだった。
フレームセットで購入できるなら完成車購入よりバラ組で作った方が長く使える車体になるかも。
※転んでもカーボンより被害が比較的小さいといってもパーツは消耗品と割り切った方が良い。ディレイラーハンガーは常にスペア持ってた方がいい。
〇『カーボンほど高くなく、クロモリもあるじゃん』
クロモリフレームでの一番の問題と思われるのはフレーム内部に水が溜まっての腐食(サビ)かと。
毎回ダート走行後には洗車して、シートポスト外して、必要ならFフォークも外して、で内部の水抜きをやって乾燥させる時間とマメさが有る。という人ならクロモリを選ぶのもアリ。※ケーブル類は外通しの物が多い。
水抜きサボるとねじ切りBB(クロモリだと大抵ねじ切り(スレッド)BBかと)やシートポストが錆で固着するぞ。(他のフレーム素材でも水抜きは必要だけど)
------------------
泥詰まり対策としてフレームとタイヤなどのクリアランスでBB裏とブレーキ付近に注意!
カーボンフレームだと(この写真はヒルクライム用の車体のなのでフレームとタイヤのクリアランスが狭いけど参考までに)BB裏は滑らかに成型されているのでひっかかりが少ないけど
金属系フレームだとBB裏に補強、センタースタンド、フェンダーを取り付ける前提の為の『チェーンステーブリッジ』と呼ばれる棒状のパイプが溶接されていることが多い。(矢印の)

これが有ってフロントシフトワイヤーも有ると泥がここに溜まりやすくなり最悪こうなる。
長く伸びた芝と粘土質の土が混ざってシフトワイヤーに絡みついて簡単に取れず、泥詰まりでタイヤが回らない。初出場のレースはこれで途中リタイヤ。この時はフロントチェーンリングはダブル。(車体はGT GRADE。この車体はシクロクロス向きではなかった。だけど、この車体で結果を出したかったので最初はGTで走ってた。一番良かったリザルトでCM1+2+3混走レースで20名中8位、CM3クラス内では1位)
GT GRADEの純正状態(アルミフレーム このGTは棒のブリッジだけでなくガゼット(板)補強もあるので尚更泥が溜まりやすかった。初レース後はフロントシングル化してこの部分もちょっと加工した。下の画像ではタイヤは700×23c。現在でも通勤+どこでも行ける用として活躍中)
GIANT TCX SLR(アルミフレーム)のBB後ろ。ブリッジが無く、フロントシングル仕様なのでクリアランスが広め。タイヤは700×32c
『ブリッジが無いとフレーム剛性が~』と言われるけど、初心者、普通の人には無くても問題無いので…フレーム剛性云々の前に乗り方です。車体を激しく左右に振るダンシングで力任せにペダリングしてもシクロクロスでは速く走れません。泥、雪等の滑りやすい路面だと車体を振るダンシングしてるとスコーンと直ぐスリップダウンします。カテゴリー1や全日本のエリートクラスの人達の走行動画をよく見て下さい。フラットだったりアスファルトはダンシングしてる場面もありますが、激坂とかでもほとんどシッティングで走り、車体、身体を左右にはあまり振ってません。上半身のわずかな動きとサドル着座位置で重心移動を行い、絶妙に前後タイヤへの荷重を配分をして走っています。(力を入れずペダリングしてる訳ではなく、シッティングで超パワーはかけてる)
ヒルクライムでキツイ時をイメージしてみて下さい。キツくてダンシングに逃げ、やたら前荷重(腕からハンドルに荷重)にするような乗り方だと後ろタイヤはグリップしません。グリップの良いアスファルトならある程度誤魔化せますが、ダートで前荷重にしすぎると直ぐリアがホイルスピンして前に進みません。
『タイヤの銘柄が~』とか『エア圧が~』とかより前の話だと思います。
------------------
チェーンステーとタイヤのサイドクリアランス。
写真の赤マル部、泥などが激しいと黒い純正塗装が剥がれてフレーム素材のアルミ地がむき出しになる位削れる。

これがカーボンフレームだったら?クラック(ヒビ割れ)が入るかも
また、Rブレーキ付近もクリアランスが狭くなる。
この写真はRブレーキを真後ろから撮ったもの。この車体はブレーキキャリパーの固定方式が現在主流のフラットマウントではなくポストマウントだけれでも、ディスクローターとフレームの取付台座のクリアランスが狭くなる。

ホイールを外して内側から。ここもフレームの塗装が削れてアルミ地が出てる。

泥コースメインで走る車体の場合は要注意。
カーボン、クロモリ、アルミ、少数だけどチタン、ステンってフレーム素材も様々だけど、『ダート走行後は洗車~メンテする』ってのが大前提なので。乗りっぱなしだとフレームの素材もコンポのグレードもなにもないよ。チェーン、スプロケとかは泥汚れのまま一日放置しとくと直ぐ錆が浮いてくる。
舗装路走行だけのロードより汚れるので当然メンテ頻度は増える。各パーツの摩耗も早く、寿命も短い。
だけど『洗車から自分でやる』ってとこから覚えていけば車体のメンテなんかも『自分でやってみよう』ってなりますよ。
------------------
コンポは次回にします
------------------
ゲラント・トーマス・・・12時間×3日のライドでzwift上とはいえ、36時間で走行距離1,220㎞って、どんだけ…
さて、さて、さて、『競技としてのシクロクロスを始めるなら』って事で書いていきます。
そもそもシクロクロスって競技ですが、ロードバイク的な車体で非舗装路メインの周回コースを初心者クラスで30分~トップクラスで1時間走る競技となります。
比較的短い競技時間で、自分が走った後は他のクラスのレース観戦が出来たりするので勉強にもなります。
使用前

使用後
泥まみれになって何だかわからない。
他者だけでなく周回するたびに変わっていくコースとも戦うレース。みたいな
他者だけでなく周回するたびに変わっていくコースとも戦うレース。みたいな
感じ的には『レースに出る前提で車体を購入し、練習してレースに出場する』という方向で進めていくので、『通勤通学用でシクロクロス車体を乗る(もしくは車体選び)』、『レースには出ないけれどもダート走行をしたい』という方だとちょっと方向が違ってきます。
『方向がちょっと違う』というのも、ここ最近で『ダートロード』というジャンルが広がってきたため、自分的に『シクロクロス』と『ダートロード』と分けて考えていきたいと思います。
------------------
車体の話から行きますが、『シクロクロスという競技』で話をしていくと、『競技』なので機材の方にもルールが存在します。
例えばタイヤ幅。シクロクロスでは
【タイヤ】
シクロクロス競技におけるタイヤ幅は実測33mmを超えないことと規則で定められている。JCF登録必須のカテゴリーについてはこれに従うこと。
と最大タイヤサイズが決められています。そのため『33㎜のタイヤが履けて、タイヤとフレームにクリアランスが有れば良い』のようなフレーム設計だったりします。
(タイヤカタログを見てみるとシクロクロス用タイヤだとほとんどが700×32cとか700×33cのサイズしかないはず。)
それがダートロードで『競技』という枠に縛られていないフレーム設計だと700Cと650B(27.5インチ)両方履けて、650B×2.1(約53㎜)の太いタイヤサイズまでOKとかあったりします。
『太いタイヤが履けるようになっているフレームに細いタイヤ履けばタイヤとフレームのクリアランスが増えて泥が詰まりにくいじゃん』と思われるかもしれませんが、それをやるとBB後ろの設計が『縦のタイヤクリアランスをとるためにホイールベースを延ばさないといけない』『横幅が広くなるとチェーンリングとチェーンステイが接触するからQファクターを広くしないと…』等々複雑になってきます…
そんな感じなので『レースで1時間持てばよくて、泥が詰まったりしたらスペアバイクに交換すればいい。短時間で全力疾走、ストップアンドゴーの繰り返し。快適性とかあまり考えない』短期決戦型シクロクロスフレームと『荷物とか積むためのキャリアを後付けして固定する用のダボ穴が有ったり、長距離旅行も出来るようにハンドル位置もアップポジションで楽な姿勢で、軽量化よりも丈夫さ、便利さの方を優先』って感じの急がないダートロードフレームみたいな?感じでそもそもの設計思想が違うようです。
って長々書いていますが、シクロクロス車体でなくてもマウンテンバイクでも最初はシクロクロスレースに出れます。
機材規定に【バイク】
C1、C2、CJ、CL1、CM1 については、競技規則に則ったシクロクロスバイクで出走すること(MTBでの参加は不可)。
CL2以下・CM2以下についてはシクロクロスバイクでの出走を強く推奨(*)とする。
*スタート時の安全確保の点から、MTBなどフラットバータイプの車両はスタート位置を後方とする場合があるため、大会主催者の判断に従うこと。
イベントによってはMTBファットタイヤなどに関して規制を設ける場合があるため、大会主催者の判断に従うこと。
というように、上のクラスでは不可ですが、CL2以下・CM2以下のビギナークラスだとマウンテンバイクだったり、33㎜以上の太いタイヤを履いていても出走は出来ます。
2019年スーパークロス野辺山にて。左前の人はフラットバーのマウンテンで走ってる
けど、まぁ一回だけじゃなく長く続けるならせっかくなのでシクロクロス用のフレームでいきましょう。
------------------
次回はフレーム素材、コンポの事を書きます
------------------
今朝は走り始めたけど山の方は雲が厚く雨が飛んできそうだったので390号のループ橋を超えるだけの短いコースに変更。
『桜 写日記 4/19 No. 6』
散り始め
遠目から見た時に『赤くなってんな』と思ったが、昨日の雨、風で早くも散り始め…
C19(新型コロナウイルス)の影響により先がまだ見えない状況が続いています。
今年は自転車競技には春(5月)~秋前(9月)には月イチペースで長野県内で開催されているヒルクライムレースに参戦し、10月からは長野、山梨、静岡各県でシリーズ戦として行われるシクロクロスのシリーズ戦『信州シクロクロスミーティング(通称 CCM)』に出る予定でいる。
しかし、現状だと春~夏前のヒルクライムレース開催は難しく、中止、もしくは開催を検討中の所が多い。
今年は11月14、15日にRapha スーパークロス野辺山、11月28、29日が飯山でシクロクロス全日本選手権とBigレースが長野県で続くので出れるんなら開催日程が決まっているこの二つを今年は目指してやっていこうかと。
------------------
そして、それまでに『当たり前の普通の生活』が出来るようになるのを願うのみ。
『何かしらの特効薬が出来るのを待つ』しかなさそうだけれども、自分に出来るのは感染しない、させないようにして医療関係者、他の方に余計な負担を掛けないようにする位しか出来んが…
------------------
さて、さて、さて、シクロクロスを始めてレースに出るようになったのは2017年からで、17年と18年は飯山と上山田の2ステージに出場し、去年(19年)は『もっと経験が積みたいから出れるだけ出場増やすべさ』ってことで5戦出た。
その中でもスーパークロス野辺山で走れたのは良かった。
スーパークロス野辺山っていうと、『ヒルクライムレースの乗鞍みたいな感じか?』ってイメージだったんだけど、ちょっと違う。
自分が出てるヒルクライムレースだと人が多いのは乗鞍ヒルクライム、次いでツール・ド・美ヶ原だと思うけど、それは参加者が多いって話(それ以上に人が多い富士ヒルやハルヒルには出たことが無い)
それがスーパークロス野辺山は観客も多い。
ヒルクライムレースだとスタート地点は選手も観客もアナウンスもあったりだけど、スタートして競技が始まると(コース規制になるため)基本、途中のコースサイドには観客は居ない。(ツール・ド・美ヶ原はスタートして最初は温泉街を抜けるので観客が多い) 各CP(チェックポイント)とゴールには観客が居るけど、道中はひたすら自分の呼吸音しかせず、黙々と上るになりがち。
だけど、ラインレースのヒルクライムレースと違ってコース周回レースのシクロクロスだとコースのどこにでも観客が居て、カウベルの音が鳴り響き、BGMも鳴ってる。あのお祭り的なノリが走ってても良い。
レースで走ってると、観客の人の方を見たり手を振り返す余裕はまるで無いが、『行け―!、がんばれー!、踏めー!』とかの応援はバッチリ聞こえてます。走っててもテンション上がる上がる。BGMもテンションアップに一役買ってる。
(バイク(原チャリ)のレースにちょこっと出たことが有るけど、排気音とフルフェイスのヘルメット+風切り音で人の声(PITの人の声)なんかほとんど聞こえない。。。)
自転車競技の他ジャンルのクリテリウムとかだったり別のスポーツ競技でもこんな感じなんかな?とは思うけど、他のスポーツで競技ってやってないので知らんのよ…(観客で見てるのと出場してるのでもかなり違うが。)
------------------
めっちゃ前フリが長くなったけど、次回からは競技としてのシクロクロスって事で書いて行こうと思います。自分もまだ3シーズン、10戦も出てません。
ヒルクライムレースには出てましたが、シクロクロスはほぼ知識ゼロから始めてます。『飯山や自宅から30分位の場所(上山田)でレースやってるなんて知らなかった。せっかくなので出れるなら出てみよう』な感じで始めた位です。
自分が感じたこと、やってみたことしか書けませんが…
それでも『今年から始めてみよう』って人が居れば前にも書いた通り春の今からやってけば秋~冬のシクロクロスシーズンには十分間に合いますって。
タグ :シクロクロス
えー…C19(新型コロナウイルス)への対応による「緊急事態宣言」が全国に拡大されるという事態になってしまいました…
通常生活も不便になる感じがするが…
------------------
そんな事態になってしまい、6/7に開催されるなら出るつもりでいた『つがいけサイクルクラシック』が開催中止に。…だけど、『こんな状況なら開催は難しいだろうな…』とは覚悟していた。
また、5/17に開催予定だった『車坂峠ヒルクライム』も開催中止に。(こちらは5月の日曜日は休めなさそうなので出場は見合わせていた)
その代わりに、というか、例年だと5月15日に冬季通行止めが解除され開通になる『乗鞍スカイライン』に5月中に上ろうかと考えていたが、『不要な県外への移動』にあたるかと思い、こっちも行くのは難しいか…
(行くならこっち(長野で)食べ物、飲み物買っといて、家から乗鞍スカイライン上り口の平湯峠ゲートまでノンストップで行き、畳平まで上って写真撮って自販機も使わず(他の物にも接触せずに)Uターンしてくるつもり。トイレも自宅で済ましとけば大丈夫、向こうでトイレにすら多分寄らない。)
人が居ない時は上ってる最中は半径500m以内に他の人が居ない位なので飛沫感染とかまず無いと思うんだけど。(畳平には人は居るが…)ただ、開通直後は上ってる人が多いようなのでちょっとね…
あとひと月あるけど状況が良くなって警戒レベル的なのが下がればね…
------------------
話は変わって最近、心拍計(Mioのリストバンドタイプ)の『タッチ操作感度が何か悪くなったなー』と思っていたが…
内側が…
チ~ン 死亡ー…
こっちもトホホだよ…
本当なら先週の日曜日(4/12)にフランスで約260Kmを走るワンデーレース、通称『クラシックの女王』、または『北の地獄』の『パリ~ルーベ 2020』が開催されるはずだった。
今年はNIPPOデルコ・ワンプロヴァンスに移籍した別府 史之選手も出場予定だったのだが…残念ながらC19の影響により現在のところ『延期』という事になっている。
今回、春のレースが開催(放送)されなかったので、かわりに過去の名レースを放送してたりする。(スカパー!のJスポ他で)
その中でカンチェラーラが単独アタック、長距離逃げ切り勝利を決めた『2010年 パリ~ルーベ』とマシュー・ヘイマンが大金星を挙げた『2016年 パリ~ルーベ』が放送してた。
やっぱり『2016年 パリ~ルーベ』は名レース
歴代最多優勝タイで110年以上続いてるレースで前人未到の単独5勝目を狙う『絶対王者』トム・ボーネン、そのシーズン限りで引退を決めていて最多優勝タイの4勝目を目指すファビアン・カンチェラーラ、ロードの世界チャンピオンを獲り、その頃やたら強かったペテル・サガンなど優勝候補は多かった。
最終的に5人が先頭グループで生き残り、ゴールまで残り5㎞を切った辺りからアタック、牽制の繰り返しで何度トップが入れ替わったか分からない。
一度チギレかけて画面に映らなくなっていたヘイマンがまた前に追いつき、一番後ろで脚を溜めて休んでるんじゃなくてアタックもして、ボーネンのアタックにも単独で追走などを繰り返し。5人の中で一番勝ち目が薄いはずだった。
260㎞、6時間走りっぱなしで最後はベロドローム(自転車競技場)の1/4周でトム・ボーネン他を抑えて1車体分もない差でマシュー・ヘイマンが勝利。こんなんマンガか映画のストーリーだって。
レースを全部見てると6時間、TV放送が7時間の長丁場だけど、前半の100㎞より最後の20㎞の方が時間が長く感じるレース。(流石にぶっ通しで見てられないんでまた録画した)
レース終了後のボーネンのヘイマンへの祝福のコメントがまた泣ける…
------------------
さて、さて、さて、今年の秋の信州シクロクロスは熱くなりそうなんで、『もし、シクロクロスに興味をもって始めるなら』を書こうと思ったけどそれは次回以降って事にして、今回は花見のを。
------------------
『桜 写日記 4/16 No. 5』
満開ですな
満開ですな
------------------
午後からは休みだったので、茶臼山のグランド横の桜の下で昼飯食べてチョイ昼寝を。
1人で行って、そばには人が居ない所で昼飯。(10m以上離れてる)
------------------
『山の方の桜も咲いてんなぁ』と山の方(恐竜公園)を見ていたが…
『ん?』、『んんんー!?何だアレ?』

恐竜…?

黄色になってる??塗り替えたのか?
どっかのギャルとかが酔った勢いでお持ち帰りした恐竜みたいな派手な色してんな。。。
調べたら『恐竜塗り絵コンテスト』の大賞作品のを具現化したとのこと。かなり前から塗り替えられてたらしいが毎年ここに来てんのに全く気付かんかった。。。
------------------
そして木の下でお昼寝ー。
とりあえずお約束は果たした。
------------------
い、稲荷山温泉が!!!!マジかー…
朝っぱらから目が覚めるような記事が出てました。
サブタイの通り、
シクロクロス全日本選手権2020の開催地が長野県飯山市に決定!
会場はいつもシクロクロスミーティング 飯山ラウンドを開催している長峰運動公園
これは2019-20シーズンの飯山ラウンド(2019年11月)1周目走行時の。
スタートして直ぐのダート区間の所。最初は良かったが…
スタートして直ぐのダート区間の所。最初は良かったが…
ニュースソース https://www.cyclowired.jp/news/node/322581
開催日は11月28、29日の予定、との事なので現状だとC19の影響があるが、収束してることを願うのみ。
今年の11月の長野のシクロクロスはスーパークロス野辺山の後、全日本飯山ラウンドと続くので熱くなりそうだ…
------------------
今年は春先のヒルクライムレースはどこも開催が難しそうなので、長野でビッグイベントが続く秋のシクロクロスに向けてって事で、『シクロクロスに出てみる?』を去年書いたヤツをベースに先に書こうかと。
もし興味があるなら今から練習してけば秋のレースには十分間に合いますって!
自分がシクロクロスに出たきっかけは『近くで開催してるんだし、出れるなら出てみよう』位な気持ちからだったので。
------------------
さて、さて、さて、昨日は雨が長い時間降っていた。風も強かったので『満開の桜が雨風で散っちゃうかもしれん』と思い、とりあえずいつもの所の桜の写真だけ撮りに行くことに。
いつもの場所の茶臼山のグランドの横
雨が降ってるので歩いてお花見してる人は居なかったが車は結構多く、みんな車の中から桜を見ていたのかも。
------------------
…そして、今朝も早よからウグイスが鳴いてた