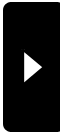さて、さて、さて、仕事の方は終わったんで、走る方の納めを。
いつもの練習場所で昨日はマウンテン、今日はシクロクロスで締めに。
昨日は『雪が降った後で路面がグチャグチャだろうなー』と思ってマウンテンバイクを車載して練習場所へ。


走ってたら昨日は小雪が舞ってきたけど、防水ソックスの下に冬用ソックスを履いて2枚重ねにしてたので全く冷たく寒くなく余裕。
今日はシクロクロスで。
朝起きたら屋根にはうっすら雪が積もっていたが、10時位になると日が出てきて、路面が乾き始めてきたので出撃。
長野市北部の方が雪が多いみたいだったが、篠ノ井橋から千曲川CRに入るとドライ路面。

昨日よりは路面がマシだった。
・・・ロードバイクはローラー台で走り納めか。。。
今年はヒルクライムレースは全く納得いく走りは出来ず、タイム更新できたのは乗鞍だけだった。良くなかった理由がイマイチ分からん・・・
シクロクロスは2年目ということもあってコースを覚えたり、レース慣れもしてきて結果も出せて良かった。CM2、1、カテ3クラスの人達になんとかついていけるようにならんと・・・(上山田ラウンドでCM3で1位になれたけど(総合7位?)、6位のCM2の人とはタイム差がかなりあった。)来年のシクロクロスは参戦レースを増やす方向で。
後は年明けの落ち着いたところでマウンテンバイクを車載して戸狩(スキー場)に行くかーと。
いつもの練習場所で昨日はマウンテン、今日はシクロクロスで締めに。
昨日は『雪が降った後で路面がグチャグチャだろうなー』と思ってマウンテンバイクを車載して練習場所へ。
予想通りのヘヴィーマッド
散々滑った。シューズに泥がてんこ盛り。

走ってたら昨日は小雪が舞ってきたけど、防水ソックスの下に冬用ソックスを履いて2枚重ねにしてたので全く冷たく寒くなく余裕。
---------------
今日はシクロクロスで。
朝起きたら屋根にはうっすら雪が積もっていたが、10時位になると日が出てきて、路面が乾き始めてきたので出撃。
長野市北部の方が雪が多いみたいだったが、篠ノ井橋から千曲川CRに入るとドライ路面。
しかし走るのはこっち(ダート)だけどね。。。
昨日よりは路面がマシだった。
---------------
・・・ロードバイクはローラー台で走り納めか。。。
---------------
今年はヒルクライムレースは全く納得いく走りは出来ず、タイム更新できたのは乗鞍だけだった。良くなかった理由がイマイチ分からん・・・
シクロクロスは2年目ということもあってコースを覚えたり、レース慣れもしてきて結果も出せて良かった。CM2、1、カテ3クラスの人達になんとかついていけるようにならんと・・・(上山田ラウンドでCM3で1位になれたけど(総合7位?)、6位のCM2の人とはタイム差がかなりあった。)来年のシクロクロスは参戦レースを増やす方向で。
後は年明けの落ち着いたところでマウンテンバイクを車載して戸狩(スキー場)に行くかーと。
今年もありがとうございました。2019年もよろしくおねがいします。
2018年もあと残り3日となって仕事の方は外注の仕事は昨日でほぼ仕事納め、後は掃除と棚卸し位を残すのみでやっと落ち着いた。
『今朝こそは起きたら屋根が白いんじゃ?』と思っていたが、またもソレは無かったけど車のフロントガラスは凍ってるし、雪は舞ってるしで寒かった。
地面にはうっすら雪が積もってるので、『こんな時こそシクロクロスを』と(練習場所までは車載で)出撃。
路面が乾いててもロードには乗りたくないが、シクロクロスなら雪が積もってても乗るという。。。(ロードは山まで行くずくがない。移動走行中と下りが寒くて死ぬ。(普段でも市街地は危ないんで体が温まるほど踏まない))



まだ地面がガチガチに凍ってはいないのでそんなには滑らない。しかし最後の方は若干溶けてきてツルっと滑ってコケた。
(篠ノ井橋付近から)須坂、飯山方向は白くて見えない・・・かなり降ってるんかな?
っと、防水ソックスを1ヵ月位使ってみての感想を。
繰り返し使用して洗濯をしているけど、水が内部に浸みてくる事は無く、耐久性は有る。
洗濯後、乾燥させるには裏返してつま先側を上にして吊るさないと内部が乾かない+乾燥までには時間がかかる。(そのため2足購入してたけど)
乾燥機で乾かすのは傷みそうなので止めた方がいいかと。
で、防寒性能は(このソックス単品では)あまり期待できない。
防水性能はあるけど、このソックス自体には保温、発熱性能はないので(保温性能は靴下なので全く無い訳ではないが)、ソックス内部が濡れていなくても、『薄いゴム手袋をして冷たい水の中に手を入れる』ような状態になるため外の冷たさが中に伝わってくる。
シューズが濡れてなくて、気温がマイナス3度位の今日だと鼻呼吸で動ける位がメインの運動ペースなら自分なら1時間位は寒さに耐えられるかな。(今日は耐えられた)シューズが濡れていたり、動かず待機してるような状態だと冷たくて死ぬ。
一応、冬用のシューズは厚いソックスを履いたり、2枚重ねする前提でワンサイズ大きなシューズにしているので、防水ソックスの下にもう一枚冬用のソックスを履けば多少濡れててもイケそう。それでも寒けりゃつま先にカイロ入れるしかないな(低温やけどには注意!)2枚重ねにしてもネオプレーン素材の防水ソックスと違って締め付け感がないので遥かに快適。
冬に限らず(真夏は暑いだろうけど…)シューズが濡れるような状況で走る時には防水ソックスが無きゃ走れん!と思えるようになってますよ。。。
『今朝こそは起きたら屋根が白いんじゃ?』と思っていたが、またもソレは無かったけど車のフロントガラスは凍ってるし、雪は舞ってるしで寒かった。
地面にはうっすら雪が積もってるので、『こんな時こそシクロクロスを』と(練習場所までは車載で)出撃。
路面が乾いててもロードには乗りたくないが、シクロクロスなら雪が積もってても乗るという。。。(ロードは山まで行くずくがない。移動走行中と下りが寒くて死ぬ。(普段でも市街地は危ないんで体が温まるほど踏まない))
--------------------
去年の12/28はこんなんだったが↓(去年記事に飛びます)2017/12/28
--------------------
今日はこんな感じでまだまだ序の口?
--------------------
そしてグルグル廻る。と・・・
パイロンの間隔を半分にしてグルグル・・・
まだ地面がガチガチに凍ってはいないのでそんなには滑らない。しかし最後の方は若干溶けてきてツルっと滑ってコケた。
--------------------
(篠ノ井橋付近から)須坂、飯山方向は白くて見えない・・・かなり降ってるんかな?
--------------------
っと、防水ソックスを1ヵ月位使ってみての感想を。

繰り返し使用して洗濯をしているけど、水が内部に浸みてくる事は無く、耐久性は有る。
洗濯後、乾燥させるには裏返してつま先側を上にして吊るさないと内部が乾かない+乾燥までには時間がかかる。(そのため2足購入してたけど)
乾燥機で乾かすのは傷みそうなので止めた方がいいかと。
で、防寒性能は(このソックス単品では)あまり期待できない。
防水性能はあるけど、このソックス自体には保温、発熱性能はないので(保温性能は靴下なので全く無い訳ではないが)、ソックス内部が濡れていなくても、『薄いゴム手袋をして冷たい水の中に手を入れる』ような状態になるため外の冷たさが中に伝わってくる。
シューズが濡れてなくて、気温がマイナス3度位の今日だと鼻呼吸で動ける位がメインの運動ペースなら自分なら1時間位は寒さに耐えられるかな。(今日は耐えられた)シューズが濡れていたり、動かず待機してるような状態だと冷たくて死ぬ。
一応、冬用のシューズは厚いソックスを履いたり、2枚重ねする前提でワンサイズ大きなシューズにしているので、防水ソックスの下にもう一枚冬用のソックスを履けば多少濡れててもイケそう。それでも寒けりゃつま先にカイロ入れるしかないな(低温やけどには注意!)2枚重ねにしてもネオプレーン素材の防水ソックスと違って締め付け感がないので遥かに快適。
冬に限らず(真夏は暑いだろうけど…)シューズが濡れるような状況で走る時には防水ソックスが無きゃ走れん!と思えるようになってますよ。。。
詐欺(偽)メールの情報です。
『ハッキングされています』『〇月〇日にスパム仕掛けました。カメラで見ています』や件名や本文が全部漢字や英語で同じような内容と思われる詐欺メールがウザいほど皆さんのところにも来てるとは思いますが、
最近『株式会社アドマック の前田 拓磨』なる人物から『〇月分の請求書を送らせて頂きます』的なメールが来るようになりました。
一見、実在しそうな会社員からの送り間違えのメールのようにも見えますが詐欺メールですので、
親切心からメール返信で『メールを送り間違えてます』みたいな返信は送らないように!感染します。
ちょっと前から(追記 検索すると2017年位と結構前から)流れてるようなので注意して下さい。
ってか1度だけ送るんじゃなくて連続で来ればおかしいメールだとさすがに気付くぞ・・・
(以前、凄く名前が似ている会社と実際に取引していたことが自分は有った。しかし『メールでやり取りなんかしてないな』で気付いた)
『カメラをセットしました』で信じちゃって相手に送金しちゃった人も居たようですが…
『今年は暖冬』っていっても去年の記事を見たら12/27にロードバイクで坂を上って走り納めして、28日に結構な積雪になったんだな。去年も降ってなかったんだっけか。
アカン。今年は雪が降ってなくても『ロードに乗ろう』って気にならん…
今度は福岡のスーパーツールの川渕 太一さんだと。
ツール?工具か?そういえば、工具を通販で買っ…ってねえ
『ハッキングされています』『〇月〇日にスパム仕掛けました。カメラで見ています』や件名や本文が全部漢字や英語で同じような内容と思われる詐欺メールがウザいほど皆さんのところにも来てるとは思いますが、
最近『株式会社アドマック の前田 拓磨』なる人物から『〇月分の請求書を送らせて頂きます』的なメールが来るようになりました。
一見、実在しそうな会社員からの送り間違えのメールのようにも見えますが詐欺メールですので、
親切心からメール返信で『メールを送り間違えてます』みたいな返信は送らないように!感染します。
ちょっと前から(追記 検索すると2017年位と結構前から)流れてるようなので注意して下さい。
ってか1度だけ送るんじゃなくて連続で来ればおかしいメールだとさすがに気付くぞ・・・
(以前、凄く名前が似ている会社と実際に取引していたことが自分は有った。しかし『メールでやり取りなんかしてないな』で気付いた)
『カメラをセットしました』で信じちゃって相手に送金しちゃった人も居たようですが…
---------------
『今年は暖冬』っていっても去年の記事を見たら12/27にロードバイクで坂を上って走り納めして、28日に結構な積雪になったんだな。去年も降ってなかったんだっけか。
アカン。今年は雪が降ってなくても『ロードに乗ろう』って気にならん…
---------------
追記
今度は福岡のスーパーツールの川渕 太一さんだと。
ツール?工具か?そういえば、工具を通販で買っ…ってねえ
上伊那郡中川村「天の中川河川公園」で今日、行われた CCMの第8ラウンド 南信州には結局準備不足、車体調整が間に合わずで観戦(試走)にも行けず…
シクロクロス車体のTCXはハンドルの切れ過ぎ感を抑えるためにステム長を変更(長く)した。交換後に走行したけど、良い感じ。(まぁ、『気がするだけ』かもしれんけど。。。)
ステム長は『ハンドルまでの距離』というポジション調整だけの話ではなく、曲がってる時の(曲がり始めるまでの?)ハンドルの切れ角の速さ調整(というか、なんというか)出来るという役割も有るので・・・細かい話は他所を参考にして下さい。。。
それとチェーンデバイスを前の車体のGTで使っていた物を部分的に再利用して製作し、ある程度の位置調整幅をもたせていたけど、制作時に位置を合わせとけばチェーンリングやスプロケの丁数を変える仕様変更がなければ後から位置調整はしないので、もうちょっとシンプルな物にしようかと再製作することに。







新商品の記事でみたチェーンステーに取り付けて、サーボでワイヤーを引っ張ってレバー部分をワイヤレス変速にするという「Xshifter MINI POD」(エックスシフターミニポッド)。
(現状、リア用だけだけど)なるほど、そういう方法も有ったか。
------------------
シクロクロス車体のTCXはハンドルの切れ過ぎ感を抑えるためにステム長を変更(長く)した。交換後に走行したけど、良い感じ。(まぁ、『気がするだけ』かもしれんけど。。。)
ステム長は『ハンドルまでの距離』というポジション調整だけの話ではなく、曲がってる時の(曲がり始めるまでの?)ハンドルの切れ角の速さ調整(というか、なんというか)出来るという役割も有るので・・・細かい話は他所を参考にして下さい。。。
------------------
それとチェーンデバイスを前の車体のGTで使っていた物を部分的に再利用して製作し、ある程度の位置調整幅をもたせていたけど、制作時に位置を合わせとけばチェーンリングやスプロケの丁数を変える仕様変更がなければ後から位置調整はしないので、もうちょっとシンプルな物にしようかと再製作することに。
旧型。ボルトで位置調整すれば多少羽を上下に動かして位置調整出来た。
が、実際には取付時に合わせとけば後で調整ってのはしない。
が、実際には取付時に合わせとけば後で調整ってのはしない。
羽の部分から作り直す事に。材料は前回の残りのアングル材の切れっ端と角パイプから。
羽の部分はこんなんか?
本体部分を切って、穴開けて、削って・・・
色塗って(ツヤ消しよりツヤ有りの方が泥が付きにくく、洗車時に落としやすい
かと思って今回はツヤ有り仕上げで)完成ー
かと思って今回はツヤ有り仕上げで)完成ー
多少軽くなったかなー位な感じで。それでも上下方向には微調整出来る。
------------------
新商品の記事でみたチェーンステーに取り付けて、サーボでワイヤーを引っ張ってレバー部分をワイヤレス変速にするという「Xshifter MINI POD」(エックスシフターミニポッド)。
(現状、リア用だけだけど)なるほど、そういう方法も有ったか。
今日は朝まで雨で、その後は天気も回復してきたので絶好のシクロクロス日和ということで空いてる中休み時間に『グルグル』しに。

単調な基礎練習ではあるけれども、それでも自分は11月のCCM 第4戦の飯山ラウンド後から12月の上山田までの間の約1ヶ月間の走行練習はほとんどコレ『パイロン代りに空き缶2本を立てて、8の字グルグル』をやっていた。その結果が上山田では出せたと思う。
小さなスペースで済んで、短時間でも出来るのでお手軽ではある。しかし、やっぱり単調な動きになり、飽きやすいので(ローラー台みたいなもんか?)ウェアのポケットにスマホ入れて音楽流しながらやってる。(ヘッドホンはせんよ。怪しいサウンドを垂れ流し。周りに人は居ないし。)
それでも路面状況が砂っぽいドライからマッドまで様々なので、今日みたいなマッドだと普通にツルっと滑ってコケる。


『転ぶのも練習のうち』というのがシクロクロスではある。。。何度かコケたけどスピード出てないから体も車体もノーダメージで済むし。着ている物は・・・だけれども。
これで12/23がCCMの『第8ラウンド 南信州』になるけど、『日曜日は仕事』かと思っていたのでエントリーはしていなかったが、たまたま23日は休みになってた・・・
準備不足だし、車体を乗り換えてまだ全く乗れてる感じがしないので今回は参戦を見送るが、行けたらレース観戦のついでにレース当日の試走の時だけ走ってコースを覚えようかどうしようかと・・・
去年のレースの動画を見ると、上山田のような河川敷横のコースレイアウトで、路面状況も芝+舗装路か?最初から長めのストレートが有り高速コースのよう。高さが1m位だとは思うけど、土手をS字のように上ったり下りたりの繰り返しがキツそう。下りは気を抜くと背負い投げ(前転転倒)を喰らうか、跳ねると着地の衝撃で前輪リムがグシャりそうなコース動画だった。
自分なら6分前半で周回出来れば・・・かな?
8の字型のミステリーサークルを製作。
単調な基礎練習ではあるけれども、それでも自分は11月のCCM 第4戦の飯山ラウンド後から12月の上山田までの間の約1ヶ月間の走行練習はほとんどコレ『パイロン代りに空き缶2本を立てて、8の字グルグル』をやっていた。その結果が上山田では出せたと思う。
小さなスペースで済んで、短時間でも出来るのでお手軽ではある。しかし、やっぱり単調な動きになり、飽きやすいので(ローラー台みたいなもんか?)ウェアのポケットにスマホ入れて音楽流しながらやってる。(ヘッドホンはせんよ。怪しいサウンドを垂れ流し。周りに人は居ないし。)
それでも路面状況が砂っぽいドライからマッドまで様々なので、今日みたいなマッドだと普通にツルっと滑ってコケる。
右も
左も
『転ぶのも練習のうち』というのがシクロクロスではある。。。何度かコケたけどスピード出てないから体も車体もノーダメージで済むし。着ている物は・・・だけれども。
-----------------
これで12/23がCCMの『第8ラウンド 南信州』になるけど、『日曜日は仕事』かと思っていたのでエントリーはしていなかったが、たまたま23日は休みになってた・・・
準備不足だし、車体を乗り換えてまだ全く乗れてる感じがしないので今回は参戦を見送るが、行けたらレース観戦のついでにレース当日の試走の時だけ走ってコースを覚えようかどうしようかと・・・
去年のレースの動画を見ると、上山田のような河川敷横のコースレイアウトで、路面状況も芝+舗装路か?最初から長めのストレートが有り高速コースのよう。高さが1m位だとは思うけど、土手をS字のように上ったり下りたりの繰り返しがキツそう。下りは気を抜くと背負い投げ(前転転倒)を喰らうか、跳ねると着地の衝撃で前輪リムがグシャりそうなコース動画だった。
自分なら6分前半で周回出来れば・・・かな?
日が出てるけど気温は上がらずで、雪が舞ってて屋根が段々白く・・・
さて、さて、さて、シクロクロス用の前輪用、15㎜スルーアクスルのハブ、TNIのエボⅡハブ(ランエボか?とお約束を)が来た。
穴は28Hの。標準状態でクイックシャフト仕様になっている。重量は166g。ハブ本体のTNIロゴの左側、赤矢印の所に白いシリアルナンバーが入ってるのがエボ『Ⅱ』ハブ。
クイックシャフト用のアダプターはOリングでハブ本体に嵌っているので、工具無しで手で外せる。
15㎜スルーアクスル用のアダプターは別売りで購入となる。(12㎜用も有り)約¥1,400位。重量は左右2個で6g。
15㎜アダプターは内側にOリングがセットされていて
ハブ本体のくぼみに合わせて手で嵌める。という構造。※斜めに無理矢理強くはめ込むとOリングが伸びて痛むので注意!
アダプターをはめるとOLDが100㎜となる。
15㎜アクスル状態での重量は154g。
『なんか(ベアリングの)シールかグリスで抵抗(回りが悪い)あるなぁ…』と最初は思ったが、組みながらハブを回してたら普通の軽さにはなった。
逆イタリアンの6本組で。重量は838g。リム重量が490gなので400g前半の軽量リムを使えば800gは切れます。スポーク、ニップルはDT。
さて、さて、さて、シクロクロス用の前輪用、15㎜スルーアクスルのハブ、TNIのエボⅡハブ(ランエボか?とお約束を)が来た。

穴は28Hの。標準状態でクイックシャフト仕様になっている。重量は166g。ハブ本体のTNIロゴの左側、赤矢印の所に白いシリアルナンバーが入ってるのがエボ『Ⅱ』ハブ。
クイックシャフト用のアダプターはOリングでハブ本体に嵌っているので、工具無しで手で外せる。
15㎜スルーアクスル用のアダプターは別売りで購入となる。(12㎜用も有り)約¥1,400位。重量は左右2個で6g。
15㎜アダプターは内側にOリングがセットされていて
ハブ本体のくぼみに合わせて手で嵌める。という構造。※斜めに無理矢理強くはめ込むとOリングが伸びて痛むので注意!
アダプターをはめるとOLDが100㎜となる。
15㎜アクスル状態での重量は154g。
『なんか(ベアリングの)シールかグリスで抵抗(回りが悪い)あるなぁ…』と最初は思ったが、組みながらハブを回してたら普通の軽さにはなった。
逆イタリアンの6本組で。重量は838g。リム重量が490gなので400g前半の軽量リムを使えば800gは切れます。スポーク、ニップルはDT。
昨日の夜は風が強くて窓が『パチ、パチ』鳴ってると思ったら、雪が舞ってたのね。。。今日こそは朝起きたら真っ白になってるかと思ったが朝は気温が下がらず雨と。
さて、さて、さて、TCXはとりあえず完成。
バーテープはまだ巻いてないが他の付ける物は付いている練習仕様状態。
ホイールは前後WH-M785の29erでカタログ重量はF840g、R990gらしく、完全チューブレスホイールだけど練習用タイヤ(非チューブレス)のためチューブ入り。
今年の本番用として使っていたRホイール 32h。タイヤIRC シラクCXクロスガード(シーラント入り)、スプロケHG-800の34-11T、ディスクローター6穴の160㎜、スピードセンサーマグネット有りで組んだ状態で(クイックシャフトは無し)2.03㎏(別に全く軽量では無い)
練習用となるXTのホイールで練習用タイヤ+チューブ入り、スプロケは本番用と同じ34-11T、ディスクローターはセンターロックの160㎜、センサーマグネット有りのタイヤ、チューブ以外は本番と同じような状態で2.15㎏。
完組状態でのホイール重量は練習用も本番用のほぼ差が無いので『単純にタイヤが重い』って事で。
ペダルはシマノのPD-M520、サイコンはLezyne Super GPSが付いて、アルミ製ボトルケージ2個、サドルバッグ取付用のベースパーツ、ベル、リフレクターが付いての写真の状態で9.84㎏。
この重量でも前回までのレース仕様より若干だけれども軽くなってる。(前の車体GTだと9.93㎏ってなってる)バーテープを付けて重量増しても保安部品等不要な物を取り外して、タイヤ、ホイールを本番用にすればあと3、400g位は軽くなるかな?
フレームとタイヤのクリアランス。タイヤサイズは32C表記でホイールはXT。
Fフォークとのクリアランスは横15㎜位、縦25㎜位。(タイヤのヤマがかなり減った状態だけど)

Rタイヤ側。BB裏にはブリッジが無いので空いてるねぇ。。。(ネットで探してもこういうアングルで撮ってる写真が少なかった)
タイヤ横は10㎜位。縦(前)は最長で55㎜位のクリアランスが有る。

タイヤをセットする部分のフレーム内幅は約52㎜。
で、今日は午後が空いてるので早速試走に。
朝まで雨が降ってたので路面コンディションはマッド。(かえって好都合)
リストウォーマー。やってれば袖口のスキマ風を防いでくれるので暖かい。しかし真面目に10分位グルグル回って走ってれば暑くなっていらなくなるけど。ホムセンで購入。
ハンドル、サドルのポジション調整をするため工具なども有ったため、練習場所までは車載で。
練習場所に着いて早速走り出す。。。
『お、おぅふ♡』軽い。重量的にではなく推進力的に。練習状態だけど前の本番用と同等に軽く進む。
パイロンを置いていつもの8の字走行を。
ジオメトリの数値だと前のGTよりヘッドパイプが立っているためハンドル(ハンドリングが、か。)が軽い。『スッと』ハンドルがイン側に切れるが、切れる反面、GTの感じでバンクさせ過ぎると(路面がマッドでニュルニュルって事も有るが)切れすぎてコケそうになり足が出る。(GTに比べると)オーバーステア傾向か。
『直線状態(直立状態)でスピード落として、あまりバンクさせずに曲がる。Rタイヤをホイルスピンさせないように後ろ乗り』って感じで30分ほどグルグルと。。。途中でポジションをちょこちょこ変えたが、レバーのクランプ位置はこのままで良さそう。
結構、耕した。
タイヤにはこの位泥が付いているが
Fタイヤ回りの状況。
BB周りの泥状況。泥で詰まらず地面が見えてる。この位の泥ならタイヤサイドも余裕のクリアランス。
チェーンデバイスの所に泥が乗ってるけどこれは問題無し。
これでバーテープ巻いて終わりかな。

スカイが『チーム SKY』のスポンサーから2019年で撤退だと?
------------------
さて、さて、さて、TCXはとりあえず完成。
バーテープはまだ巻いてないが他の付ける物は付いている練習仕様状態。
ホイールは前後WH-M785の29erでカタログ重量はF840g、R990gらしく、完全チューブレスホイールだけど練習用タイヤ(非チューブレス)のためチューブ入り。
今年の本番用として使っていたRホイール 32h。タイヤIRC シラクCXクロスガード(シーラント入り)、スプロケHG-800の34-11T、ディスクローター6穴の160㎜、スピードセンサーマグネット有りで組んだ状態で(クイックシャフトは無し)2.03㎏(別に全く軽量では無い)
練習用となるXTのホイールで練習用タイヤ+チューブ入り、スプロケは本番用と同じ34-11T、ディスクローターはセンターロックの160㎜、センサーマグネット有りのタイヤ、チューブ以外は本番と同じような状態で2.15㎏。
完組状態でのホイール重量は練習用も本番用のほぼ差が無いので『単純にタイヤが重い』って事で。
------------------
ペダルはシマノのPD-M520、サイコンはLezyne Super GPSが付いて、アルミ製ボトルケージ2個、サドルバッグ取付用のベースパーツ、ベル、リフレクターが付いての写真の状態で9.84㎏。
この重量でも前回までのレース仕様より若干だけれども軽くなってる。(前の車体GTだと9.93㎏ってなってる)バーテープを付けて重量増しても保安部品等不要な物を取り外して、タイヤ、ホイールを本番用にすればあと3、400g位は軽くなるかな?
------------------
フレームとタイヤのクリアランス。タイヤサイズは32C表記でホイールはXT。
Fフォークとのクリアランスは横15㎜位、縦25㎜位。(タイヤのヤマがかなり減った状態だけど)
Rタイヤ側。BB裏にはブリッジが無いので空いてるねぇ。。。(ネットで探してもこういうアングルで撮ってる写真が少なかった)
タイヤ横は10㎜位。縦(前)は最長で55㎜位のクリアランスが有る。
タイヤをセットする部分のフレーム内幅は約52㎜。
------------------
で、今日は午後が空いてるので早速試走に。
朝まで雨が降ってたので路面コンディションはマッド。(かえって好都合)
リストウォーマー。やってれば袖口のスキマ風を防いでくれるので暖かい。しかし真面目に10分位グルグル回って走ってれば暑くなっていらなくなるけど。ホムセンで購入。
ハンドル、サドルのポジション調整をするため工具なども有ったため、練習場所までは車載で。
練習場所に着いて早速走り出す。。。
『お、おぅふ♡』軽い。重量的にではなく推進力的に。練習状態だけど前の本番用と同等に軽く進む。
パイロンを置いていつもの8の字走行を。
ジオメトリの数値だと前のGTよりヘッドパイプが立っているためハンドル(ハンドリングが、か。)が軽い。『スッと』ハンドルがイン側に切れるが、切れる反面、GTの感じでバンクさせ過ぎると(路面がマッドでニュルニュルって事も有るが)切れすぎてコケそうになり足が出る。(GTに比べると)オーバーステア傾向か。
『直線状態(直立状態)でスピード落として、あまりバンクさせずに曲がる。Rタイヤをホイルスピンさせないように後ろ乗り』って感じで30分ほどグルグルと。。。途中でポジションをちょこちょこ変えたが、レバーのクランプ位置はこのままで良さそう。
結構、耕した。
タイヤにはこの位泥が付いているが
Fタイヤ回りの状況。
BB周りの泥状況。泥で詰まらず地面が見えてる。この位の泥ならタイヤサイドも余裕のクリアランス。
チェーンデバイスの所に泥が乗ってるけどこれは問題無し。
これでバーテープ巻いて終わりかな。
追記
これで完成。
スカイが『チーム SKY』のスポンサーから2019年で撤退だと?
・・・前回のタイトルに『♭』付けるの忘れてた。まぁ、それは置いといて。
12/9にマキノ高原(牧之原SAのマキノ(静岡県)ではなくて、滋賀県のマキノ高原)で開催された『シクロクロス全日本選手権 2018』のダイジェストが出てたので見てみたが、…『アレは地獄…』。
『暖冬、暖冬』と今年は言ってるが、レース会場は降雪で真っ白。メインストレート過ぎて1コーナーの右に曲がったらいきなり担ぎでワッショイ。最初の方は(自転車に)乗ってる映像より担いでる映像しかないぞ…しかしこれが真の『冬シーズンの』シクロクロスなんだろうか…
https://www.youtube.com/watch?v=HM2kxZ1QLNQ ←でyoutubeの男子エリートクラスのダイジェスト動画へ飛びます。
さて、さて、さて、今回はケーブルエンドの処理とかチェーンデバイスを・・・

現行モデルのTIAGRA(~4700シリーズ)、SORA(~R3000シリーズ)、Claris(~R2000シリーズ)や旧モデルのDURA(~9000)、Ultegra(~6800)、105(~5800)のRディレイラーのシフトワイヤー取付口は後ろ方向に有ってシフトワイヤーは円を描くような感じだったけど(下の画像)
DURA、アルテ、105ではMTBのようなデザインの『Shadowデザイン』となったモデルからワイヤーの取付口も変更になった。
フレームメーカーの方でせっかくケーブル捻じれが無いようにフレームエンドから真っすぐ後ろに出すように設計してるのを無視して
シフトワイヤーを斜め上方向から入れるに変更しているため、ShadowデザインのRディレイラーを取り付ける時は普通に売っているシフトワイヤーではなく、シマノの品番では『OT-RS900』を使用した方がいいです。
このシフトワイヤーは通常のシフトアウターワイヤーだと内部の鋼線が『縦』に並んでいますが、ブレーキアウターと同じように鋼線が『巻いて』あります。この方が小さな曲げにしやすい為で、また、このケーブル自体も通常のワイヤーに比べて柔らかく曲がりやすくなっています。柔らかいが、潰れやすいとも言えるので切断作業やワイヤーの折れ曲がりには注意を!
ただ、『OT-RS900』の品番で探すと240㎜×10本の単位が標準らしい。(長さは240㎜のみ、みたい。あくまでフレームエンドとRディレイラーを繋げられる長さ用)ショップによってはバラ売りしている所もあるようなので補修用などではバラ買いの方がいいかも。(Rディレイラーを買うと1本は付属してますが。)
このケーブル、Rディレイラーについてはもう多数の作業説明が出ているので別の所を参考にしてみて下さい。
どうしてもTCX+アルテのR8000だと90度近い曲がりで短めになる・・・(ワイヤー接続部などは防水処理済み)

チェーンデバイスの方を。
TCXはエントリーモデルのアルミフレームのSLRも2019年モデルからフロントギアがシングルとなり、純正のチェーンデバイスが装着されるようになった模様。(カーボンフレームの画像だと思うけれどもアルミフレームモデルにも同じ物が付いてるんかな?)
チェーンデバイスの効果は身に染みて分かっているのでTCXの合わせて自作を。
まず潔く純正のFディレイラーベースを取り外す。

材料はアルミのアングルからで。
まず厚紙で大体の形状を考える(下の方の黒い『羽根』の部分は前のGTで使っていたものを再利用。)

厚紙をアングルに当てて切り出し
穴開けて周りを削る・・・
色塗って完成。位置の微調整は出来るようにはなってる。
チェーンが落ちてしまった場合も『羽』の切り欠き部分から『知恵の輪』みたいな感じにチェーンを斜め下から入れるとはめられる。
全日本のダイジェストとか見ると寒いがそれでも走りたくなるねぇ…
(今週末だと長野も)雪の中の走行になるかもしれないが…
12/9にマキノ高原(牧之原SAのマキノ(静岡県)ではなくて、滋賀県のマキノ高原)で開催された『シクロクロス全日本選手権 2018』のダイジェストが出てたので見てみたが、…『アレは地獄…』。
『暖冬、暖冬』と今年は言ってるが、レース会場は降雪で真っ白。メインストレート過ぎて1コーナーの右に曲がったらいきなり担ぎでワッショイ。最初の方は(自転車に)乗ってる映像より担いでる映像しかないぞ…しかしこれが真の『冬シーズンの』シクロクロスなんだろうか…
https://www.youtube.com/watch?v=HM2kxZ1QLNQ ←でyoutubeの男子エリートクラスのダイジェスト動画へ飛びます。
----------------
さて、さて、さて、今回はケーブルエンドの処理とかチェーンデバイスを・・・
現行モデルのTIAGRA(~4700シリーズ)、SORA(~R3000シリーズ)、Claris(~R2000シリーズ)や旧モデルのDURA(~9000)、Ultegra(~6800)、105(~5800)のRディレイラーのシフトワイヤー取付口は後ろ方向に有ってシフトワイヤーは円を描くような感じだったけど(下の画像)
DURA、アルテ、105ではMTBのようなデザインの『Shadowデザイン』となったモデルからワイヤーの取付口も変更になった。
このシフトワイヤーは通常のシフトアウターワイヤーだと内部の鋼線が『縦』に並んでいますが、ブレーキアウターと同じように鋼線が『巻いて』あります。この方が小さな曲げにしやすい為で、また、このケーブル自体も通常のワイヤーに比べて柔らかく曲がりやすくなっています。柔らかいが、潰れやすいとも言えるので切断作業やワイヤーの折れ曲がりには注意を!
ただ、『OT-RS900』の品番で探すと240㎜×10本の単位が標準らしい。(長さは240㎜のみ、みたい。あくまでフレームエンドとRディレイラーを繋げられる長さ用)ショップによってはバラ売りしている所もあるようなので補修用などではバラ買いの方がいいかも。(Rディレイラーを買うと1本は付属してますが。)
このケーブル、Rディレイラーについてはもう多数の作業説明が出ているので別の所を参考にしてみて下さい。
----------------
どうしてもTCX+アルテのR8000だと90度近い曲がりで短めになる・・・(ワイヤー接続部などは防水処理済み)
----------------
チェーンデバイスの方を。
TCXはエントリーモデルのアルミフレームのSLRも2019年モデルからフロントギアがシングルとなり、純正のチェーンデバイスが装着されるようになった模様。(カーボンフレームの画像だと思うけれどもアルミフレームモデルにも同じ物が付いてるんかな?)
チェーンデバイスの効果は身に染みて分かっているのでTCXの合わせて自作を。
まず潔く純正のFディレイラーベースを取り外す。
材料はアルミのアングルからで。
まず厚紙で大体の形状を考える(下の方の黒い『羽根』の部分は前のGTで使っていたものを再利用。)
厚紙をアングルに当てて切り出し
穴開けて周りを削る・・・
色塗って完成。位置の微調整は出来るようにはなってる。
チェーンが落ちてしまった場合も『羽』の切り欠き部分から『知恵の輪』みたいな感じにチェーンを斜め下から入れるとはめられる。
全日本のダイジェストとか見ると寒いがそれでも走りたくなるねぇ…
(今週末だと長野も)雪の中の走行になるかもしれないが…
寒い・・・
結局、金、土曜日に降雪は無く、(それでも『長野市(の山間部)は土曜日に初雪を観測。』となったようだけど。)『もしかしたら今朝は起きたら湿った雪で屋根が真っ白になってるんじゃないか』と思っていたがそれも無かった。
CATVの道路Live映像を見ていると、信州新町や飯綱の方の普光寺の辺では雪が舞っていて、北の方は古間や信濃町ICは白い。もうじき市街地にも来るかねぇ・・・
今回はケーブルの処理なんかを。
ハンドル周りのケーブル取り回しが決まって、フレームにケーブルを入れていくけれど、まずR用のシフトケーブルアジャスターの取付。
シフトケーブルアジャスターはこの向きで取付て、上側のアウターケーブルとの接続部は熱収縮ホースで防水処理。
以前にも少し書いたけれど、アジャスターはこの向きの方が防水性能が高いと思う。
アジャスターの構造はこんな感じ。(※シフトアジャスターが2個無かったので、この辺の写真のはブレーキケーブル用のアジャスターです。シフト用より太い)
(シマノパーツで)ロードシフトレバー(STIレバー)で機械式のディスクにする場合はケーブル途中の、走っている時でも操作可能な位置にアジャスターを組み込んで下さい。そうしないと停車して工具を使わないと微調整が出来ません。(テクトロとかの機械式ディスクには工具を使わず回せるアジャスターが付いてるのも有ったような?)
(リムブレーキの)キャリパーブレーキだとブレーキ本体に工具を使わず微調整が出来るアジャスターが付いていますが、ディスクブレーキはホイール中心寄りにブレーキ本体が有るため乗車状態だと手が届かないってのもあります。
文字、写真が小さくて見づらいかもしれませんが、


実際にアジャスター部分をそれぞれの向きで組んで上側を熱収縮ホースで防水処理して、上の方をビニール袋で覆って水を入れてみると違いが有る。
左の方は水が浸入して下のケーブル内部をつたって水が流れてるが、右側は水の浸入を防いでいる。
実際にここまで水に浸かるってことは無いけれど、シクロクロスでの走行後は水道で水をジャバジャバかけて洗車するのでアジャスターの向きを変えて組むだけでも防水効果はあるって事で。
ただ、アジャスター内部のOリングがヘタってると浸水しやすいし、そもそもがこのOリングは防水が第一目的ではないと思うので。緩み防止(カタカタ音防止)と防塵?
こういう風にアジャスター本体にかぶせるように熱収縮ホースを取り付けて防水って方法もあるけど。(若干アジャスターの回りが渋くなるが)
シフトインナーワイヤーは普通のステンレスワイヤーで組込。純正状態でコストダウンのために鉄のインナーワイヤーで組んであるものは錆びる前に交換しときましょう。錆があった時はアウターワイヤーもセットで交換を。
今はどこまでバージョンアップしたかはわからないけど(茶色かったり緑色になったりの)、なんとかコーティングしてあるあのケーブルは部品の付属で付いてきた最初だけ使ったが、ケーブルが毛羽立って動きが悪くなるのでその後は使ってない。
逆に軽くなるという噂の日泉ケーブルは使ってみたかった。
BB下周り。
ブレーキ、シフトケーブルが一旦BB下付近で車外に出るが、ケーブル出入り口はコーキングして防水(レバー側の上の方も防水処理済)。TCXだとチェーンステー下に(スタンドかサイコンのセンサーを付けるための?)埋め込みナットが2個あったが、それも使わないので塞ぐ。
BB下の水抜き穴。ここに糸を通す。
糸の結び目には瞬着(瞬間接着剤)を付けて緩みを防止。
『何のために?』っていうと・・・フレーム内部、BB下に溜まった水を抜けやすくするため。水抜き穴付近の水の表面張力を壊す目的。
一応、糸をつたって水が落ちて来るが、おまじないレベルな事かも・・・
今回はここまでー
結局、金、土曜日に降雪は無く、(それでも『長野市(の山間部)は土曜日に初雪を観測。』となったようだけど。)『もしかしたら今朝は起きたら湿った雪で屋根が真っ白になってるんじゃないか』と思っていたがそれも無かった。
CATVの道路Live映像を見ていると、信州新町や飯綱の方の普光寺の辺では雪が舞っていて、北の方は古間や信濃町ICは白い。もうじき市街地にも来るかねぇ・・・
------------------
今回はケーブルの処理なんかを。
ハンドル周りのケーブル取り回しが決まって、フレームにケーブルを入れていくけれど、まずR用のシフトケーブルアジャスターの取付。
シフトケーブルアジャスターはこの向きで取付て、上側のアウターケーブルとの接続部は熱収縮ホースで防水処理。
以前にも少し書いたけれど、アジャスターはこの向きの方が防水性能が高いと思う。
------------------
アジャスターの構造はこんな感じ。(※シフトアジャスターが2個無かったので、この辺の写真のはブレーキケーブル用のアジャスターです。シフト用より太い)
(シマノパーツで)ロードシフトレバー(STIレバー)で機械式のディスクにする場合はケーブル途中の、走っている時でも操作可能な位置にアジャスターを組み込んで下さい。そうしないと停車して工具を使わないと微調整が出来ません。(テクトロとかの機械式ディスクには工具を使わず回せるアジャスターが付いてるのも有ったような?)
(リムブレーキの)キャリパーブレーキだとブレーキ本体に工具を使わず微調整が出来るアジャスターが付いていますが、ディスクブレーキはホイール中心寄りにブレーキ本体が有るため乗車状態だと手が届かないってのもあります。
文字、写真が小さくて見づらいかもしれませんが、


実際にアジャスター部分をそれぞれの向きで組んで上側を熱収縮ホースで防水処理して、上の方をビニール袋で覆って水を入れてみると違いが有る。
左の方は水が浸入して下のケーブル内部をつたって水が流れてるが、右側は水の浸入を防いでいる。
実際にここまで水に浸かるってことは無いけれど、シクロクロスでの走行後は水道で水をジャバジャバかけて洗車するのでアジャスターの向きを変えて組むだけでも防水効果はあるって事で。
ただ、アジャスター内部のOリングがヘタってると浸水しやすいし、そもそもがこのOリングは防水が第一目的ではないと思うので。緩み防止(カタカタ音防止)と防塵?
------------------
こういう風にアジャスター本体にかぶせるように熱収縮ホースを取り付けて防水って方法もあるけど。(若干アジャスターの回りが渋くなるが)
------------------
シフトインナーワイヤーは普通のステンレスワイヤーで組込。純正状態でコストダウンのために鉄のインナーワイヤーで組んであるものは錆びる前に交換しときましょう。錆があった時はアウターワイヤーもセットで交換を。
今はどこまでバージョンアップしたかはわからないけど(茶色かったり緑色になったりの)、なんとかコーティングしてあるあのケーブルは部品の付属で付いてきた最初だけ使ったが、ケーブルが毛羽立って動きが悪くなるのでその後は使ってない。
逆に軽くなるという噂の日泉ケーブルは使ってみたかった。
------------------
BB下周り。
ブレーキ、シフトケーブルが一旦BB下付近で車外に出るが、ケーブル出入り口はコーキングして防水(レバー側の上の方も防水処理済)。TCXだとチェーンステー下に(スタンドかサイコンのセンサーを付けるための?)埋め込みナットが2個あったが、それも使わないので塞ぐ。
BB下の水抜き穴。ここに糸を通す。
糸の結び目には瞬着(瞬間接着剤)を付けて緩みを防止。
『何のために?』っていうと・・・フレーム内部、BB下に溜まった水を抜けやすくするため。水抜き穴付近の水の表面張力を壊す目的。
一応、糸をつたって水が落ちて来るが、おまじないレベルな事かも・・・
今回はここまでー
さて、さて、さて、ボチボチ細かなパーツが集まってきたのでTCXの組立をね。
TCX SLRは純正状態だとブレーキシステムがGIANTでは『コンダクト』システムってのを採用していて、『(STIの)ブレーキは機械式のワイヤーブレーキで、ステムの部分で機械式作動を油圧に変換する』というシステムのため、『ブレーキキャリパーは油圧式で効きを確保して、レバーはコストを抑えた機械式』という状態になっている。
ステムヘッド部の平たくなっている部分(ハンマーヘッド的な?)に横からブレーキワイヤーが入り、下向きに油圧ホースに変更されて出ている。
純正のケーブル取り回しはこんな感じ。
2018年モデルとなるのか、フロントギアがダブルのモデル。ダウンチューブ上から前後シフトワイヤーが2本フレームに入り、ダウンチューブ左横から後ブレーキホースが入る。
フロントギアがシングルになった2019年モデル。シフトワイヤーが1本になった以外は取り回しは変わってない感じ。
で、今回組み立ててるのはコンダクトシステムではなく、ノーマルステム。
今まで乗っていたGTからコンポは乗せ換えで、シフトレバーはST-RS685。純正の取り回しを参考にして仮組し始めたが、なんかイマイチしっくりこない。
●コンダクトシステムだとブレーキホースがステムの所で真下に出るため、普通のホースで取り回そうとするとステムの下でちょいホースを長めに余らせないと上手くいかない。
●そもそもの車体設計が『右ブレーキレバーで後ろブレーキ操作する』としている為か?ダウンチューブの(自分が乗車した状態で)左側にしかブレーキを通す穴が無い。日本人向けに多い『右ブレーキレバーが前ブレーキ、左が後ろブレーキ』の取り回しだと右にいっぱい切った状態で後ろホース長を決めると、逆の左に切った時にホースが余り気味に。
ほぼ全部黒いので(車体色がマットブラックな所にメーカーロゴまで黒っていう)何だかわかりにくい(『キャラが立ってないんだよ!』)けどこっち(左)側にしか穴が開いてない。右側にも穴が開いてれば良かったんだが。
まずこの二つ。
・・・とりあえずそっちをどうするか考えながら一番取り回しを決めやすい(右レバーで操作する場合の) 前ブレーキからやろうかと。
Fフォークにはタイラップでホースを束ねるための金具(輪っか)が有るのでそれに合わせてFフォークの後ろに添わせるようにしたが・・・
『?・・・左にハンドルを切るとかなりフレームに前ブレーキホースが当たるんだけど・・・』
普段走ってる時ならここまでハンドルを切ることは無いんだけれども、(キャリパーブレーキのロードなら右にいっぱいハンドル切ればブレーキアジャスターがフレームに当たったりもするが…)『それでもなー』って事で、Fフォークの前に添わせるように取り回し。
ホース前回しだと左いっぱいにハンドルを切ってもなんとか当たらず。
前ブレーキの取り回しが決まったんで、後ろシフトワイヤーはダウンチューブ上から入れるより本来ブレーキを通すフレーム横から通した方がケーブルの曲がりが緩やかなのでフレーム横から。シフトケーブルアジャスターも上の写真の位置のフレーム横に決定。
左レバーから出る後ろブレーキホースはヘッドパイプの右から通し、本来シフトワイヤーを通すダウンチューブ上からフレームに入れるに決定。
とりあえず決まり。(バーテープ巻くのは試走してみてからで)
左いっぱいにハンドル切った時でこんな感じ。これ以上ホース長を短くするとヘッドパイプの所に結構擦れる。
次回に続く・・・