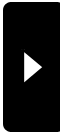さて、さて、さて、『シクロクロスを始めるなら…』って事で3回目、コンポについて。
…っとなるけど、以前にも『シクロクロスを始めるなら』的な事を書きましたが、(小さな画像か下の青文字クリックで過去記事に飛びます)
------------------
(10/10から複数回。今回のはそれをベースにまた書いてる)この時とは状況が変わりました。
------------------
そう、ご存知の方も多いと思いますが、シマノからグラベル用コンポーネント≪GRX≫シリーズが2019年に発売になりました。(今回の『その1』の所で、『グラベルロード』じゃなくて『ダートロード』って書いてますが、主流な呼び方は『グラベルロード』でしたね…)
しかし、自分は全くGRXについては導入していないのでメリット、デメリットは分かりません!ので、もし書く時は『・・・じゃないかなぁ…』でGRXについては書いていきます。(ってか電動(Di2)も無いよ)
それに自分は主にシマノパーツで組んでいるため、SRAMについても全く無知ですが…
(妄想が過度にあるかもしれません)
------------------
とはいえ、基本的な所はフレーム、パーツ各社、共通な所が考えな事もあるようなのでそんなところをちょこっと参考になれば。って事で。
そりゃー、各パーツ一番上で高いものが良いのかもしれませんが、『これから始めよう』って人に『全部トップグレードで揃えろ』なんて勧め方で敷居高くしてもしょうがないでしょ?
『こういうところは上のグレードにした方が良い、ここにお金かけるならコッチにかけた方が良いと思う』って感じに最終的にはなるかと思います。(まとめるまで長くなっちゃうけど…)
------------------
●ブレーキ
もうここ最近の新型やラインナップされててマイナーチェンジしたシクロクロス車体はほとんどが『ディスクブレーキ』で製造されてるんじゃないでしょうか。
『最初だから中古車体(フレーム)で…』と考えている方もいるでしょうが、カンチブレーキ、Vブレーキ車体が中古で安く出ている場合もありますが、ディスクブレーキ車体の購入を迷わずお勧めします。
理由は、軽い力でブレーキが効くので、腕に力が入らないで済む(疲れにくい)、がまず挙げられます。
ロードバイクで平坦路や山の下りを走っているよりシクロクロスはスピードは出ません。おそらく自分がシクロクロスのレースで出てる最高速はいいとこ45㎞/h位だと思う。しかし、『最高速で走っててブレーキかけてスピードを落とす』より、シクロクロスはテクニカルなコースの周回レースなので、20数㎞/h以下の平均レーススピードでも『フルブレーキ、曲がって、フル加速、またフルブレーキで180°ターン』みたいなのの繰り返しになります。ブレーキングの回数は非常に多いので、指先の力だけで速度が落とせるディスクの方が間違いなく楽で、ブレーキング動作より曲がる方に集中できます。
作動方式は『油圧式』とリムブレーキのシフトレバーのままワイヤーで動かす『機械式』が有りますが、油圧の方が安定して軽い力で作動します。但し、金額は油圧の方が高額になります。
油圧と機械のハイブリッド式って方法もあります
------------------
ブレーキキャリパーのフレーム側への取付方法ですが、最新だと『フラットマウント』方式がほとんどじゃないでしょうか?
左がポストマウント、右がフラットマウントのキャリパー。解りやすいと思って適当なボルトを立ててます。取付ピッチが違います。ポストマウントはマウンテン車体は標準で、少数になってきてますがエントリー向けグラベルロードで採用され、フラットマウントはロード、シクロクロスのディスク車体で標準的な取付方法になってきているかと。
シマノや他各社からアダプターが出ているのでポストマウント⇔フラットマウントの変換取付は出来ます(下の画像の左側のキャリパーに付いてる板状の物がアダプター。これはフラットマウントのキャリパーをFフォークに取り付ける際の物。向きを変える事によりφ140㎜とφ160㎜両方のローターサイズに対応出来たりします。) フラットマウントの取付ボルトを外す際には緩み止めの『割りピン』を抜きましょう(矢印の)

------------------
●ディスクローター
ロードの方では主流になっているサイズは前がφ160㎜、後ろがφ140㎜になってきています。一応、『大径の方が効く』です。シクロクロスだといくつかのメーカーの完成車を見るとローターサイズにはバラツキ有るよう。F、Rともφ160㎜の車体もあればロードと同じってトコもあったりしてる。
ホイールへの取付方式は6本のトルクスで固定する『6穴式』(左)と、スプロケットのロックリング工具や、(シマノの)BBサイズの工具で締め付ける『センターロック式』(右)の2種。サードパーティー製では6穴式が若干種類が多く金額も安めかと。
※6穴式はボルトが固着すると(ネジロック剤も付けるし)面倒なので…ここのトルクスボルトを緩める際には『精度の良い丈夫な工具を垂直にセットし、しっかり押しながら回して緩める』で。じゃないとあっさりボルトをナメます。
また、以前も書きましたが、シマノでは6穴のφ140㎜というローターはラインナップに在りません。(6穴取付のハブもほとんど無い)6穴式をセンターロック式に変換するアダプターも出てますがクリアランスが狭くなり、キャリパー等に接触する場合もあるようなので注意。
------------------
●ハブ、ハブ軸
まずO.L.D(オーバーロックナット寸法、エンド幅)はフロントが100㎜、リアは135㎜から現在は142㎜が標準となってきました。
軸はリムブレーキで主流なクイック方式からφ12㎜のEスルーアクスルがディスク車では標準になってきています。
Eスルーの方は長さ、ネジピッチ等統一されていないので注意。半回転で脱着が出来るの物も有り。また、メンテナンススタンド(リアのハブ軸にかけるディスプレイ型スタンド)はディスク用でないと使えなかったり…
自分が現在乗っているシクロクロス車体は中古フレームで入手した(おそらく2014年モデル)GIANT TCX SLR(アルミフレーム+カーボンフォーク)でフロントがφ15㎜のEスルーでリアは135㎜のクイックな旧規格なもの。
コレで起こったトラブルは 段差を超えた衝撃でリアのクイックがズレてストップしたってのが起こりました。その後対策はしましたが、(もし再発したらその時はフレーム買換えを検討)前後φ12㎜のEスルーの方が良いんじゃないかな、と。
一応書きますが、自作で車体組む際にエンド幅が合わないからって、やたらスペーサーかまして142㎜幅のフレームに135㎜ハブを入れたり、逆に無理矢理フレームを広げて135㎜エンド幅の車体に142㎜のハブを入れるとかは止めましょうね。
------------------
●ホイール
リムはチューブレス、もしくはチューブレスレディリムを推奨します。
以前は練習用はチューブ入りでやっていましたが、どうしてもリム打ちパンクを防ぐために自分は45psi(3.1bar)~は入れてないとダメでした。(冬の凍結土だとリム打ちしやすかったし、ダート走行は異物が刺さってのパンクも多い)チューブレスだとリム打ちパンクは起きません。
パンク防止+シクロクロスではエア圧は低圧(人によっては2bar以下)にしてグリップを稼ぐ手段にもなります。(自分にゃそこまで下げられん…『ホントのリム打ち』でリムが曲がるな…)
それにシクロクロスではレース当日にコース試走が出来るため試走用(練習用兼スペアホイール)ホイールもチューブレスにしてコース状況を確認できるように変更しました。
チューブ入りでやってればパンク修理(チューブ交換)は慣れますが…
チューブラーもありますが、水気でのセメント、テープの剥がれでタイヤが外れちゃってるのを何度か見てる…
リムの素材はアルミ、カーボンとありますが、最初はアルミで良いと思います。乗り始めはなんせ滑って転びますし、路面のギャップ等への対応が直ぐ出来ず『ガツッ!』とリムを打ったりします。なので最初は軽さより丈夫さを優先した方が良いかと(というか、自分はカーボンホイール持ってませんし)
------------------
一回、切って続きは次回に
------------------
『桜 写日記 4/25 No. 8』
残り僅か
残り僅か
ここの桜は若干、山の方に在るけど、平地はもうほとんど散っちゃったね
さて、さて、さて、シリコンバンドが破損し、感度が怪しくなったリストバンド型心拍計(Mio FUSE)をMioの別製品Mio LINKに換えました。
これまで使っていたMio FUSEは自転車専用じゃなくて通常生活、ランニング等でも使用できるので、心拍数だけではなく歩数、消費カロリー、距離、ペース、タイムなどもログが取れた。
…が、自転車で使ってると、必要なのは心拍数だけ分れば良く、時計も表示することが出来たがサイコンの方に心拍数も時計も表示させていたためMio FUSEを操作して腕時計のように数値を見るって事は結局しなかった。ログもサイコンで取ってたので心拍計の方でログデータが溜まると消去しないといけないのが手間だった。
今回は心拍数をとるだけのシンプルなMio LINKにした。(約7,000円)ANT+対応の心拍計って少ないからねぇ…
本体部の横幅は約30㎜。Mio FUSEとほぼ同じ
バンドサイズはLで商品案内の通り約149-208mmの調節幅
おおよそ最小140㎜
最大200㎜チョイ
------------------
開封してとりあえず充電ー。
充電時間は計ってなかった(放置しといていつのまにか充電ランプ消えてた)…
充電器はMIo FUSEとは端子数が違い互換性無し(Mio LINKは端子4本)
------------------
公式の『SUPPORT』→ユーザーガイド→PDFユーザーガイドで取説が見れるけど、『満充電で約8~10時間使用できます。』とのことなので、ロングライドだと電池切れになるか?
------------------
充電終わってスマホ(iPhone 6)とペアリング。
公式に2019年9月1日 【アプリ Mio PAI Health、Mio GO 配信/サービス終了のご案内】 この度、Mioアプリ「PAI Health」、ならびに「Mio GO」の配信が終了となりました。
と出ているけど、『Mio GO』ってアプリで前のMio FUSEの時から使ってるので、旧アプリのまま使う。
腕に巻いて真ん中辺を長押し。ランプが点滅して心拍を探してるので安静にしてしばらく待つ。速く点滅してたのが遅くなるのでそうなったら動いてOK。そしてMio GOアプリでペアリング。
MAX心拍数やなんかを設定してペアリング終了ー。(心拍数は46ってなってるけど、これで合ってる)
サイコンとのペアリングも終了。
------------------
精度は胸バンド式の方が良いとは思うけど、サイコンの表示数値をガン見してるわけじゃないし、明らかずっとおかしな数値を表示しっぱなしって事は無いんで『目安で心拍数がわかれば良いか』なのでMio FUSEの時から普通に使えると思ってるけど。
------------------
『桜 写日記 4/22 No. 7』
散り盛ん
散り盛ん
先日、雨降って風強かったから…
えー…C19(新型コロナウイルス)への対応による「緊急事態宣言」が全国に拡大されるという事態になってしまいました…
通常生活も不便になる感じがするが…
------------------
そんな事態になってしまい、6/7に開催されるなら出るつもりでいた『つがいけサイクルクラシック』が開催中止に。…だけど、『こんな状況なら開催は難しいだろうな…』とは覚悟していた。
また、5/17に開催予定だった『車坂峠ヒルクライム』も開催中止に。(こちらは5月の日曜日は休めなさそうなので出場は見合わせていた)
その代わりに、というか、例年だと5月15日に冬季通行止めが解除され開通になる『乗鞍スカイライン』に5月中に上ろうかと考えていたが、『不要な県外への移動』にあたるかと思い、こっちも行くのは難しいか…
(行くならこっち(長野で)食べ物、飲み物買っといて、家から乗鞍スカイライン上り口の平湯峠ゲートまでノンストップで行き、畳平まで上って写真撮って自販機も使わず(他の物にも接触せずに)Uターンしてくるつもり。トイレも自宅で済ましとけば大丈夫、向こうでトイレにすら多分寄らない。)
人が居ない時は上ってる最中は半径500m以内に他の人が居ない位なので飛沫感染とかまず無いと思うんだけど。(畳平には人は居るが…)ただ、開通直後は上ってる人が多いようなのでちょっとね…
あとひと月あるけど状況が良くなって警戒レベル的なのが下がればね…
------------------
話は変わって最近、心拍計(Mioのリストバンドタイプ)の『タッチ操作感度が何か悪くなったなー』と思っていたが…
内側が…
チ~ン 死亡ー…
こっちもトホホだよ…
さて、さて、さて、今朝は走る時間があるにはあったが、天気の方が微妙ー。
それでも1時間位なら降らなそうなので『桜の写日記』撮って、山を1本回ってくるルートで練習に。
国道403号の聖の上り口から。山の上の方は白いんですが…
聖方向には行かず、途中で右折する県道390号の方には雲はかかってきてなかった。
------------------
桜 写日記 4/5 No. 2
一昨日、昨日と日中の気温が高めだったためか開花が進んだ気がする
一昨日、昨日と日中の気温が高めだったためか開花が進んだ気がする
------------------
先日、在った通行止めの看板は無くなっていた。なんとなくで通行止めの理由は想像がついたが。。。
踏切を渡って上りスタート。ゆっくり上ってて雨に降られるのも嫌なんで、踏んでく、で。
頂上近くは昨晩の雨のためハーフウエット路面に。
途中の細い道の所に伐採された木が大量に在った。(画像無し)
ふもとの通行止めの看板の理由はやはりコレ、『着雪のため倒木で通行止めだった』と思われる。(撤去作業ありがとうございます)
回って下ってくると路面もドライに。なんとか雨には降られず終了ー。
------------------
帰宅して車体の方を見ると、ウエット走行気味になったので、砂、水の汚れが…
ササっと汚れ落としの清掃を。
〇車体の方は柔らかめのタオルにクリーナーをつけて軽く拭き取りで。
〇ブレーキやスプロケ、チェーンのメカ系なんかはタオル生地よりTシャツ生地の方が作業しやすかったりします。
タオル生地だと厚みが有って狭い所はやりづらい時もありますが…(例えばブレーキの隙間とか)
Tシャツ生地だと薄目で伸縮性があるので狭い所もやりやすい
取れてる汚れがお分かりいただけるだろうか(ほん呪風に)
汚れを落としたら、可動部分にチョチョッと注油を。
Rブレーキも 清掃前
清掃後
スプロケにもTシャツ生地のウエスで引っ張ってゴシゴシすれば生地が引っかかりにくく、ギアとギアの隙間の汚れも取りやすい。
作業前
作業後(フラッシュ焚いたら逆に暗めになってよく分かんね)
汚れが溜まりやすいBB裏もRホイール外してササっと拭き取り終了
チェーンオイルと砂などの汚れが混ざってこびりついたままにしてると落としづらくなるので、こまめにやってると楽に汚れが落とせます。
------------------
専用のウエスもあったりしますが、古タオルと綿の古Tシャツ生地で十分なので、古着を使ってみては?
家族に古着をとっとくように頼んだり、自分の場合だと 仕事時の制服=普段着=作業服なのでTシャツ生地には困らない。。。
作業用のイス(オイル缶)
の、中身はウエスが大量。。。
今まで多くの方が使っていた(と思う)ルートマップ製作ツール『ルートラボ』が2020年3月31日をもってサービス終了になってしまうため、『じゃあ、代わりのツールを…』って事で、『Ride with GPS』というツールを新たに使ってみる事にしましたよ。
Ride with GPSに限らず他にも別のツールもありますが、それぞれメリットデメリットがあるとは思うけどとりあえずコレで。
------------------
まず、『Ride with GPS』でグーグルで検索すれば最初に出るのでそこをクリック ※Ride with GPSは日本語対応していません(まぁ、なんとかなるさー、で。。。)
そしたら登録が求められるので
名前(ニックネームなので後で変更できます)とメールアドレス、パスワードを決めてサインアップ
------------------
メイン画面がこちら
①の名前の所をクリックするとプロフィール画面に移り、登録情報の変更、ロケーション(ルートを製作する時の初期ポイント)の設定(自分の初期地点は博多になってた…)
初期地点変更は赤丸の所を左クリック、一旦空欄にして右側の地図で地点設定しsetをクリック
登録情報やロケーション変更をしたら下のSave changesをクリック
------------------
メインページの②は他の人が作ったルートの検索、閲覧
③がルート製作
で、③のルート製作画面がこちら。(ルート製作の初期地点を篠ノ井橋に変更してある)
①が道に沿ってルートを製作する
②が直線的にルート製作
③が徒歩、自転車、車と条件変更(※ここがちょっと融通がきかなかった)
④でルートラインの色変更が可能
------------------
手始めにいつもの練習ルートを作ってみる。
言葉だと篠ノ井橋→千曲川サイクリングロード→斉の森交差点から姨捨駅方向に上る→千曲川展望台→国道403号を下って→県道390号へ左折し→ループ橋までの上り→信里を下って→県道70号を下って→篠ノ井橋近くまで戻る ルート。
まず篠ノ井橋を左クリックして土手の上のサイクリングロードをクリック… なんだけど、サイクリングロードをクリックしてるのに No cycling route found.(そこに自転車が通れるルートは無いよ)って表示が!
なので、条件をCyclingからWalking(徒歩)に変更してみる。そしたら引けた。
聖川を越えて高速道路をくぐる所も『自転車』の条件ではルートが引けず『徒歩』で…『自転車道路』ってなってるのに『自転車』で引けないっていう…
しかし徒歩に設定してると割と細かい所までそしてスムーズに引けると思う。千曲橋をくぐる所とか細い道が複数あるけど行きたいルートでサクッと引けた。
そんな感じでとりあえず1周のルートを製作。※下の方に標高データも出ます
『徒歩』でほとんど製作したが、最後の方で県道70号の信田選果場の先の所がかなり太い道なのになぜか『徒歩』『自転車』では引けず
『車』で引けた…(この辺が上で書いてるちょっと融通がきかないところ)
あ、ルートを修正したいときはマップの右下のUndoをクリックすると1つ前に戻ります
製作したルートは『ルートラボ』同様に(公開、非公開、友人のみ等に設定可)アップすることも可能。
------------------
使ってみるとルートラボより細かく楽に引けるかも?って感じ。参考にしてみて下さい
今日は朝から雪が降ったり止んだりな天気だけれども、平地はそんなに積もらないか?っていうか、長野市より九州や鳥取の方が雪が降ってるな…
それでもスキー場には積もってくれよ…まだ行くんだから。
そして2/23(日)は山梨県 清里 萌木の村でシクロクロスミーティング 第9戦(2019-20シーズン 最終戦)になる。会場はこの前(1/13)の第8戦 清里 丘の公園のそばなのだけれど、最終戦は都合がつかないため出れず…
さて、さて、さて、前回からの続きでTRPのハイブリッドブレーキキャリパー HY/RDの続きを。

ブレーキパッドは付属しているが、摩耗してパッド交換する際にはシマノのパッドB01Sと互換が有る為入手しやすい。
このHY/RD キャリパー、特徴があって輪行等でホイールを外した際に不意にレバーを握ってキャリパーが閉じてしまわないようにロック機構が付いている。
開梱した状態だとロックが効いている状態になっていたので(ネジが締めこまれていてピストンが動かない)
通常時はロック解除してから使う。
※組立時にブレーキワイヤーを取付てロック解除せずにブレーキレバーを強く握ると多分キャリパーが(ロックしてるネジが曲がったりして)破損します。使う時は解除を忘れずに
ブレーキワイヤーは以前も書いたけど『コレにすれば機械式ディスクも引きが軽くなり、グニグニワイヤーが延びる感じも減るだろう』と思っていたニッセンケーブルのSP31を使用。
ブレーキキャリパーにワイヤーアジャスターが付いてはいるが、ハンドル付近にも追加でアジャスターを付けた。
また、シフトケーブルアジャスターはヘッド、ダウンチューブの近くに配置。以前書いた『タイラップとクリアホースを使って間隔を維持する』って方法にしてるので、ハンドルを左右一杯まで切ってもシフトワイヤーとアジャスターが上下にバタついてフレームに接触してキズが付くことは無い。

で、交換してのインプレですね…『意外と悪くないな。』
ブレーキの引きの重さは確かに機械式(ワイヤー)なので油圧よりは重い。それにリムブレーキ車に比べるとディスクブレーキはブレーキワイヤーは長くなり、今回のGTだと水、泥のケーブルへの侵入を防ぐためフルアウター化してあるのも引きの重さにはつながってはいる。
だけどブレーキタッチは機械式キャリパーに比べると遥かに固め。ブレーキを握りきった時のグニグニ感はかなり少ない(5600から5700になりレバーのピボット位置変更やニッセンのケーブルの高い引っ張り強度ってのも効いてると思う)
また、(シマノの)機械式キャリパーは片押しピストンで機械式だとどうしてもパッドが斜めに押し出され気味になるが、HY/RDは対抗2POTピストンなので繰り返し動かしてもパッドの戻り位置が安定している。自分はブレーキレバーの遊びは少な目が好みなのでワイヤーアジャスターで遊びを調整できるためギリギリまで遊びを減らせる。(完全油圧だと一応ギリギリまでは詰められない≪事になっている≫)
●動作の軽さは 普通の機械式<HY/RD<完全油圧(ST-RS685、R8020)(まぁ、予想通り…)
で、完全油圧は引きは軽く、指の力が少なくてもロックまで持っていける。機械式だと強くかけたい時は強く握らないとダメだけど、HY/RDはパッドがローターに当たってからの効き方は確かに油圧で、指の力をそんなに強くしなくてもロックまでもっていける。
効きは(雨の中を走ったり、下りで強くブレーキをかけたりは試してないが)ディスクブレーキの効き(そりゃそうだ)。
良くも悪くもHY/RDは機械式と油圧の中間。
ホントは『ヒルクライム用の車体は乗り換えで部品取りにし、リムブレーキのSTIレバーと今回のHY/RDを使ってディスクロードを組もうか』とも考えていた。
重量時に『機械式シフトで油圧ブレーキ+油圧ブレーキキャリパー、ブレーキホース』と『機械式シフトで機械式ブレーキワイヤー+ハイブリッド油圧キャリパー』どっちが重量時に良いのかな?と。(そもそもヒルクライム時の軽さを求めてんならディスクは本当は無いんだけれど。)
(ブレーキの効きとか動作の軽さは置いといて)シフトレバーを軽くするか、ブレーキキャリパーで軽くするか?って。
ダンシングで車体振った時には中心から離れるレバーが重い方が不利とは思うが、最近のディスクブレーキのカーボンフレームは電動シフト+油圧ブレーキで組む事が前提となっているためエアロ化優先でケーブル類をフレーム、ステム内装になっているものが多くなった。油圧ブレーキホースだとある程度の取り回しのキツイ場合でもブレーキ動作に影響は無いけど、機械式だとそうもいかない。機械式でステム、コラム内装はかなり厳しい。
自分は次にレース用のフレームを買うのはもしかしたら最後になるかもしれないのでディスクロードの方は流行を追っかける様子見で機械シフト+油圧で組んでみた。アルミフレームで昔ながらの内装の無いワイヤー取り回しのGTはワイヤー取り回しでキツくなることも無かったのでHY/RDを試してみたかった。
あ、あと油圧ブレーキホースはサードパーツで有る事は有るがカラーバリエーションが基本、黒か白の2色しかないので『フレームやシフトアウターとブレーキケーブルの色を揃えたい』って時にも機械式ワイヤーで組めるこのHY/RDは良いかもしんない。
それでもスキー場には積もってくれよ…まだ行くんだから。
そして2/23(日)は山梨県 清里 萌木の村でシクロクロスミーティング 第9戦(2019-20シーズン 最終戦)になる。会場はこの前(1/13)の第8戦 清里 丘の公園のそばなのだけれど、最終戦は都合がつかないため出れず…
------------------
さて、さて、さて、前回からの続きでTRPのハイブリッドブレーキキャリパー HY/RDの続きを。
重量はキャリパー1つ(ブレーキオイル、ブレーキパッド込)で214g。
ブレーキパッドは付属しているが、摩耗してパッド交換する際にはシマノのパッドB01Sと互換が有る為入手しやすい。
------------------
このHY/RD キャリパー、特徴があって輪行等でホイールを外した際に不意にレバーを握ってキャリパーが閉じてしまわないようにロック機構が付いている。

開梱した状態だとロックが効いている状態になっていたので(ネジが締めこまれていてピストンが動かない)

通常時はロック解除してから使う。

※組立時にブレーキワイヤーを取付てロック解除せずにブレーキレバーを強く握ると多分キャリパーが(ロックしてるネジが曲がったりして)破損します。使う時は解除を忘れずに
------------------
ブレーキワイヤーは以前も書いたけど『コレにすれば機械式ディスクも引きが軽くなり、グニグニワイヤーが延びる感じも減るだろう』と思っていたニッセンケーブルのSP31を使用。
------------------
ブレーキキャリパーにワイヤーアジャスターが付いてはいるが、ハンドル付近にも追加でアジャスターを付けた。
また、シフトケーブルアジャスターはヘッド、ダウンチューブの近くに配置。以前書いた『タイラップとクリアホースを使って間隔を維持する』って方法にしてるので、ハンドルを左右一杯まで切ってもシフトワイヤーとアジャスターが上下にバタついてフレームに接触してキズが付くことは無い。

------------------
で、交換してのインプレですね…『意外と悪くないな。』
ブレーキの引きの重さは確かに機械式(ワイヤー)なので油圧よりは重い。それにリムブレーキ車に比べるとディスクブレーキはブレーキワイヤーは長くなり、今回のGTだと水、泥のケーブルへの侵入を防ぐためフルアウター化してあるのも引きの重さにはつながってはいる。
だけどブレーキタッチは機械式キャリパーに比べると遥かに固め。ブレーキを握りきった時のグニグニ感はかなり少ない(5600から5700になりレバーのピボット位置変更やニッセンのケーブルの高い引っ張り強度ってのも効いてると思う)
また、(シマノの)機械式キャリパーは片押しピストンで機械式だとどうしてもパッドが斜めに押し出され気味になるが、HY/RDは対抗2POTピストンなので繰り返し動かしてもパッドの戻り位置が安定している。自分はブレーキレバーの遊びは少な目が好みなのでワイヤーアジャスターで遊びを調整できるためギリギリまで遊びを減らせる。(完全油圧だと一応ギリギリまでは詰められない≪事になっている≫)
●動作の軽さは 普通の機械式<HY/RD<完全油圧(ST-RS685、R8020)(まぁ、予想通り…)
で、完全油圧は引きは軽く、指の力が少なくてもロックまで持っていける。機械式だと強くかけたい時は強く握らないとダメだけど、HY/RDはパッドがローターに当たってからの効き方は確かに油圧で、指の力をそんなに強くしなくてもロックまでもっていける。
効きは(雨の中を走ったり、下りで強くブレーキをかけたりは試してないが)ディスクブレーキの効き(そりゃそうだ)。
良くも悪くもHY/RDは機械式と油圧の中間。
------------------
ホントは『ヒルクライム用の車体は乗り換えで部品取りにし、リムブレーキのSTIレバーと今回のHY/RDを使ってディスクロードを組もうか』とも考えていた。
重量時に『機械式シフトで油圧ブレーキ+油圧ブレーキキャリパー、ブレーキホース』と『機械式シフトで機械式ブレーキワイヤー+ハイブリッド油圧キャリパー』どっちが重量時に良いのかな?と。(そもそもヒルクライム時の軽さを求めてんならディスクは本当は無いんだけれど。)
(ブレーキの効きとか動作の軽さは置いといて)シフトレバーを軽くするか、ブレーキキャリパーで軽くするか?って。
ダンシングで車体振った時には中心から離れるレバーが重い方が不利とは思うが、最近のディスクブレーキのカーボンフレームは電動シフト+油圧ブレーキで組む事が前提となっているためエアロ化優先でケーブル類をフレーム、ステム内装になっているものが多くなった。油圧ブレーキホースだとある程度の取り回しのキツイ場合でもブレーキ動作に影響は無いけど、機械式だとそうもいかない。機械式でステム、コラム内装はかなり厳しい。
自分は次にレース用のフレームを買うのはもしかしたら最後になるかもしれないのでディスクロードの方は流行を追っかける様子見で機械シフト+油圧で組んでみた。アルミフレームで昔ながらの内装の無いワイヤー取り回しのGTはワイヤー取り回しでキツくなることも無かったのでHY/RDを試してみたかった。
あ、あと油圧ブレーキホースはサードパーツで有る事は有るがカラーバリエーションが基本、黒か白の2色しかないので『フレームやシフトアウターとブレーキケーブルの色を揃えたい』って時にも機械式ワイヤーで組めるこのHY/RDは良いかもしんない。
先週の降雪+冷え込みでスキー場も極上パウダースノー状態だったのに今週は気温が14℃以上に上がったり山でも雨が降ったりでまた雪が溶けてる…
先日の昼時にロードに乗ったけど山のふもとへ行くまでは防寒のロンググローブを着けていたけど、山を上る時(いつもの姨捨駅方向から千曲川展望台)には春夏用の指切りグローブに換え、上りきって帰りの下り~千曲川サイクリングロードを走っている時も結局暖かかったので指切りグローブのまま走行してた。前回走行時の展望台付近に大量に撒かれてた塩カルは雨で流されて路面は綺麗になってた。
例年ならこの時期にロードで山に上るって事は無いんだけど、ホント今年は暖冬。
------------------
さて、さて、さて、今回は『どこでも行ける用』のディスクブレーキのGTのグラベルロード車。
やったのは去年の話になるけどパーツを換えてました。
ブレーキとSTIシフトレバーを。
自転車のディスクブレーキシステムには
〇電動シフト+油圧ブレーキ
〇機械シフト+油圧ブレーキ
〇機械シフト+機械ブレーキ
の3つが多いけど、それら以外に4つ目の選択肢として
〇機械ブレーキレバーを途中で油圧に変換させて油圧ブレーキ
の方式が有る。
GIANTではCONDUCT BRAKE(コンダクト ブレーキ)という名称でステム部でワイヤー式のブレーキを油圧に変換するシステムもあるけど今回 はブレーキキャリパー部でワイヤー式を油圧式に変換するシステムのものに交換。
ブレーキキャリパーはTRPのHY/RD(ハイロード) ハイブリッドブレーキキャリパー
※超酷いことを先に書いてしまうと今だとシマノから105グレード(11速)やTiagraグレード(10速)の少し価格が下がって入手しやすくなった油圧ブレーキコンポが出ているのでシフトレバーやキャリパー等イチから部品を集めて組むのであれば絶対的な効きや動作の軽さは完全油圧ブレーキの方が上だと思うので油圧で素直に組む方をお勧めします。
今回の自分のようにある程度(古い)部品が揃っていたり、『どうしても(旧式の)機械式ブレーキレバーをディスクブレーキ用として使いたい』という場合とかはこのハイブリッドキャリパーはいいのかも。
※今回は取り付けるキャリパーはポストマウント台座ですが、フラットマウント取付ピッチになっている新型のキャリパーも出ています。
HY/RDは結構他の人のインプレがあったり、メーカーの主にグラベル向け完成車で純正採用されてたりする。(FELTのBROAM 40とかに採用されてる)
パーツ代でいうとキャリパー1個約¥10,000と普通の油圧キャリパーと比べて高いが、今回はブレーキパッド付キャリパー2個+6穴 160㎜ディスクローター2枚のセットで約¥15,000の物を購入(新品)
------------------
シフトレバーはシマノ105 5600から5700に変更。(11速にすると手持ちのホイール(フリーボディ)が使えなかったり他の部品も必要になるため11速化はしなかった)
5600と5700の一番の違いはシフトワイヤーが5700でハンドルバーに添うよう(内装)に変更されたので、通称『触覚シフト』ではなくなった。触覚シフトの方が構造的にシフトワイヤーの引きが軽いと思えるが、ハンドルにバッグ等を付けづらい。(というか基本的に付けられない)
また、公表されている点だとレバーのピボット位置が変更されていてブラケット持ちの時の操作が少ない力で済む。レバー自体の大きさがコンパクトになっている。などの変更点がある。
中古で探してると10速の5700の状態が良いものは少なくなってきている為か、それとも新型の11速シフトR7000が出て5800も型落ちとなり市場に多く出ている為か5700と5800の相場はあまり変わらなかった。(新品だと若干プレ値が付いてる)
※『10速同士だから』とはいえTiagraはシフトワイヤーの引き量が違うため旧~10速のRディレイラーと互換性が無いので使えない。
続きは次回にします
先週は『警報級な大雪になるかも』と天気予報で言ってたがそうはならず、それどころか気温高めで雨が降ったりしてスキー場の下の方のゲレンデは雪解けが凄く、地面が見えまくってた。
『これは暫く滑れないかも…』と心配したが、戸狩とかは連日降雪になり一気に積雪量がアップ!良かった良かった…(また気温上がって溶けなきゃいいが)
------------------
県境の方は徐々にではあるけど積雪も増えてきているが、市街地は雪は無いのでこっちの車体も例年より早くOHして走行準備に。
ハンドルは交換するけど他の部分はパーツ交換無しの予定なので各部外して清掃とかして摩耗、破損が無ければ再組付け。
ってか、去年(2019年)のロードは練習抜きでレースで走った距離っていうと栂池サイクルクラシックの17.1㎞と雨天で短縮になったツール・ド・美ヶ原の4.7㎞の合計距離21.8㎞しか本番は走ってない。練習もマウンテンの走行距離が増えたり(別にマウンテンのレース出た訳じゃないが)、8月に骨折して入院後はほとんどロードは距離乗れずにシクロクロスのシーズンINした為、ロードの走行距離自体は例年に比べ少なかった。
------------------
シフトレバーを外してワイヤー類を外す。インナーワイヤーは日泉ケーブルのSP31を使っていたがワイヤーのタイコの近くの所、シフトレバーの中で90度曲がるワイヤーにとって負担がかかる所でもそんなにワイヤーの曲がりが無いように思える。(写真はシフト操作が多い右レバー)普通のステンシフトワイヤーは交換の時はもっと曲がりグセが付いてた気がする。
インナーワイヤーは使えそうなんで、ハンドル交換するとシフトワイヤーの長さが足りなくはなるが、今まで使ってた後ろ用のワイヤーを前用にして再利用で。(ブレーキワイヤーも)
------------------
去年はアウターワイヤーは黒だったけど、今年は赤(ニッセンのアウターではなく別の余ってたのが有った)で。
去年
今年
ブレーキ、シフトとも機械式な為、ケーブルを2本ともハンドルに内装すると取り回しが厳しいのでブレーキは内装、シフトは外通しで。あとは油圧の時と同じ感じで組立。
ブレーキ、シフトとも機械式な為、ケーブルを2本ともハンドルに内装すると取り回しが厳しいのでブレーキは内装、シフトは外通しで。あとは油圧の時と同じ感じで組立。
------------------
…それでも今週辺りから『今シーズン一番の寒波』が来るとか天気予報で言ってんのね…降るのはスキー場で…
------------------
グラインデューロの2020年大会が
信越エリアにて5月23日(土)に開催決定。
信越エリアにて5月23日(土)に開催決定。
年間6戦のGRINDURO 世界シリーズ戦の開幕戦が日本だそうです。
エントリー、コース等詳細はまだこれからみたいだけど、コースは去年走る予定だったコース(台風で距離短縮になった)をリベンジすれば良いんじゃないの?なんて。。。
シリーズチャンピオンもあるらしいですが、そんな世界中を転戦するような豪華な生活してみたいもんだ…
『週明け月曜日の夜から火曜日にかけて警報級の降雪の可能性有り』とは天気予報では言っていたものの、『火曜日の朝は起きたら真っ白なんじゃろか?』と覚悟していたが、そんな事は無く風は強いものの雪は積もる事は無くしかも朝から気温が高いため直ぐ雨になってしまった。
市街地は雪にならなくても自分は良いが、スキー場には降ってくれ…
------------------
さて、さて、さて、例年なら自転車(ロード)は春まで冬眠、ってとこだけど、今年は雪も降らず気温も高めってことで組み立てたディスクロード車の試走をすることに。

時系列的には書いてるのが前後しちゃうけど、試走した後にバーテープを巻いて重量を計ったが、実質的に走行できる完成車状態での重量は8.53㎏。
ボトルケージ2個、ペダル、サイコン、サイコンマウント、ベル、後リフレクター有りでの重量。
------------------
走ったのは先週で、バーテープを巻く前のポジション確認ってことで走った。
走ったコースは篠ノ井橋→千曲川CR→斉の森交差点から姨捨駅へ上り→千曲川展望台まで。
千曲川展望台まで上って帰り道は403号を下ろうと思ったが、上ってる最中の日陰部分の路面が湿っていた為、日陰部分が多い403号だと霜や塩カルが撒かれてる可能性が高いので日当たりの良い来た道を戻る。で
------------------
とりあえず千曲川CRを南下。風はほぼ無し。30㎞/h目安で走行。車重自体が重いってのも有るが、組んだばかりでグリスがなじんでいないので、ハブ、クランクの回りが重い…
※1/13のシクロクロスレース以後、全く自転車に乗ってない+防寒装備で動きづらく、重いってのもあります。
グリスなじませる方向で回す感じで、ガチャガチャシフトも動かし、ブレーキも掛けたり放したりの慣らしをやってきながら姨捨方向へ。
まずヒルクライム用の車体より絶対的に重量があるってのが最大のマイナスポイントだけれども、反面グレードの低いフレーム(フレームの詳細はまたで)って事もあって?柔らかいからか、乗り心地は良い。サイクリングロードの舗装の繋ぎ目等を通過してもアルミフレームの『コン、コン』ともヒルクライム用のカーボンの『コッ、コッ』とも違う『モッ、モッ』って訳の分からん擬音での表現だけれどもフレームとハンドルで振動を吸収?分散?してるので自分の体にはあまり振動が来ない。
ヒルクライム用の車体のハンドルバーはアルミだが、今回使ったカーボンハンドルはポジションも合うのでヒルクライム用のもコレに換える予定。腕を乗せるハンドル上部もやはりフラットになっていると腕とバーが点接触じゃなく面接触となり、滑らないのでやっぱ楽。
------------------
斉の森交差点から上り開始。距離2.4㎞、平均勾配7.5%。
心拍数が170~と上がって真面目に上るけど、やっぱ重い。。。
ヒルクライムシーズンでの練習走行ならココはチェーンリングアウターで上ってるが、今日は早々にインナーへ落っことし…あ、この車体にはパワーメーターは付いてません
------------------
最初の坂区間を上って姨捨駅前の平坦部で脚を休ませ展望台までの上り 距離0.9㎞ 8~17%の勾配 平均勾配11%の区間へ。
ここは普段ならフロントチェーンリングアウターで上り始め、半分くらいまで行ったらインナーに落とす。だけど、今日は最初っからインナーで上り始め。
『えっほ、えっほ』踏んでも普段よりどうにも遅いが、それでも踏めば進んでる。(空回ってる感、力が下方向に吸われてる感は無く、前に進んでる)
フロントはインナーに落としてはいるけど、スプロケの方は重いギヤにしていつものようにダンシングで行ってみる。自分はあまり車体を左右に振ったりフロントをこじったりなダンシングはしてないと思うけど、体重70㎏近い人間が17%位の勾配でダンシングしてもBBから『パキ、パキ』音がしたり、ブレーキパッドとディスクローターが擦れて『シャリ、シャリ』鳴ったりはしない。それなりに丈夫には組んであります。
千曲川展望台に到着ー。(…止まって休憩はしないから写真は無いよ)
『ま、予想通りリムブレーキのヒルクライム用の車体みたいに走る』って訳もなく、タイムも出ないわな。(この時期、このコンディションでタイム出てたらヤバいが)
------------------
『ポジションはこれで良さそうだなー』ってことで帰ってバーテープを巻く。
------------------
で、別の日の話になるけど『じゃあ、雪が無いって所で茶臼山でも上ろうか』と。
茶臼山へ。信里小か川カンへ行くかで分岐するY字の先の所がいつも日当たりが悪いのでそこが霜が残ってるようならそこまでって事でスタート。
普段なら動物園の有る表側ならフロントアウター縛りでイケるけど、今回は中間の材木所~宅老所の辺でインナーに落とす。そこを通過後は動物園手前のストレートの所で再度アウターに入れ、路面状況も悪くなかったので頂上の信里小まで。
下の火の見やぐらまで下ってきてUターンしておかわり。2本目は(速度は全く出ないものの)アウター縛りで上まで行けた。『おぅふ。2本目で疲れてるはずなのにそれでもなんとか踏んでいけるんじゃん』っと。
下り走行中は軽いギヤでクランク回してクランクのグリス飛ばしで。ある程度回転部も馴染んできたので帰りの平坦路は組んだ直後に比べてかなり回りも軽くなったな。
------------------
ちょいっと乗ってみてのディスクロードの感想としては・・・
〇『ジャンルを細かく分けなきゃダメなのかなー』と。
ロードバイク(っぽい)所からシクロクロス、グラベルロードと分かれたように『ロードバイクのヒルクライム向けのリムブレーキ車』と、『ロードバイクのロードレース、ロングライド向けディスクブレーキ車』ってふうに別物として分けなきゃなのかと。
ヒルクライム(レース)として考えると、『ヒルクライムレース』ってのが上り坂を走って上りきるタイムを競うレースなので、以前書いた通りどうにも上ってるレース走行中は(基本的に危険回避をする時位しか)ブレーキをかけないからディスクブレーキの恩恵がはっきり言って全く無い。『雨の時でもよく効くディスクブレーキ』っていっても雨のレースでもそもそもブレーキをかける事が無いのでそれもメリットにならない。レース終了後の下山はゆっくり下れば良いだけの事。
(細かくいうと自分の出てるヒルクライムレースだとツール・ド・美ヶ原ではスタートして最初信号を右折する時や、17㎞過ぎに下り区間があるのでそこら辺はブレーキはかける)
『ヒルクライムの上りだけじゃなくて下りもあるロードレースで(またはロングライド等で)走るので下りで楽に走って体力を回復させたい、下りでアタックしてタイム稼ぎたい』って状況で走るならディスクかと。
------------------
『(このメーカーの)このモデルが乗りたい!』って決めてるならそれがリムブレーキでもディスクでも構わずいっていいと思う。行けばわかるさだけど、リムブレーキかディスクかで迷ってる人なら『自分はその車体を買ったら何処をどんなふうに走るのか』を考えて。
現状だとリムブレーキ仕様とディスクブレーキ仕様の両方を出してるメーカーもありますが、『ヒルクライムレースメインでタイム出す(他の人と競る)のを目標にしたい』ってなら軽量化の沼にどっぷり浸かってしまい抜け出せなくなると最終的には『1g削るに○○千円かけました。インナーワイヤーのエンドキャップを使わず0.3g軽量化』等の言葉が普通に出るようになります。その場合にはディスクブレーキシステムは重量物以外の何物でもありません。(というか多分そこまで行く前にディスク車体を売り払ってリムブレーキ車体を再購入してるはず)
『ヒルクライムレースだけじゃなくて、1台の車体で色々やりたい』ってなら登坂能力は落ちるのを覚悟でディスクもアリ。(それでも速い人は速いが…)
自分も実際乗ってみて『山でもタイム出す走りじゃなきゃ上ることは出来る』ってのは色々実証済み。それに下り走行で指の第二関節までの力でブレーキコントロールできるのは楽。
『ヒルクライムの練習ー』じゃなくて『上り下りのあるルートを走るー』ってならディスク車で多分行くよ。
------------------
販売サイド的にどうしてもディスクロードを広めたいならヒルクライムレースでなら『ディスクブレーキ クラス』を作るしかないのでは?最低重量を(例えば6.8㎏とかに)設定して、『それより軽いディスク車はリムブレーキ クラスで走って下さいねー。』ってするとかは必要だと思うけど…
『下りではディスクブレーキの方がメリットが有る』からと言って、下りもあるロードレースにしちゃうとコースの確保も難しいし、下りで落車事故起きまくって『自転車自体が危ない物』と決めつけられる…かといって平坦基調のクリテリウムを新たに開催するとなると出来る場所(道)の確保が難しい…サーキットコースを借り切るだと開催場所が限られる…
どうしてもこっち(ヒルクライムレース)寄りな意見になってしまうけど、ヒルクライムレースメインで走ってる人なら『ヒルクライムレース用の車体として、タイム出しに行くならリムブレーキとディスク、両方の仕様が有ったらどっち買う?』って聞かれたらやっぱ現状ならまだリムブレーキを選ぶでしょ。
どこかがどこかに圧力かけてリムブレーキの車体やパーツを出さなくさせない限りはまだリムブレーキには乗れるしね。
ヒルクライムっていう一つのジャンル、『上ったら終わり』って特殊な走行状況だからやっぱそうなるんじゃないかな。
昨日(1/24)の大相撲 十三日目の炎鵬は上手い足取りからの押しだった。
155㎏の相手を持ち上げてるように見えるけど、そうじゃなくて相手の片足を取って、相手がケンケンして宙に浮いてるところを斜めから押すっていう絶妙なタイミング。相手が自らを宙に浮かせてるので相手の力を利用しての押しっていう。それに押しに行っても炎鵬は両足をしっかり土俵の中に残してる。全力でも冷静。
今日のは大栄翔の下に潜れず距離を取られ、土俵際でも押しに来る相手の勢いを利用して回って回ってだったけど突かれ負け。それでも最後の最後まで粘る土俵際は勝ちでも負けでも『ん――!おお~!!』っと見てると思わず声が出る。
それに比べ土俵際に押されたら上体を起こして背中伸ばしてたらダメなんじゃないか?御嶽海…
------------------
さて、さて、さて、順番的には前回でハンドル、レバーの組立が終わってるけど、今回はSTIレバーの方を。
今回組んだSTIレバーはST-R8020。油圧ブレーキで機械式変速。
訳アリの新車取り外し品で訳ってのが5㎜以下の小さなキズがあった物って事で定価の半額位で購入。
シクロクロスの方で油圧ブレーキレバーST-RS685を使っているけど、685は初期モデルってことで、重かったり大きかったり。
ST-RS685の実測重量。カタログ値では左右ペアで649gってなってる。
ちなみの同年のリムブレーキ用機械式レバーST-6800はペアで425g。
油圧だとレバーだけで224g重いって事になる。
ちなみの同年のリムブレーキ用機械式レバーST-6800はペアで425g。
油圧だとレバーだけで224g重いって事になる。
ST-R8020の実測。カタログ値ではペアで554gとのこと。
色々と仕様変更されていて、まずブレーキホースとレバー本体の連結のボルト。
左がST-RS685のボルトでブレーキキャリパーやマウンテン用のレバーの連結ボルトと共通品だったが、右側のフランジボルトに変わってる。スペーサーも追加されてる。ボルトのサイズ、ネジピッチが違うため互換性はありません。
ブレーキオイルを補充するフタになるボルト。ここもネジサイズが変わっていて、エア抜き作業をする際にブリーディングキット(下の画像で右側のじょうご状のもの)に追加で延長アダプター(マニュアルだとファンネルアダプター)を付けないとオイルがダダ漏れ。
他にも調整ネジの位置が変わってたり。
ファンネルアダプターは購入しとかないとエア抜き作業が出来ないので注意。
------------------
組立作業的には新旧モデルで大きく変わってる所は無いが、ちょこっと注意する点といえば、まずホースにインサートコネクターを入れる所、バイスに挟んで打ち込む場合
インサートコネクターを打ち込んだ後でもオリーブは抜くことが出来るのでバイスを開放する前にオリーブは外しときましょう。
オリーブを外さずにバイスを開放してしまうとホースの巻きぐせが戻る力でバヒューンとオリーブが吹っ飛んでいきます。
------------------
ブレーキホースがハンドルバーに内装する場合、レバーとホースの連結作業をする時はハンドルバーにはレバー本体を取り付けずに連結作業をした方が組込ミスが防げるかと。(マニュアルだと内装じゃないハンドルバーに添わせる場合でのみ説明されてますが)
こんな感じでレバー側と接続しますが
マニュアルにも書いてある通り、ホースを真っすぐ押し込みながら最初は工具を使わず手で連結フランジボルトを締めこまないとホースが確実に一番奥に入っていなかったり、オリーブが斜めになった状態でもフランジボルトは締込出来てしまうため、ちゃんと締めこんだつもりでもオイルを入れて握るとオイル漏れになります。(一番最初に一度やらかしました)

『オイルが漏れてきてるから』とそこで増し締めしてもオイル漏れは止まりません。ボルトを外して再組付けになります。その際一度使ったオリーブは再使用できません。一度締め付けてオリーブに締め付けスジが入っているとそこからオイル漏れします。オイル漏れを止めるつもりで無理矢理強く締め込むとネジ山が当然ナメて終わりです。
ブレーキホースは固いのでバーに内装する時にはレバーは取り付けてない方がホースを真っすぐ押し込みやすいと思います。ブレーキキャリパー側もキャリパー本体を車体に取り付けてない方がやっぱりホースを押し込みやすいかと。
------------------
チョイっと走ってレバーの取付位置が決まったためバーテープは巻いた。ゴムゴム的にグリップするのが好みなので今回はリザードスキンの1.8㎜に。
また、あるものを使ってブレーキホース、シフトアウターの色はブラックではなく色付き(赤にしたかったが若干ピンク寄り)にしてます。