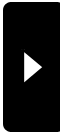寒い・・・
結局、金、土曜日に降雪は無く、(それでも『長野市(の山間部)は土曜日に初雪を観測。』となったようだけど。)『もしかしたら今朝は起きたら湿った雪で屋根が真っ白になってるんじゃないか』と思っていたがそれも無かった。
CATVの道路Live映像を見ていると、信州新町や飯綱の方の普光寺の辺では雪が舞っていて、北の方は古間や信濃町ICは白い。もうじき市街地にも来るかねぇ・・・
今回はケーブルの処理なんかを。
ハンドル周りのケーブル取り回しが決まって、フレームにケーブルを入れていくけれど、まずR用のシフトケーブルアジャスターの取付。
シフトケーブルアジャスターはこの向きで取付て、上側のアウターケーブルとの接続部は熱収縮ホースで防水処理。
以前にも少し書いたけれど、アジャスターはこの向きの方が防水性能が高いと思う。
アジャスターの構造はこんな感じ。(※シフトアジャスターが2個無かったので、この辺の写真のはブレーキケーブル用のアジャスターです。シフト用より太い)
(シマノパーツで)ロードシフトレバー(STIレバー)で機械式のディスクにする場合はケーブル途中の、走っている時でも操作可能な位置にアジャスターを組み込んで下さい。そうしないと停車して工具を使わないと微調整が出来ません。(テクトロとかの機械式ディスクには工具を使わず回せるアジャスターが付いてるのも有ったような?)
(リムブレーキの)キャリパーブレーキだとブレーキ本体に工具を使わず微調整が出来るアジャスターが付いていますが、ディスクブレーキはホイール中心寄りにブレーキ本体が有るため乗車状態だと手が届かないってのもあります。
文字、写真が小さくて見づらいかもしれませんが、


実際にアジャスター部分をそれぞれの向きで組んで上側を熱収縮ホースで防水処理して、上の方をビニール袋で覆って水を入れてみると違いが有る。
左の方は水が浸入して下のケーブル内部をつたって水が流れてるが、右側は水の浸入を防いでいる。
実際にここまで水に浸かるってことは無いけれど、シクロクロスでの走行後は水道で水をジャバジャバかけて洗車するのでアジャスターの向きを変えて組むだけでも防水効果はあるって事で。
ただ、アジャスター内部のOリングがヘタってると浸水しやすいし、そもそもがこのOリングは防水が第一目的ではないと思うので。緩み防止(カタカタ音防止)と防塵?
こういう風にアジャスター本体にかぶせるように熱収縮ホースを取り付けて防水って方法もあるけど。(若干アジャスターの回りが渋くなるが)
シフトインナーワイヤーは普通のステンレスワイヤーで組込。純正状態でコストダウンのために鉄のインナーワイヤーで組んであるものは錆びる前に交換しときましょう。錆があった時はアウターワイヤーもセットで交換を。
今はどこまでバージョンアップしたかはわからないけど(茶色かったり緑色になったりの)、なんとかコーティングしてあるあのケーブルは部品の付属で付いてきた最初だけ使ったが、ケーブルが毛羽立って動きが悪くなるのでその後は使ってない。
逆に軽くなるという噂の日泉ケーブルは使ってみたかった。
BB下周り。
ブレーキ、シフトケーブルが一旦BB下付近で車外に出るが、ケーブル出入り口はコーキングして防水(レバー側の上の方も防水処理済)。TCXだとチェーンステー下に(スタンドかサイコンのセンサーを付けるための?)埋め込みナットが2個あったが、それも使わないので塞ぐ。
BB下の水抜き穴。ここに糸を通す。
糸の結び目には瞬着(瞬間接着剤)を付けて緩みを防止。
『何のために?』っていうと・・・フレーム内部、BB下に溜まった水を抜けやすくするため。水抜き穴付近の水の表面張力を壊す目的。
一応、糸をつたって水が落ちて来るが、おまじないレベルな事かも・・・
今回はここまでー
結局、金、土曜日に降雪は無く、(それでも『長野市(の山間部)は土曜日に初雪を観測。』となったようだけど。)『もしかしたら今朝は起きたら湿った雪で屋根が真っ白になってるんじゃないか』と思っていたがそれも無かった。
CATVの道路Live映像を見ていると、信州新町や飯綱の方の普光寺の辺では雪が舞っていて、北の方は古間や信濃町ICは白い。もうじき市街地にも来るかねぇ・・・
------------------
今回はケーブルの処理なんかを。
ハンドル周りのケーブル取り回しが決まって、フレームにケーブルを入れていくけれど、まずR用のシフトケーブルアジャスターの取付。
シフトケーブルアジャスターはこの向きで取付て、上側のアウターケーブルとの接続部は熱収縮ホースで防水処理。
以前にも少し書いたけれど、アジャスターはこの向きの方が防水性能が高いと思う。
------------------
アジャスターの構造はこんな感じ。(※シフトアジャスターが2個無かったので、この辺の写真のはブレーキケーブル用のアジャスターです。シフト用より太い)
(シマノパーツで)ロードシフトレバー(STIレバー)で機械式のディスクにする場合はケーブル途中の、走っている時でも操作可能な位置にアジャスターを組み込んで下さい。そうしないと停車して工具を使わないと微調整が出来ません。(テクトロとかの機械式ディスクには工具を使わず回せるアジャスターが付いてるのも有ったような?)
(リムブレーキの)キャリパーブレーキだとブレーキ本体に工具を使わず微調整が出来るアジャスターが付いていますが、ディスクブレーキはホイール中心寄りにブレーキ本体が有るため乗車状態だと手が届かないってのもあります。
文字、写真が小さくて見づらいかもしれませんが、


実際にアジャスター部分をそれぞれの向きで組んで上側を熱収縮ホースで防水処理して、上の方をビニール袋で覆って水を入れてみると違いが有る。
左の方は水が浸入して下のケーブル内部をつたって水が流れてるが、右側は水の浸入を防いでいる。
実際にここまで水に浸かるってことは無いけれど、シクロクロスでの走行後は水道で水をジャバジャバかけて洗車するのでアジャスターの向きを変えて組むだけでも防水効果はあるって事で。
ただ、アジャスター内部のOリングがヘタってると浸水しやすいし、そもそもがこのOリングは防水が第一目的ではないと思うので。緩み防止(カタカタ音防止)と防塵?
------------------
こういう風にアジャスター本体にかぶせるように熱収縮ホースを取り付けて防水って方法もあるけど。(若干アジャスターの回りが渋くなるが)
------------------
シフトインナーワイヤーは普通のステンレスワイヤーで組込。純正状態でコストダウンのために鉄のインナーワイヤーで組んであるものは錆びる前に交換しときましょう。錆があった時はアウターワイヤーもセットで交換を。
今はどこまでバージョンアップしたかはわからないけど(茶色かったり緑色になったりの)、なんとかコーティングしてあるあのケーブルは部品の付属で付いてきた最初だけ使ったが、ケーブルが毛羽立って動きが悪くなるのでその後は使ってない。
逆に軽くなるという噂の日泉ケーブルは使ってみたかった。
------------------
BB下周り。
ブレーキ、シフトケーブルが一旦BB下付近で車外に出るが、ケーブル出入り口はコーキングして防水(レバー側の上の方も防水処理済)。TCXだとチェーンステー下に(スタンドかサイコンのセンサーを付けるための?)埋め込みナットが2個あったが、それも使わないので塞ぐ。
BB下の水抜き穴。ここに糸を通す。
糸の結び目には瞬着(瞬間接着剤)を付けて緩みを防止。
『何のために?』っていうと・・・フレーム内部、BB下に溜まった水を抜けやすくするため。水抜き穴付近の水の表面張力を壊す目的。
一応、糸をつたって水が落ちて来るが、おまじないレベルな事かも・・・
今回はここまでー
さて、さて、さて、ボチボチ細かなパーツが集まってきたのでTCXの組立をね。
TCX SLRは純正状態だとブレーキシステムがGIANTでは『コンダクト』システムってのを採用していて、『(STIの)ブレーキは機械式のワイヤーブレーキで、ステムの部分で機械式作動を油圧に変換する』というシステムのため、『ブレーキキャリパーは油圧式で効きを確保して、レバーはコストを抑えた機械式』という状態になっている。
ステムヘッド部の平たくなっている部分(ハンマーヘッド的な?)に横からブレーキワイヤーが入り、下向きに油圧ホースに変更されて出ている。
純正のケーブル取り回しはこんな感じ。
2018年モデルとなるのか、フロントギアがダブルのモデル。ダウンチューブ上から前後シフトワイヤーが2本フレームに入り、ダウンチューブ左横から後ブレーキホースが入る。
フロントギアがシングルになった2019年モデル。シフトワイヤーが1本になった以外は取り回しは変わってない感じ。
で、今回組み立ててるのはコンダクトシステムではなく、ノーマルステム。
今まで乗っていたGTからコンポは乗せ換えで、シフトレバーはST-RS685。純正の取り回しを参考にして仮組し始めたが、なんかイマイチしっくりこない。
●コンダクトシステムだとブレーキホースがステムの所で真下に出るため、普通のホースで取り回そうとするとステムの下でちょいホースを長めに余らせないと上手くいかない。
●そもそもの車体設計が『右ブレーキレバーで後ろブレーキ操作する』としている為か?ダウンチューブの(自分が乗車した状態で)左側にしかブレーキを通す穴が無い。日本人向けに多い『右ブレーキレバーが前ブレーキ、左が後ろブレーキ』の取り回しだと右にいっぱい切った状態で後ろホース長を決めると、逆の左に切った時にホースが余り気味に。
ほぼ全部黒いので(車体色がマットブラックな所にメーカーロゴまで黒っていう)何だかわかりにくい(『キャラが立ってないんだよ!』)けどこっち(左)側にしか穴が開いてない。右側にも穴が開いてれば良かったんだが。
まずこの二つ。
・・・とりあえずそっちをどうするか考えながら一番取り回しを決めやすい(右レバーで操作する場合の) 前ブレーキからやろうかと。
Fフォークにはタイラップでホースを束ねるための金具(輪っか)が有るのでそれに合わせてFフォークの後ろに添わせるようにしたが・・・
『?・・・左にハンドルを切るとかなりフレームに前ブレーキホースが当たるんだけど・・・』
普段走ってる時ならここまでハンドルを切ることは無いんだけれども、(キャリパーブレーキのロードなら右にいっぱいハンドル切ればブレーキアジャスターがフレームに当たったりもするが…)『それでもなー』って事で、Fフォークの前に添わせるように取り回し。
ホース前回しだと左いっぱいにハンドルを切ってもなんとか当たらず。
前ブレーキの取り回しが決まったんで、後ろシフトワイヤーはダウンチューブ上から入れるより本来ブレーキを通すフレーム横から通した方がケーブルの曲がりが緩やかなのでフレーム横から。シフトケーブルアジャスターも上の写真の位置のフレーム横に決定。
左レバーから出る後ろブレーキホースはヘッドパイプの右から通し、本来シフトワイヤーを通すダウンチューブ上からフレームに入れるに決定。
とりあえず決まり。(バーテープ巻くのは試走してみてからで)
左いっぱいにハンドル切った時でこんな感じ。これ以上ホース長を短くするとヘッドパイプの所に結構擦れる。
次回に続く・・・
さて、さて、さて、シクロクロスミーティングの上山田ラウンドが終わって(って、またレース当日は晴れて、週明けの月曜日は雨降ってたような?) 天気予報だと『週末は雪』っていうから車のタイヤをスタッドレスに交換を。
いつもの年なら11月の末でスタッドレスに履き替えてたが、今年は12月だというのに20℃超えの気温になって、それで次は雪ってホントに雪が降るくらいまで気温が下がるのか?(今も雨が降ってるけど、生暖かい気温だが・・・)
タイヤ交換はウチにコンプレッサーや(なくても出来るけどやっぱりインパクトは有れば楽)工具は有るので自分で。
車のホイールでのチョイネタ。
タイヤ交換してるのは仕事で使ってる業務用のワンボだけれども、ホイールナットは純正は貫通式のナットを採用しているが、袋ナットに交換してある。
袋ナットに交換しておくと塩カルなどでナットやハブボルトが錆びる事が無い為。
また、自分はナット(ネジ部)に油塗って締める派。油はネジの部分だけに極少量付けるだけ。ナット座面には付けない。付けないが座面はホイール側もパーツクリーナーで綺麗に拭いてから取付。大量にグリスを付けたり、ナット座面に付けるとブレーキディスクに油分が付くので。(しかしこの車は後ろブレーキはドラムなのでそこまで神経質にならんでいいけど。)
袋ナットに交換+ネジ部にグリス付けてでやってれば実際、ハブボルトには一切錆は無いし、上の写真でもナット座面は綺麗なままで錆は無し。(5年は使ってるはず)
春先にノーマルタイヤに履き替えようとして塩カルで錆びたハブボルトを緩めようとして『ボキッ!!』と折った人はいませんか?もしくは業者に頼んだ後、車を取りに行ったらハブボルトが1本だけ新品になってたとか。(作業時間を短くしようとして、インパクトレンチで強トルクで一気に緩めようとするとやっぱり『ボキッ!!』と折れる。)
袋ナットはホームセンターでも売ってるのでスチールナット(鉄製ナットだと20個一台分で¥2,000~位か?軽量なアルミナットも有るけど冬での使用はお勧めしません。塩カルでやられる)に交換しとくと防げます。
※車種によってハブボルトの太さ、ピッチ、使用するナットの個数が違い、社外ホイールに替えている場合等埋め込みナットの場合はナットの二面幅に注意しないと(ボルト径が同じでもナットの二面幅が17㎜幅のが有ったり21㎜幅のがあったりする)『ナットがデカ過ぎて工具(ソケット)が入らなくて締め付けできねー!』なんて事が有るので。
で、こっち。シクロクロスの乗り換えフレームTCXの方。
STDとは異なるケーブルルーティングで仮組中。
Fハブはクイックから15㎜スルーアクスルになるけど、どうやら今までのホイールはアダプター変更は出来ないホイールがある。
今年の本番用として組んだ赤ハブがメーカー名が不明な為、変換アダプターが無い。(試しでTNIの旧型アダプターを取り寄せたが駄目だった)今年走りが良かったのは(油圧)ブレーキ、(チューブレス)タイヤと組んだホイールが上手くいったからだと思ってたんだが…
以前書いた『シクロクロス車で舗装路走る用の前輪を組んだ』ってのがコレで↓
とあるシクロクロス完成車に使っていたハブを貰ったもの+別のリムで組んだ前輪。ハブはDTのおそらく一番安い(完成車用なのでハブ単体の販売はないのかもdb24スプライン?だったか?)
これはアダプターも付属してたので交換した。(DTのアクスル変換アダプターは買うと約¥5,000するん!)
他の車輪も使い勝手は悪くなるがアルミのカラーをワンオフで作ってもらえば今までのホイールはベアリングの内径がφ15㎜なので引き続き使うことも出来るけど、ワンオフだとアルミのカラー1個で¥2~3000とかするので(そう考えるとDTのアダプターの値段もまぁねー・・・TNIは¥1,200位だったが。)車輪1つにつきカラー2個を製作するよりTNIのディスクハブで組み直そうかと…
次回からは『冴えないシクロの作り方』が始まるかもしれない
いつもの年なら11月の末でスタッドレスに履き替えてたが、今年は12月だというのに20℃超えの気温になって、それで次は雪ってホントに雪が降るくらいまで気温が下がるのか?(今も雨が降ってるけど、生暖かい気温だが・・・)
タイヤ交換はウチにコンプレッサーや(なくても出来るけどやっぱりインパクトは有れば楽)工具は有るので自分で。
車のホイールでのチョイネタ。
タイヤ交換してるのは仕事で使ってる業務用のワンボだけれども、ホイールナットは純正は貫通式のナットを採用しているが、袋ナットに交換してある。
袋ナットに交換しておくと塩カルなどでナットやハブボルトが錆びる事が無い為。
また、自分はナット(ネジ部)に油塗って締める派。油はネジの部分だけに極少量付けるだけ。ナット座面には付けない。付けないが座面はホイール側もパーツクリーナーで綺麗に拭いてから取付。大量にグリスを付けたり、ナット座面に付けるとブレーキディスクに油分が付くので。(しかしこの車は後ろブレーキはドラムなのでそこまで神経質にならんでいいけど。)
袋ナットに交換+ネジ部にグリス付けてでやってれば実際、ハブボルトには一切錆は無いし、上の写真でもナット座面は綺麗なままで錆は無し。(5年は使ってるはず)
春先にノーマルタイヤに履き替えようとして塩カルで錆びたハブボルトを緩めようとして『ボキッ!!』と折った人はいませんか?もしくは業者に頼んだ後、車を取りに行ったらハブボルトが1本だけ新品になってたとか。(作業時間を短くしようとして、インパクトレンチで強トルクで一気に緩めようとするとやっぱり『ボキッ!!』と折れる。)
袋ナットはホームセンターでも売ってるのでスチールナット(鉄製ナットだと20個一台分で¥2,000~位か?軽量なアルミナットも有るけど冬での使用はお勧めしません。塩カルでやられる)に交換しとくと防げます。
※車種によってハブボルトの太さ、ピッチ、使用するナットの個数が違い、社外ホイールに替えている場合等埋め込みナットの場合はナットの二面幅に注意しないと(ボルト径が同じでもナットの二面幅が17㎜幅のが有ったり21㎜幅のがあったりする)『ナットがデカ過ぎて工具(ソケット)が入らなくて締め付けできねー!』なんて事が有るので。
------------------
で、こっち。シクロクロスの乗り換えフレームTCXの方。
STDとは異なるケーブルルーティングで仮組中。
Fハブはクイックから15㎜スルーアクスルになるけど、どうやら今までのホイールはアダプター変更は出来ないホイールがある。
今年の本番用として組んだ赤ハブがメーカー名が不明な為、変換アダプターが無い。(試しでTNIの旧型アダプターを取り寄せたが駄目だった)今年走りが良かったのは(油圧)ブレーキ、(チューブレス)タイヤと組んだホイールが上手くいったからだと思ってたんだが…
以前書いた『シクロクロス車で舗装路走る用の前輪を組んだ』ってのがコレで↓
とあるシクロクロス完成車に使っていたハブを貰ったもの+別のリムで組んだ前輪。ハブはDTのおそらく一番安い(完成車用なのでハブ単体の販売はないのかもdb24スプライン?だったか?)
これはアダプターも付属してたので交換した。(DTのアクスル変換アダプターは買うと約¥5,000するん!)
他の車輪も使い勝手は悪くなるがアルミのカラーをワンオフで作ってもらえば今までのホイールはベアリングの内径がφ15㎜なので引き続き使うことも出来るけど、ワンオフだとアルミのカラー1個で¥2~3000とかするので(そう考えるとDTのアダプターの値段もまぁねー・・・TNIは¥1,200位だったが。)車輪1つにつきカラー2個を製作するよりTNIのディスクハブで組み直そうかと…
次回からは『冴えないシクロの作り方』が始まるかもしれない
朝の気温がいよいよ市街地でもマイナスになって、明日の天気予報でも『雪になるかも』となったのでボチボチロードは冬眠かと。
それでも自分で去年書いたのを見ると、去年は11月20日頃に長野市街地でも雪が降っていたのでやっぱり今年はまだ暖かいか。
ここの所はシクロクロスの方にばかり乗っていたのでもうほぼロードは固定ローラー仕様になってた。

地面に汗が落ちる位は乗ってる。音楽聞きながらやってないと飽きちゃうけどね。。。

そしてシクロクロスの方も次戦の上山田まであと1週間ほど。また本番用にして慣らし練習をしてくか・・・
で、タイヤ。チューブレスはやっぱりチューブ入りよりエア圧を落とせるので、良い感じ。(といっても自分の入れてるエア圧はベテランの人からすれば『そんなに(エア)入れてんの!』と思われるかも。それでもチューブ入りの時よりもはるかにエア圧を下げて走れてる)
飯山での試走の際に木の根っこなどを超えた時に結構な衝撃が有ったのでリムが危ないと思って試走時間中にエア圧上げて調整してた。あれはチューブ入りのタイヤなら間違いなくリム打ちパンクやってたと思う感じ。路面もドライに移行してったこともある。(体重も有るし…)

今回から使い始めたIRC SERAC CX クロスガード、『次も使うならこれかなー』と思っているけど、このSERAC CX、買おうとすると結構、商品が分かりづらい。
まず、『SERAC CX』というシリーズ?で走行コースに合わせてタイヤブロックパターンが
●無印
●SAND
●MAD
●EDGE(EDGEは最近追加になった?)
と4種有り、それぞれのタイヤパターンの中で
●ノーマルタイヤサイドのチューブレス
●タイヤサイド面を強くしてあるクロスガード チューブレス
●物によってはチューブ使用前提でのチューブレスではないクリンチャータイヤ(普通にチューブレスタイヤにチューブ入れて使うんじゃダメなのか?)
と一つのタイヤパターンの中でも2、3種類有るので買おうと思ってる人は注意して。
『他のトコに比べて安いから。』って買ったらチューブレスじゃ無かった。クロスガードじゃなかったから使ってたらタイヤサイドが直ぐ切れた。なんて事にならないように。
使わなくなってた車・バイク用(米式バルブオンリー)のエアゲージ本体と自転車用のフレンチバルブ用のポンプヘッド(¥900)をニコイチにして低圧タイヤゲージを。。。
一般自動車・バイクのエアゲージだとMAX400kpa位のスケールなので自転車の低圧用(おおよそ2気圧(200kpa)近辺が見れればシクロ的、自分的にはOK)としてなら使えるかと。
『誤差が出るんじゃ…』とは言ってもそもそも『じゃあ、どこのメーカーのメーター(ポンプ)なら誤差が無いの?』って話になるし、フレンチバルブでポンプヘッドをセットする時、外す時にもわずかにエアが漏れたりするから、それも誤差に繋がるかもしれないしね…
エア抜きバルブが付いているので、もう『少し多めに入れて、抜いてこのメーターで見て○○kpaにして合わせてく』という使い方で。
ネット記事でこの前の野辺山で走行していた(エリートクラスのトップ選手の)車体が出ていたけど、カーボンフレームだけどシフトは機械式だったり、アルミフレームだったり、機械式の旧型コンポメインだったりと、必ずしも全てが最新式のものでなかったりしてて色々面白い。
明日は雪か雨だったら久々に砂埃が舞わないにゅるにゅる路面が走れるぜ・・・
車のタイヤもそろそろスタッドレスの準備をしないとな。
それと明日の夜は長野で恵比寿講の花火だったな。
それでも自分で去年書いたのを見ると、去年は11月20日頃に長野市街地でも雪が降っていたのでやっぱり今年はまだ暖かいか。
----------------
ここの所はシクロクロスの方にばかり乗っていたのでもうほぼロードは固定ローラー仕様になってた。
地面に汗が落ちる位は乗ってる。音楽聞きながらやってないと飽きちゃうけどね。。。
----------------
そしてシクロクロスの方も次戦の上山田まであと1週間ほど。また本番用にして慣らし練習をしてくか・・・
で、タイヤ。チューブレスはやっぱりチューブ入りよりエア圧を落とせるので、良い感じ。(といっても自分の入れてるエア圧はベテランの人からすれば『そんなに(エア)入れてんの!』と思われるかも。それでもチューブ入りの時よりもはるかにエア圧を下げて走れてる)
飯山での試走の際に木の根っこなどを超えた時に結構な衝撃が有ったのでリムが危ないと思って試走時間中にエア圧上げて調整してた。あれはチューブ入りのタイヤなら間違いなくリム打ちパンクやってたと思う感じ。路面もドライに移行してったこともある。(体重も有るし…)
今回から使い始めたIRC SERAC CX クロスガード、『次も使うならこれかなー』と思っているけど、このSERAC CX、買おうとすると結構、商品が分かりづらい。
まず、『SERAC CX』というシリーズ?で走行コースに合わせてタイヤブロックパターンが
●無印
●SAND
●MAD
●EDGE(EDGEは最近追加になった?)
と4種有り、それぞれのタイヤパターンの中で
●ノーマルタイヤサイドのチューブレス
●タイヤサイド面を強くしてあるクロスガード チューブレス
●物によってはチューブ使用前提でのチューブレスではないクリンチャータイヤ(普通にチューブレスタイヤにチューブ入れて使うんじゃダメなのか?)
と一つのタイヤパターンの中でも2、3種類有るので買おうと思ってる人は注意して。
『他のトコに比べて安いから。』って買ったらチューブレスじゃ無かった。クロスガードじゃなかったから使ってたらタイヤサイドが直ぐ切れた。なんて事にならないように。
----------------
使わなくなってた車・バイク用(米式バルブオンリー)のエアゲージ本体と自転車用のフレンチバルブ用のポンプヘッド(¥900)をニコイチにして低圧タイヤゲージを。。。
一般自動車・バイクのエアゲージだとMAX400kpa位のスケールなので自転車の低圧用(おおよそ2気圧(200kpa)近辺が見れればシクロ的、自分的にはOK)としてなら使えるかと。
『誤差が出るんじゃ…』とは言ってもそもそも『じゃあ、どこのメーカーのメーター(ポンプ)なら誤差が無いの?』って話になるし、フレンチバルブでポンプヘッドをセットする時、外す時にもわずかにエアが漏れたりするから、それも誤差に繋がるかもしれないしね…
エア抜きバルブが付いているので、もう『少し多めに入れて、抜いてこのメーターで見て○○kpaにして合わせてく』という使い方で。
----------------
ネット記事でこの前の野辺山で走行していた(エリートクラスのトップ選手の)車体が出ていたけど、カーボンフレームだけどシフトは機械式だったり、アルミフレームだったり、機械式の旧型コンポメインだったりと、必ずしも全てが最新式のものでなかったりしてて色々面白い。
----------------
明日は雪か雨だったら久々に砂埃が舞わないにゅるにゅる路面が走れるぜ・・・
車のタイヤもそろそろスタッドレスの準備をしないとな。
それと明日の夜は長野で恵比寿講の花火だったな。
ここのところ、急に気温が下がるようになって昼は20℃以下になり、朝は下がれば5℃近くといよいよ冬が来るか来ちゃうのか…
そしてシクロクロス CCMシリーズ戦の第3戦、第4戦の飯山ラウンドまであっという間にあと1週間ほど。(第3戦は11/3 土曜日の夕方位からのナイターレース、第4戦は11/4 日曜日の朝からのレース。共に飯山市運動公園(長峰運動公園)で2日間連続で開催される)
土日連休はちょっと…なので今回は日曜日だけの出場。
さて、さて、さて、本番も近くなって最近は朝練習してることが多いけど、気温が下がってきていつも走ってるダートコースで草が伸びてる個所が朝露か夜露で結構濡れてて走ってるとシューズがかなり濡れてしまう。


夏用シューズだと甲の部分がメッシュな為、中に水が浸みてしまうが、かといって冬用シューズを履くにはまだ早い…ということで防水ソックスを購入した。
今まではネオプレーンのインナーみたいなのを普通のソックスに上に重ねて履いていたが、シューズが若干キツくなってしまうのと、蒸れるので『他の無いかなー』と探してた。
とりあえず『何処で何というソックスを買った。』というのは細かく書かないけど、普通に通販で評価数が多く、高得点だったモノ。(多分あそこで探せば最初の方に出るはず)
開封して触ってみると、3重構造だそうで中間に防水層が入ってるらしく何か硬い感じ。履き心地は普通の冬用ソックスと変わらない感じ。
厚さは普通の冬用より若干薄いか、というところ。(モコモコ感があまり無いというかなんというか)左の黒い方が今回購入したもの。右のグレーのはこの前の乗鞍でも履いてった普通の冬用の厚手のソックス。

自分の足のサイズは約27.5㎝。参考までにシマノのMTBシューズだと43のワイド、SIDIのロードシューズ、WIREで45を履いているけど、今回購入したソックスのサイズはL。

また、商品レビューには『防水ソックスな為、洗濯後、内側を乾燥させるのに時間がかかる。』とあったので、使いまわし出来るように今回は2足セットの物を購入した。 (2足で¥4,800位。1足単品だと¥2,500位)
で、今朝走行してシューズが露で濡れたけど、ソックス内部には浸透せず、履いていて蒸れるような感じも無し。
『朝露くらいじゃ耐水テストにならんのかな?』と走行後、自転車を洗車した時にシャワーの水を上からかけてみる

それでも内部には浸透せず足は乾いてる!
『それなら』と水を張ったバケツに足首まで突っ込んでみること30秒ほど。ついでに水の中で足をバシャバシャ動かしてみる。

すると『何となく中が濡れてる感じがする』という感覚は有るけど、ソックスを脱いで足を触ってみても濡れてない。


ファーストインプレは『コレはスゲェかも!』。と驚き。
あとは洗濯しての繰り返し使用での耐久性(あまり伸ばすと生地(防水層)が傷むとの事)と真冬の雪の時での防寒性か。
洗濯が終わって触ってみると、確かに内側には水気が多い。ひっくり返して干した方がいいな。
・・・あ、シューズをバケツにドブ漬けしちゃったからずぶ濡れだ…ソックスが乾いてれば防水するからまぁいいか…
そしてシクロクロス CCMシリーズ戦の第3戦、第4戦の飯山ラウンドまであっという間にあと1週間ほど。(第3戦は11/3 土曜日の夕方位からのナイターレース、第4戦は11/4 日曜日の朝からのレース。共に飯山市運動公園(長峰運動公園)で2日間連続で開催される)
土日連休はちょっと…なので今回は日曜日だけの出場。
-------------------
さて、さて、さて、本番も近くなって最近は朝練習してることが多いけど、気温が下がってきていつも走ってるダートコースで草が伸びてる個所が朝露か夜露で結構濡れてて走ってるとシューズがかなり濡れてしまう。
上手く撮れてないけど、結構シューズが濡れてる
夏用シューズだと甲の部分がメッシュな為、中に水が浸みてしまうが、かといって冬用シューズを履くにはまだ早い…ということで防水ソックスを購入した。
今まではネオプレーンのインナーみたいなのを普通のソックスに上に重ねて履いていたが、シューズが若干キツくなってしまうのと、蒸れるので『他の無いかなー』と探してた。
-------------------
とりあえず『何処で何というソックスを買った。』というのは細かく書かないけど、普通に通販で評価数が多く、高得点だったモノ。(多分あそこで探せば最初の方に出るはず)
開封して触ってみると、3重構造だそうで中間に防水層が入ってるらしく何か硬い感じ。履き心地は普通の冬用ソックスと変わらない感じ。
厚さは普通の冬用より若干薄いか、というところ。(モコモコ感があまり無いというかなんというか)左の黒い方が今回購入したもの。右のグレーのはこの前の乗鞍でも履いてった普通の冬用の厚手のソックス。
-------------------
自分の足のサイズは約27.5㎝。参考までにシマノのMTBシューズだと43のワイド、SIDIのロードシューズ、WIREで45を履いているけど、今回購入したソックスのサイズはL。
商品パッケージ裏のサイズ表。
また、商品レビューには『防水ソックスな為、洗濯後、内側を乾燥させるのに時間がかかる。』とあったので、使いまわし出来るように今回は2足セットの物を購入した。 (2足で¥4,800位。1足単品だと¥2,500位)
-------------------
で、今朝走行してシューズが露で濡れたけど、ソックス内部には浸透せず、履いていて蒸れるような感じも無し。
『朝露くらいじゃ耐水テストにならんのかな?』と走行後、自転車を洗車した時にシャワーの水を上からかけてみる
それでも内部には浸透せず足は乾いてる!
『それなら』と水を張ったバケツに足首まで突っ込んでみること30秒ほど。ついでに水の中で足をバシャバシャ動かしてみる。
すると『何となく中が濡れてる感じがする』という感覚は有るけど、ソックスを脱いで足を触ってみても濡れてない。
裏返して内側だった方をペーパータオルに押し当てても
(写ってはいないけど、両手でソックスをペーパータオルに押し付けた)
(写ってはいないけど、両手でソックスをペーパータオルに押し付けた)
ペーパータオルは湿らない。
ファーストインプレは『コレはスゲェかも!』。と驚き。
あとは洗濯しての繰り返し使用での耐久性(あまり伸ばすと生地(防水層)が傷むとの事)と真冬の雪の時での防寒性か。
洗濯が終わって触ってみると、確かに内側には水気が多い。ひっくり返して干した方がいいな。
-------------------
・・・あ、シューズをバケツにドブ漬けしちゃったからずぶ濡れだ…ソックスが乾いてれば防水するからまぁいいか…
長野市は日曜の夜~月曜に台風が通過したが、いつもの通り?アルプスブロックが大活躍でほとんど風は無かった。合計雨量は多かったみたいだけど…
ロードの世界選手権、バルベルデ(スペイン)が勝つとは…フレッシュ・ワロンヌといい今回のコースといい、ショート激坂王だわ。この人は年を取ってる感じが無い。それどころか2017年ツール・ド・フランスの開幕TTで脚を骨折した後から逆に強くなってると思う。
フランスチームは最後の方でアラフィリップが脚が攣ってしまって脱落、ロマン・バルデに最後を託したそうだけど惜しくも2位だったのね。アラフィリップ、バルデとブエルタで調子が良かったティボー・ピノの3人が最後まで残ってたらフランスチームの誰かが勝つ…という予想だったがバルベルデ(後から知るとスペインチームも凄いメンバーで揃えてた)が一番強かったのか。
さて、さて、さて、シクロクロスの練習もやらなきゃだけど、まだロードに乗れるので練習比率は半々位でやってる。
ロードの方はちょい前に組んだRホイールでの走行を2、3回やってみて様子を見ていた。

なんせ初オフセットリム組みだったので組んだ感じからすると、左側が張れるので結線しなくてもいいのでは?という感触だったので、結線なしで走行して様子を見ることにしてた。『練習用のホイール』って前提なので重量はあまり考えずに組んだが、リムの重量が実測で557gもあった。(ま、一番安い完組ホイールのリムだから…丈夫、頑丈ということで…)完組での重量は957g(クイック、リムフラップ無し重量)

走り始めると最初の1踏み目で『キン!カキン!』と鳴るが、ちょっと走った所で止まってリムの振れを見て一ヵ所チョイとフレ取り。
平地(サイクリングロード)をシッティングで走ってる分には特に問題無し。
上り(約10㎞平均勾配5%)へ行くと『???んー?もうちょっと』という感じ。別の日に別のコース平均勾配8%ダンシングを多用するコースを走ってもやっぱり同じような感覚。ちょっと弱い感じ。だけど結線すると硬くなりすぎるんじゃないか。というような微妙なところ。
全体的にニップルをチョイ増し締めして今回の走行となったが、上りに行ってみるとかなり改善されてた。ホイール中心に芯が通ってる感じ。ダンシングで振って走っても釣り竿の穂先みたいに振った後に遅れて来るでもなく、下に力が行っちゃて空回ってる感もなくちゃんと動作についてくる。
『カシュ、カシュ』と鳴ったり、引っかかったりな(ブレーキパッドの)シュータッチも無し。
シューズの方のチョイ小技。
ロード用のシューズはSIDI WIRE SP用を使っているけど、SIDIでの部品名『ソフトインステップ』の先(矢印の所)が浮いちゃうとペダリングしてる時にクランクアームに『パチン、パチン』と当たってしまう。

『自分しか履かない。一度フィッティングしたら変えない』っていうなら短くカットしちゃってもいいかもしれない(SIDIだとこのパーツは補修パーツで購入できる)が、ドライヤーで温めて冷やしてで曲げクセをつけてやるとシューズ側面にフィットする。

シクロクロスではSPDクリート、シマノのシューズを使ってるけど、このシューズだと甲の部分がベロクロで『クロスXストラップ』って機能名でベロクロが中向き、外向きと交互になっているが、先っぽが余るとSIDIと同じようにクランクアームに当たる。こっちはカットしてた。(シューズの取説を持ってないんだけど多分カットする前提になってる?)

最近やたら来る『緊急対応!』のメールがウザい。全部無視だこんなもん。
--------------------
ロードの世界選手権、バルベルデ(スペイン)が勝つとは…フレッシュ・ワロンヌといい今回のコースといい、ショート激坂王だわ。この人は年を取ってる感じが無い。それどころか2017年ツール・ド・フランスの開幕TTで脚を骨折した後から逆に強くなってると思う。
フランスチームは最後の方でアラフィリップが脚が攣ってしまって脱落、ロマン・バルデに最後を託したそうだけど惜しくも2位だったのね。アラフィリップ、バルデとブエルタで調子が良かったティボー・ピノの3人が最後まで残ってたらフランスチームの誰かが勝つ…という予想だったがバルベルデ(後から知るとスペインチームも凄いメンバーで揃えてた)が一番強かったのか。
--------------------
さて、さて、さて、シクロクロスの練習もやらなきゃだけど、まだロードに乗れるので練習比率は半々位でやってる。
ロードの方はちょい前に組んだRホイールでの走行を2、3回やってみて様子を見ていた。
アシンメトリックリム(オフセットリム)だとバルブ穴がなんか変な所に開いてるのね。(無理矢理リムのセンターにバルブ穴を開けているというかなんというか…)
なんせ初オフセットリム組みだったので組んだ感じからすると、左側が張れるので結線しなくてもいいのでは?という感触だったので、結線なしで走行して様子を見ることにしてた。『練習用のホイール』って前提なので重量はあまり考えずに組んだが、リムの重量が実測で557gもあった。(ま、一番安い完組ホイールのリムだから…丈夫、頑丈ということで…)完組での重量は957g(クイック、リムフラップ無し重量)
--------------------
走り始めると最初の1踏み目で『キン!カキン!』と鳴るが、ちょっと走った所で止まってリムの振れを見て一ヵ所チョイとフレ取り。
平地(サイクリングロード)をシッティングで走ってる分には特に問題無し。
上り(約10㎞平均勾配5%)へ行くと『???んー?もうちょっと』という感じ。別の日に別のコース平均勾配8%ダンシングを多用するコースを走ってもやっぱり同じような感覚。ちょっと弱い感じ。だけど結線すると硬くなりすぎるんじゃないか。というような微妙なところ。
全体的にニップルをチョイ増し締めして今回の走行となったが、上りに行ってみるとかなり改善されてた。ホイール中心に芯が通ってる感じ。ダンシングで振って走っても釣り竿の穂先みたいに振った後に遅れて来るでもなく、下に力が行っちゃて空回ってる感もなくちゃんと動作についてくる。
『カシュ、カシュ』と鳴ったり、引っかかったりな(ブレーキパッドの)シュータッチも無し。
--------------------
シューズの方のチョイ小技。
ロード用のシューズはSIDI WIRE SP用を使っているけど、SIDIでの部品名『ソフトインステップ』の先(矢印の所)が浮いちゃうとペダリングしてる時にクランクアームに『パチン、パチン』と当たってしまう。
『自分しか履かない。一度フィッティングしたら変えない』っていうなら短くカットしちゃってもいいかもしれない(SIDIだとこのパーツは補修パーツで購入できる)が、ドライヤーで温めて冷やしてで曲げクセをつけてやるとシューズ側面にフィットする。
シクロクロスではSPDクリート、シマノのシューズを使ってるけど、このシューズだと甲の部分がベロクロで『クロスXストラップ』って機能名でベロクロが中向き、外向きと交互になっているが、先っぽが余るとSIDIと同じようにクランクアームに当たる。こっちはカットしてた。(シューズの取説を持ってないんだけど多分カットする前提になってる?)
この写真は極端にやってるけど『ペチン、ペチン』って結構気になる。。。

--------------------
最近やたら来る『緊急対応!』のメールがウザい。全部無視だこんなもん。
タグ :手組ホイールビンディングシューズ
シクロクロスの車体のサドルを交換してとりあえずは車体の方は終わって、外を走っては止まり、走っては止まりでちょこちょこサドルポジションを合わせながらの走行をしてた。
ここのところ雨続きになってしまったのと(多少の雨なら走っちゃうけど)自宅の風呂をユニットごと替えるちょっと大がかりな工事を行っているため、走った後のシャワーも浴びれないので『ヒルクライム佐久』の後からほとんど自転車に乗ってない。
『走れないならホイール組みや他のメンテを…』ということでホイール組みをやってたってのもあったけど、ニップルの入荷が10月ってことで途中で中断のまま。(飾り用の10sロードの前輪(4本組イタリアン)と街乗り用のディスクの後輪(6本組JIS))

来週辺りからまた走れるようになるのでそれまで銭湯通いの日々ってことで。
ここのところ雨続きになってしまったのと(多少の雨なら走っちゃうけど)自宅の風呂をユニットごと替えるちょっと大がかりな工事を行っているため、走った後のシャワーも浴びれないので『ヒルクライム佐久』の後からほとんど自転車に乗ってない。
『走れないならホイール組みや他のメンテを…』ということでホイール組みをやってたってのもあったけど、ニップルの入荷が10月ってことで途中で中断のまま。(飾り用の10sロードの前輪(4本組イタリアン)と街乗り用のディスクの後輪(6本組JIS))
来週辺りからまた走れるようになるのでそれまで銭湯通いの日々ってことで。
たまには足を思いっきり伸ばして風呂に入るってのもいいもんだ。
タグ :ホイール
3連休だったけど(自分は3連休ではないが)前半は雨降りだったのでダートへ出撃、パーツが届いたらシクロ車体へ組んでいくといった感じでシクロクロス車体はとりあえず終了。
ステム、BB周りをやって最後はサドル。サンマルコのアスピデダイナミックに交換。
シクロクロスだと雨、ウエット路面の走行が多いので、穴あきサドルやサドル上、横面に縫い目があると尻が濡れてくるので、そうならない物へ交換。ヒルクライム用でもアスピデを使っていて、他のサドルも付けたことは有るが自分に合うのがこの形状だったので今年はシクロクロス車体もアスピデに。(オクで入手)
で、シクロクロスの本番用のホイールにチューブレスをセットしたので、『使わない間はスリックタイヤに履き替えて街乗り用に~』ってのが気軽に出来なくなったので『街乗り、チョイロード走る用に手持ちのハブ、リムを使えるだけ使って1セット組むか…』からなんかおかしな方向に・・・
〇1本目『シクロのチョイ乗り用の前に、前にオクで入手したアシンメトリックリム(完組リムの新品バラシ品かと)を使ってロードの練習用を組んでしまおう』
今まで練習用で使っていたリムと交換ってことで24hのリム。リム自体は『なんだアレのリムか』と言われるだろうな代物(ステッカーは剥がした)。当然スポークも長さが合わないので交換。


とりあえずアシンメトリックリムで組んだことが無いので組んでみたかった。だけ。
確かに左側(ノンドライブ側)が張れる。あとは実際に乗ってみて…
〇2本目『シクロ練習用で前後ハブセットを購入して、余った前輪用が有るのでそれをマウンテンの前輪に…』
〇3本目『ロード10s用で1組作らないといけないんだっけ…アシンメトリックリムに交換して空いた今までロードの練習用で使ってたリムを使おう…』
〇4本目『じゃあ、シクロの街乗り用の前輪を…』(組んだけど画像無し)
ここまででニップルとスポークが足らなくなって中断。
〇5本目『ロード10s用の前輪を…』スポークは有るけどニップル無しで組めない…(画像無し)
〇6本目『シクロの街乗り用の後輪を…』ハブ、ニップル、スポーク無し。だったけどハブは通販で在庫が有りだったのですぐ来た。(どっちにしろスポーク、ニップルが無いので組めない…)
ハブはシマノのFH-RS505 32H。『ロード11sのスプロケが使えて、クイックリリース(O.L.D135㎜)で安いの』って事でコレ。

…だったのだけれど、自分が『紙のパーツカタログ』として持っているのが2016年のシマノのカタログでそれをみていてハブを探していたけど、ネットで最新のカタログをシマノHPで『フリーハブ』もしくは『ロード ディスク用フリーハブ』とかで検索していくと、ディスク用フリーハブの上のグレードでFH-CX75は新105 R7000シリーズと共にEスルーアクスル、O.L.D142㎜、穴数は28Hのみ(FH-RS770となってO.L.Dは148㎜になってる。ミス?画面下の製品仕様の所は142㎜になってる…)135㎜クイック仕様は載ってない。(市場在庫分のみ?)
FH-RS505(ティアグラグレードになってる)は135㎜、クイック仕様だけの様子。穴数は28H、32H、36Hがあるよう。
ディスクブレーキのリア用O.L.Dは142㎜へ移行していくのか…Eスルーもネジピッチが複数有ったりで、また混乱の素では…
出場した人はパンフに載っていたのでご存知かと思いますが、9/22 13:00からNBS長野放送で『第33回 マウンテンサイクリングin乗鞍』のTV放送がありまっせ。
ステム、BB周りをやって最後はサドル。サンマルコのアスピデダイナミックに交換。
シクロクロスだと雨、ウエット路面の走行が多いので、穴あきサドルやサドル上、横面に縫い目があると尻が濡れてくるので、そうならない物へ交換。ヒルクライム用でもアスピデを使っていて、他のサドルも付けたことは有るが自分に合うのがこの形状だったので今年はシクロクロス車体もアスピデに。(オクで入手)
---------------------
で、シクロクロスの本番用のホイールにチューブレスをセットしたので、『使わない間はスリックタイヤに履き替えて街乗り用に~』ってのが気軽に出来なくなったので『街乗り、チョイロード走る用に手持ちのハブ、リムを使えるだけ使って1セット組むか…』からなんかおかしな方向に・・・
〇1本目『シクロのチョイ乗り用の前に、前にオクで入手したアシンメトリックリム(完組リムの新品バラシ品かと)を使ってロードの練習用を組んでしまおう』
今まで練習用で使っていたリムと交換ってことで24hのリム。リム自体は『なんだアレのリムか』と言われるだろうな代物(ステッカーは剥がした)。当然スポークも長さが合わないので交換。
とりあえずアシンメトリックリムで組んだことが無いので組んでみたかった。だけ。
確かに左側(ノンドライブ側)が張れる。あとは実際に乗ってみて…
〇2本目『シクロ練習用で前後ハブセットを購入して、余った前輪用が有るのでそれをマウンテンの前輪に…』
〇3本目『ロード10s用で1組作らないといけないんだっけ…アシンメトリックリムに交換して空いた今までロードの練習用で使ってたリムを使おう…』
〇4本目『じゃあ、シクロの街乗り用の前輪を…』(組んだけど画像無し)
ここまででニップルとスポークが足らなくなって中断。
〇5本目『ロード10s用の前輪を…』スポークは有るけどニップル無しで組めない…(画像無し)
〇6本目『シクロの街乗り用の後輪を…』ハブ、ニップル、スポーク無し。だったけどハブは通販で在庫が有りだったのですぐ来た。(どっちにしろスポーク、ニップルが無いので組めない…)
ハブはシマノのFH-RS505 32H。『ロード11sのスプロケが使えて、クイックリリース(O.L.D135㎜)で安いの』って事でコレ。
…だったのだけれど、自分が『紙のパーツカタログ』として持っているのが2016年のシマノのカタログでそれをみていてハブを探していたけど、ネットで最新のカタログをシマノHPで『フリーハブ』もしくは『ロード ディスク用フリーハブ』とかで検索していくと、ディスク用フリーハブの上のグレードでFH-CX75は新105 R7000シリーズと共にEスルーアクスル、O.L.D142㎜、穴数は28Hのみ(FH-RS770となってO.L.Dは148㎜になってる。ミス?画面下の製品仕様の所は142㎜になってる…)135㎜クイック仕様は載ってない。(市場在庫分のみ?)
FH-RS505(ティアグラグレードになってる)は135㎜、クイック仕様だけの様子。穴数は28H、32H、36Hがあるよう。
ディスクブレーキのリア用O.L.Dは142㎜へ移行していくのか…Eスルーもネジピッチが複数有ったりで、また混乱の素では…
追記
出場した人はパンフに載っていたのでご存知かと思いますが、9/22 13:00からNBS長野放送で『第33回 マウンテンサイクリングin乗鞍』のTV放送がありまっせ。
タグ :ホイール
前回からの続き。
Rホイールは出来上がり。

シフトワイヤー交換とRディレイラーの清掃を。
作業途中の写真は特に撮ってないが、テンションプーリーの摩耗が結構激しいので撮っといた。
左はロードで使ってたのアルテRD-R8000のテンション(下側の)プーリー、右が今まで車体に着いてたもの(R8000-GSの)。右側のは1/3位歯がすり減って尖ってるね。(期間的には1年は使ってない)同じ物のはずだけど、なんか右側んのは直径が小さいような感じがする。。。
これだけ泥まみれになってるんだから摩耗もするさね。。。

前後のブレーキパッドも交換。
以前『油圧ブレーキだとパッドが摩耗してもブレーキタッチは変わらないはず』と書いたけど、車やバイクだとパッドが減ったらピストンが少しずつ移動してブレーキタッチが変わらないようになってるけど、自転車だと内部構造が違うためかパッドが摩耗していくとブレーキタッチが柔らかくなるよう。パッド交換したらカッチカチのブレーキタッチに戻った。

(交換後にひとっ走りしてるので汚れてますが。。。) また、文章だけの説明になっちゃうが、ブレーキキャリパーとブレーキホースの連結部、ストレートで連結してるけど、そこにカバーが付いてます。MTB用のブレーキホースを購入すると付属してくる本来はシフトレバーに付けるカバーをブレーキキャリパー側にかぶせてます。。。
Rホイールは出来上がり。
シフトワイヤー交換とRディレイラーの清掃を。
作業途中の写真は特に撮ってないが、テンションプーリーの摩耗が結構激しいので撮っといた。
左はロードで使ってたのアルテRD-R8000のテンション(下側の)プーリー、右が今まで車体に着いてたもの(R8000-GSの)。右側のは1/3位歯がすり減って尖ってるね。(期間的には1年は使ってない)同じ物のはずだけど、なんか右側んのは直径が小さいような感じがする。。。
これだけ泥まみれになってるんだから摩耗もするさね。。。
前後のブレーキパッドも交換。
以前『油圧ブレーキだとパッドが摩耗してもブレーキタッチは変わらないはず』と書いたけど、車やバイクだとパッドが減ったらピストンが少しずつ移動してブレーキタッチが変わらないようになってるけど、自転車だと内部構造が違うためかパッドが摩耗していくとブレーキタッチが柔らかくなるよう。パッド交換したらカッチカチのブレーキタッチに戻った。
(交換後にひとっ走りしてるので汚れてますが。。。) また、文章だけの説明になっちゃうが、ブレーキキャリパーとブレーキホースの連結部、ストレートで連結してるけど、そこにカバーが付いてます。MTB用のブレーキホースを購入すると付属してくる本来はシフトレバーに付けるカバーをブレーキキャリパー側にかぶせてます。。。
タグ :シクロクロス
さて、さて、さて、自分のヒルクライムレースシーズンは『ヒルクライム佐久』で終わりで早くも?冬シーズン突入に。
…とはいってもロードに乗らない訳じゃないが。
それにしてもヒルクライムレースやってる日だけ晴れて前後は雨降りっていう…アメダスを見ると9/9は蓼科付近だけ雨雲が南西から流れてこなかった。生け贄を2体捧げた効果か?
それプラス年間5、6戦に出るペースで5年位レースをやっているけど、雨のレースだったのは第30回のマウンテンサイクリングIN乗鞍(三本滝までの短縮になった時の。あれが完全初の乗鞍エコーラインの走行)と2014年?の岐阜の乗鞍スカイライン(あまりの強風で自走下山が禁止になったほど)の2回のみ。それ以外は岐阜も長野も乗鞍はフルコースで好天続きなどで、他のレースでも天気の悪い時でたしかレースの開催時間は雨上がりか山頂付近が霧位のというイベント晴れ率の高さが自分の自慢。
今年は出れないのでエントリーを見送ったレースが雨で開催中止にまでなってるという回避率。
で、シクロクロス車体のシーズンin準備ってことで、中外シフトワイヤーの交換、チェーンをロードで使ってたやつをシクロクロス車へお下がりさせて交換、練習用のRホイールの組み直し、BB、クランク、ステムの清掃辺りを徐々にやっていく予定。(シーズンin準備といっても一昨日とかまで路面濡れてる時とかは普通に乗ってる車体なんだが…)
とりあえず『部屋の中で出来る作業を~』って事でブエルタの録画を見ながらRホイールを。
今まで使っていた¥1,980で購入した何かの完成車についていた中古Rホイールのハブの玉受け(ボディ側)が水、砂などの虫喰いでもうガタガタ、ゴリゴリなのでリムだけ再利用して組み直し。
代わりのハブは新品だけど前後で¥3,980っていうモノに・・・(それでも玉でなくてベアリング使用のモノ)安いのはアルミを多用していなくて、鉄のフリーボディだったり、鉄のハブ軸だったりするためかと。重さは測ってないけど普通に重い。
それとフリ-ボディが8~10s用だが、スプロケが11sだけど11-34Tなので10s用フリーボディで使えるってのがミソ。今回使わないフロントハブはまた何かで使うか…
32H、リア用ディスクなのでJISの6本組でいこうかと。


上の2枚の画像のフランジ、リムに白い点がある(小さいから見えないかも)けど、ディスク取付穴を画像下側の白い棒の所のバルブ穴に0時、6時位置で合わせたかったので基準穴の目印に白ペンでマーキングしているだけ。(ハブボディにメーカーロゴは無しだったので)

で、右落としで通して組んでいくっと…(スポークは#14プレーンで290㎜と292㎜でなんとか手持ち残りが有った。)



ブエルタ第15ステージ。ティボー・ピノようやった!!ステージ勝利おめっとー!
力尽きたので今回はここで終了---。。。
…とはいってもロードに乗らない訳じゃないが。
それにしてもヒルクライムレースやってる日だけ晴れて前後は雨降りっていう…アメダスを見ると9/9は蓼科付近だけ雨雲が南西から流れてこなかった。生け贄を2体捧げた効果か?
それプラス年間5、6戦に出るペースで5年位レースをやっているけど、雨のレースだったのは第30回のマウンテンサイクリングIN乗鞍(三本滝までの短縮になった時の。あれが完全初の乗鞍エコーラインの走行)と2014年?の岐阜の乗鞍スカイライン(あまりの強風で自走下山が禁止になったほど)の2回のみ。それ以外は岐阜も長野も乗鞍はフルコースで好天続きなどで、他のレースでも天気の悪い時でたしかレースの開催時間は雨上がりか山頂付近が霧位のというイベント晴れ率の高さが自分の自慢。
今年は出れないのでエントリーを見送ったレースが雨で開催中止にまでなってるという回避率。
-------------------
で、シクロクロス車体のシーズンin準備ってことで、中外シフトワイヤーの交換、チェーンをロードで使ってたやつをシクロクロス車へお下がりさせて交換、練習用のRホイールの組み直し、BB、クランク、ステムの清掃辺りを徐々にやっていく予定。(シーズンin準備といっても一昨日とかまで路面濡れてる時とかは普通に乗ってる車体なんだが…)
-------------------
とりあえず『部屋の中で出来る作業を~』って事でブエルタの録画を見ながらRホイールを。
今まで使っていた¥1,980で購入した何かの完成車についていた中古Rホイールのハブの玉受け(ボディ側)が水、砂などの虫喰いでもうガタガタ、ゴリゴリなのでリムだけ再利用して組み直し。
代わりのハブは新品だけど前後で¥3,980っていうモノに・・・(それでも玉でなくてベアリング使用のモノ)安いのはアルミを多用していなくて、鉄のフリーボディだったり、鉄のハブ軸だったりするためかと。重さは測ってないけど普通に重い。
それとフリ-ボディが8~10s用だが、スプロケが11sだけど11-34Tなので10s用フリーボディで使えるってのがミソ。今回使わないフロントハブはまた何かで使うか…
32H、リア用ディスクなのでJISの6本組でいこうかと。
上の2枚の画像のフランジ、リムに白い点がある(小さいから見えないかも)けど、ディスク取付穴を画像下側の白い棒の所のバルブ穴に0時、6時位置で合わせたかったので基準穴の目印に白ペンでマーキングしているだけ。(ハブボディにメーカーロゴは無しだったので)
で、右落としで通して組んでいくっと…(スポークは#14プレーンで290㎜と292㎜でなんとか手持ち残りが有った。)
-------------------
ブエルタ第15ステージ。ティボー・ピノようやった!!ステージ勝利おめっとー!
力尽きたので今回はここで終了---。。。